公開日:2025.05.07
統合失調症の人に向いている仕事とは?特性に合った職種と仕事を続けるためのポイントを解説
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- 統合失調症の人に向いている仕事とは?特性に合った職種と仕事を続けるためのポイントを解説

- このコラムのまとめ
- 統合失調症の方の「長く続く仕事選び」にはコツがあります。マイペースに取り組める事務や軽作業などの適職例から、ストレスを溜めない職場環境の見極め方までを解説。一人で抱え込まず、医師や就労支援機関を味方につけて復職するための具体的なステップを紹介します。無理せず自分らしく働くためのヒントをまとめました。
もくじ
もっと見る
統合失調症の人に向いている仕事6選
統合失調症を抱えながらも、症状と上手く付き合いながら働くことは十分に可能です。大切なのは、自分の特性や症状に合った仕事を選ぶことです。ここでは、統合失調症の方に特に向いているとされる仕事を6つ紹介します。
①ルーティンワーク中心の事務職
事務職は統合失調症の方に適している仕事の代表例です。特に書類作成やデータ入力などのルーティンワークが中心の事務職は、一度覚えてしまえば同じ作業を繰り返すため、認知機能障害があっても業務を進めやすい特徴があります。
マニュアル化された業務が多く、判断に迷うことが少なく、オフィス環境は比較的刺激が少ないため落ち着いて働けます。ただし、来客対応や電話応対が業務に含まれる場合もあるため、採用面接時に業務内容をよく確認しましょう。
②少人数環境での軽作業・商品管理
倉庫や流通センターでの商品管理や軽作業も、統合失調症の方に向いています。検品作業や商品の仕分け、ピッキング作業などは比較的単純な作業の繰り返しが中心となり、人との接触が少なく、対人ストレスが比較的少ないのが特徴です。
③マイペースに取り組める製造業
工場などでの製造業も、統合失調症の方に適した職場環境を提供することが多い業種です。特に、ライン作業や組み立て作業など、一定の手順で進める作業が中心の職場が向いています。作業手順が明確で予測可能性が高く、同じ作業の繰り返しが多いのが特徴です。
④自分のペースで働けるリモートワーク
近年増加しているリモートワークは、統合失調症の方にとって働きやすい選択肢の一つです。自宅など落ち着いた環境で働くことができるため、症状による影響を受けにくくなります。通勤によるストレスや疲労を避けられ、自分の体調に合わせて休憩を取りやすいのが大きな利点です。
統合失調症当事者(35歳男性)
⑤創造性を活かせるデザイン・イラスト制作
統合失調症の方の中には、創造的な才能を持つ人も少なくありません。デザインやイラスト制作などのクリエイティブな仕事は、そうした才能を活かせる職業の一つです。独自の視点や感性を強みにでき、比較的一人で作業を進められることが多いのが特徴です。
⑥「人間関係」を断捨離できるフリーランス
会社員としての「通勤」や「複雑な人間関係」がどうしても辛い場合、フリーランス(個人事業主)も選択肢の一つです。
働く時間も場所も自分で決められるため、体調に合わせて「今日は休む」「調子が良い夜に働く」といった調整ができるのが最大の強みです。
ただし、自由である反面、「体調を崩しても誰も代わってくれない」「収入が不安定になりやすい」というプレッシャーも伴います。いきなり本業にするのではなく、まずは副業や、就労継続支援B型での作業などを通じて、「一人で仕事を完結させるリズム」を作れるか試してみるのがおすすめです。
統合失調症の方が仕事を選ぶ際には、自分の症状の特徴や得意なこと、苦手なことをよく理解した上で、無理なく続けられる仕事を探すことが大切です。また、就労支援機関を活用して、自分に合った仕事探しのサポートを受けることもおすすめします。
統合失調症の人の仕事選びで重視すべき7つのポイント
統合失調症の方が仕事を選ぶ際には、自分の症状や特性に合った環境を見つけることが何よりも重要です。ここでは、就職活動や転職を考える際に押さえておきたい7つのポイントを解説します。
①自分の症状の特徴を理解する
仕事選びの第一歩は、自分自身の症状や特性を正確に把握することです。陽性症状と陰性症状のどちらが強いか、症状が出やすい状況や環境の特徴、集中力が持続する時間の目安などを理解しておきましょう。主治医やカウンセラーと一緒に自己分析を行うと、より客観的な視点が得られます。
②無理なく働ける時間・環境を優先する
統合失調症の方は体力や集中力の面で制約を感じることが多いため、まずは無理なく働ける時間や環境を最優先に考えることが大切です。時短勤務やフレックスタイム制度がある職場、通勤時間が短い職場、リモートワークが可能な職場など、自分の状態に合わせた環境を選びましょう。
統合失調症当事者(30代女性)
③特性に合った仕事内容を選ぶ
統合失調症の特性に合いやすい仕事は、作業手順が明確でマニュアル化されている、ルーティンワークが中心で予測可能性が高い、自分のペースで進められる、対人コミュニケーションの負担が少ないなどの特徴があります。自分の得意なことや興味のある分野を活かせる仕事を見つけることで、やりがいを感じながら働けるでしょう。
④必要に応じて症状を職場に伝える
統合失調症があることを職場に伝えるかどうかは、個人の判断によります。伝えることで症状に応じた配慮が受けられるメリットがある一方、偏見を受けるリスクもあります。病名だけでなく、「こういう状況で困ることがある」「このような配慮があるとありがたい」など、具体的な対応策と合わせて伝えると理解を得やすくなります。
⑤一般雇用と障害者雇用のメリット・デメリットを比較する
統合失調症の方は、一般雇用と障害者雇用のどちらの道も選択できます。一般雇用は求人の選択肢が広く給与水準も比較的高いですが、体調面への配慮が少ない場合があります。一方、障害者雇用は症状に合わせた配慮が受けやすく長期的に安定して働ける可能性が高いですが、求人数が限られ給与水準も低めの傾向があります。自分の状況と希望に合わせて選択しましょう。
⑥「働きたい」という気持ちを、まずは主治医へ
仕事選びで最も怖いのは、自分の体調を過信して無理な環境に飛び込み、再発してしまうことです。自分では「元気だ」と思っていても、医学的に見ればまだエネルギー不足、というケースは少なくありません。
求人に応募する前に、必ず主治医に「この条件で働こうと思うけれど、どう思いますか?」と相談してください。医師は、今のあなたの服薬状況や睡眠リズムから、「今のあなたにとって安全なライン」を客観的に判断してくれます。医師の「GOサイン」を、就職活動のスタートラインにしましょう。
⑦就職活動を「チーム戦」にする
統合失調症の方の就職活動は、一人で行うには負担が大きすぎます。求人探しから面接対策、そして企業との交渉まで、すべてを一人で背負う必要はありません。
ハローワークや就労移行支援事業所などのスタッフを、あなたの「専属エージェント」として頼ってください。「自分の口からは言い出しにくい配慮事項」を企業に伝えてくれたり、自分では気づかなかった「向いている仕事」を提案してくれたりと、彼らはあなたの強力な味方になります。プロとチームを組むことが、長く続く仕事に出会う近道です。
統合失調症の人が仕事で抱えやすい5つの悩み
統合失調症の方が仕事をする上では、様々な困難に直面することがあります。症状と仕事との両立に悩む方は少なくありません。ここでは、統合失調症の方が職場で抱えやすい5つの代表的な悩みについて解説します。

①周囲の目や幻覚・幻聴による集中力低下
統合失調症の陽性症状として現れる幻覚や幻聴は、仕事中の集中力に大きな影響を与えることがあります。「周囲からの視線が気になる」「誰かが自分の悪口を言っているように聞こえる」といった症状により、業務に集中できず作業効率が落ちてしまうことがあります。
統合失調症当事者(30代男性)
②身体的・精神的な疲労の蓄積
統合失調症の方は、一般的に疲れやすい傾向があります。これは症状自体の影響や薬の副作用によるものです。同じ業務量でも、他の人よりも多くのエネルギーを消費してしまうため、疲労が蓄積しやすくなります。疲労が溜まると症状が悪化するリスクも高まります。
③陰性症状によるモチベーション維持の難しさ
統合失調症の陰性症状には、感情表現の乏しさや意欲の低下、無気力などがあります。これらの症状により、仕事へのモチベーションを維持することが難しくなることがあります。周囲からは「やる気がない」と誤解されることもあり、職場での人間関係にも影響を及ぼす場合があります。
④認知機能の変化による業務遂行の困難
統合失調症では、記憶力、注意力、判断力などの認知機能に変化が生じることがあります。指示を覚えておくことが難しく、複数の業務を同時に進めることができない、優先順位をつけて計画的に業務を進めることが難しいなどの困難が生じる場合があります。
| 仕事中の「困った」あるある | 心の中で起きていること |
|---|---|
| 指示が覚えられない | 話を聞いている時は分かったつもりでも、メモを取る前に「あれ、何だっけ?」と情報が指の隙間からこぼれ落ちてしまう。 |
| ミスが増える | 集中しようとしても、周囲の雑音や他のタスクが気になり、注意のスポットライトを一点に当て続けられない。 |
| 優先順位が選べない | 「コピーをとる」と「メールを返す」、どちらも同じくらい重要に見えてしまい、フリーズしてしまう。 |
⑤周囲の視線が「痛い」と感じる(対人ストレス)
職場において、業務内容以上にエネルギーを削られるのが「人間関係」です。
特に病気の特性(陽性症状の残りなど)として、他人の何気ないひと言を「自分への攻撃」と受け取ってしまったり、ヒソヒソ話を「悪口」と感じてしまったりすることがあります。
これは性格の問題ではなく、脳のアンテナが敏感になりすぎている状態です。この緊張感が続くと、また症状が悪化するという悪循環に陥りやすいため、「あえて一人になる時間を作る」などの自衛策が必要です。
統合失調症の人に向いていない仕事の特徴
統合失調症の方が仕事を選ぶ際には、自分に合った環境を見つけることが重要です。一方で、症状を悪化させたり、過度のストレスを感じやすい職種もあります。ここでは、統合失調症の方にとって一般的に向いていないと考えられる仕事の特徴を解説します。
ストレスが多い高プレッシャーな職種
統合失調症の方は一般的にストレスに対する脆弱性があり、高ストレス環境下では症状が悪化するリスクが高まります。締め切りに追われる仕事や数値目標の達成が求められる仕事は、大きな精神的負担となる可能性があります。
避けた方が良い高プレッシャーな職種の例としては、ノルマのある営業職、締切に追われる編集・報道関係、証券トレーダーなどの金融業界、緊急対応が求められるコールセンターなどが挙げられます。これらの職種では常に高いパフォーマンスを求められることが多く、統合失調症の方には大きなストレス要因となりやすいでしょう。
統合失調症当事者(35歳男性)
長時間労働が求められる職場
統合失調症の方は一般的に疲れやすく、長時間の労働や不規則な勤務時間は体調管理の面で大きな負担となります。また、薬の服用や十分な睡眠確保などの自己管理も難しくなります。
避けた方が良い長時間労働の職場としては、残業が常態化している職場、夜勤や交代制勤務がある仕事、24時間対応が求められるサービス業などがあります。特に問題なのは勤務時間の不規則さで、規則正しい生活リズムの維持が困難になると症状の悪化につながることがあります。
複雑な人間関係を要する接客業・営業職
統合失調症の方の中には、対人関係に強いストレスを感じる方も少なくありません。多数の人と関わる接客業や、相手の反応を読み取りながら対応を変える必要がある営業職は、大きな負担となる可能性があります。
例えば、飲食店のホールスタッフ、百貨店や小売店の販売員、ホテルのフロントスタッフ、クレーム対応が多いカスタマーサービスなどは、対人的なストレスが高まりやすい環境です。
判断ミスが許されない医療・安全系職種
統合失調症の方は、症状による集中力の低下や認知機能の変化によって、瞬時の判断や正確性が求められる仕事で困難を感じることがあります。特に、判断ミスが人命に関わるような職種は大きな負担となります。
医師・看護師などの医療従事者、薬剤師、操縦士・航空管制官、電車・バスの運転手、警察官・消防士など緊急対応職は、一瞬の判断ミスが重大な事故や人命に関わる問題を引き起こす可能性があるため注意が必要です。
統合失調症の方が仕事を選ぶ際に重要なのは、自分の症状や特性を正確に理解し、無理のない環境を選ぶことです。主治医や就労支援の専門家と相談しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
統合失調症の人が活用できる就労支援制度・機関5選
統合失調症の方の就職成功の鍵は、ズバリ「周りを巻き込むこと」です。
自分一人で求人を探し、病気のことを企業に説明し、配慮をお願いするのは至難の業です。これから紹介する5つの機関は、そうした「言いにくい交渉」や「自分に合う仕事探し」を代行・サポートしてくれる専門チームです。使えるリソースはすべて使い倒し、最短ルートで自分らしい働き方を手に入れましょう。
①就労移行支援事業所のサポート
就労移行支援事業所は、障害者総合支援法に基づいて運営される福祉サービスで、障害のある方の一般就労をサポートする施設です。ビジネスマナーやパソコンスキルなどの訓練、職場体験、就職活動支援、就職後の定着支援など、就労に関する総合的なサポートを最長2年間受けることができます。
②ハローワーク(障害者専門窓口)の活用法
ハローワークには、障害のある方の就職をサポートするための専門窓口があります。障害特性に配慮した職業相談や職業紹介、トライアル雇用制度の利用など、就職活動に関する様々なサポートを無料で受けられます。精神障害者雇用トータルサポーターという専門スタッフも配置されています。
③地域障害者職業センターのサービス
地域障害者職業センターでは、職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援など、専門的な職業リハビリテーションを受けることができます。特にジョブコーチ支援では、実際の職場で働く際に生じる課題に対して、専門家が直接職場を訪問してサポートしてくれます。
統合失調症当事者(40代女性)
④障害者就業・生活支援センターの総合的支援
障害者就業・生活支援センターでは、就業面と生活面の両方を一体的に支援しています。就職活動のサポートだけでなく、生活習慣の形成、健康管理、金銭管理などの生活面の助言も受けられるため、仕事と生活の両立に悩む統合失調症の方に特に役立ちます。
⑤精神障害者保健福祉手帳と各種助成制度
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、障害者雇用枠での就職、通勤や通院のための交通費の割引、税制優遇など、様々な支援や優遇措置を受けることができます。また、企業が障害者を雇用する際の各種助成金制度もあり、雇用の促進につながっています。
これらの支援制度や機関を積極的に活用することで、統合失調症の方も自分の特性や希望に合った職場を見つけやすくなります。まずは身近な支援機関に相談してみることから始めるとよいでしょう。
関連記事

就労継続支援A型とは?仕事内容・平均給料・利用条件を徹底解説
就労継続支援A型は、障害や難病のある方が雇用契約に基づいて働ける障害福祉サービスです。最低賃金が保障され、個々の障害特性に配慮した就労環境で、自分のペースで働きながらスキルを習得できます。

就労継続支援B型とは?仕事内容・工賃・選び方まで徹底解説
就労継続支援B型は、障害や難病のある方が自分のペースで働ける福祉サービスです。雇用契約を結ばずに働き、様々な作業を通じて就労経験を積むことができます。工賃や利用条件、選び方、利用手続きなど、就労継続支援B型について知っておきたい情報を詳しく解説した記事です。
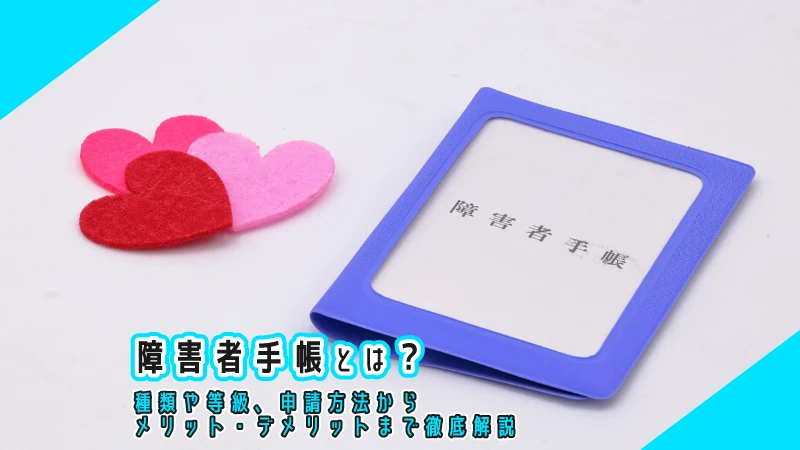
障害者手帳とは?種類や等級、申請方法からメリット・デメリットまで徹底解説
障害者手帳の基本知識から申請方法、メリットまで徹底解説。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の種類や等級、取得方法、受けられる支援サービスを詳しく紹介。手帳がなくても利用できる支援制度も解説しています。障害のある方の生活をサポートする情報が満載です。
統合失調症の人の職場復帰・再就職のポイント
統合失調症により休職した経験がある方や、症状が安定して再就職を考えている方にとって、どのように職場に戻るか、あるいは新しい職場を見つけるかは大きな課題です。ここでは、職場復帰や再就職を成功させるためのポイントを解説します。
休職からの段階的な復帰プロセス
統合失調症により休職した場合、いきなり元の業務量や勤務時間に戻ることは避け、段階的に復帰するプロセスを踏むことが重要です。まずは主治医と復職可能かどうかの相談から始め、短時間勤務から徐々に時間を増やしていく方法が効果的です。
統合失調症当事者(40代男性)
症状に合わせた働き方の再設計
職場復帰や再就職では、過去の経験から学び、自分の症状や特性に合わせた働き方を再設計することが大切です。勤務時間や日数の調整、業務内容の見直し、職場環境の調整など、症状と上手く付き合いながら長く続けられる方法を考えましょう。
再発予防のための環境調整
統合失調症は環境要因によって症状が悪化することがあるため、再発を予防するための環境調整も重要です。ストレス要因の特定と対策、症状の前兆サインの把握、定期的な通院・服薬の継続、生活リズムの規則化などが効果的です。
特に重要なのは、症状の前兆サインを把握しておくことです。「音が急に大きく聞こえる」「人の会話が気になる」といった変化に早めに気づき、必要な対処を行うことで、大きな再発を防ぐことができます。
病気が教えてくれた「方向転換」のサイン
統合失調症の発症は、辛い経験であると同時に、「これまでの働き方が、あなたの心と体に合っていなかった」という体からのSOSでもあります。
もし、前の職場のストレスが原因で体調を崩したのであれば、無理して元のレールに戻る必要はありません。「自分を守るために、道を変える」という選択は、決して逃げではなく、賢明な判断です。
ただ、いきなり全く違う業界に飛び込むのはリスクが高すぎます。まずは焦らず、以下のような「慣らし運転」から始めてみませんか?
- 原因の棚卸し:「仕事内容」が辛かったのか、「人間関係」が重荷だったのか。ノートに書き出して、次はそれを避ける条件を探す。
- お試し就労:いきなりフルタイムを目指さず、週数回のアルバイトや在宅ワークで「働く感覚」だけを取り戻す。
- プロに頼る:就労移行支援などを利用して、新しいスキルを身につけながら、自分に合う職種を客観的に見てもらう。
統合失調症とは?仕事に影響する主な症状
統合失調症は、思考や感情、行動などの統合機能に障害が生じる精神疾患です。約100人に1人が発症するとされており、適切な治療と支援があれば多くの方が症状と付き合いながら社会生活を送ることができます。
統合失調症の基本的な特徴と発症率
統合失調症は10代後半から30代前半に発症することが多く、男女差はほとんどありません。遺伝的要因とストレスなどの環境要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。早期発見・早期治療が予後を大きく左右するため、症状に気づいたら早めに専門医に相談することが重要です。
陽性症状と仕事への影響
陽性症状は幻覚、妄想、思考の障害などが含まれます。これらの症状により、会議中に集中できない、同僚が自分の悪口を言っていると感じる、考えがまとまらず報告書作成が困難になるなど、仕事のパフォーマンスに大きな影響を与えることがあります。
陰性症状と仕事への影響
陰性症状は感情の平板化、意欲・自発性の低下、社会的引きこもりなどです。これらの症状は対人関係の困難、業務へのモチベーション維持の難しさなどにつながり、職場での評価にも影響することがあります。
認知機能障害と仕事のパフォーマンス
統合失調症では注意力、記憶力、判断力、情報処理能力などの認知機能にも影響が出ることがあります。これにより指示を覚えられない、マルチタスクが苦手、優先順位の判断が難しいなどの問題が生じることがあります。
まとめ:「根性」ではなく「環境」で勝負する
統合失調症と診断されても、適切な治療と環境調整、そして自分に合った仕事選びによって、充実した職業生活を送ることは十分可能です。ルーティンワーク中心の事務職や、少人数環境での軽作業、リモートワークなど、様々な働き方の中から自分の特性に合った仕事を見つけることが大切です。
統合失調症の方が活躍できるかどうか。その9割は、本人の能力ではなく「環境との相性」で決まると言っても過言ではありません。
「刺激の少ない静かな環境」「急かされない業務」「困った時に相談できる体制」。こうした条件さえ整えば、病気があっても驚くほどのパフォーマンスを発揮できる方はたくさんいます。
もし今、働くことに不安を感じているなら、それはあなたの心が弱いからではなく、まだ「合う場所」に出会えていないだけかもしれません。
支援制度や専門家をフル活用して、あなたを守ってくれる「安全な職場」をあきらめずに探しましょう。





