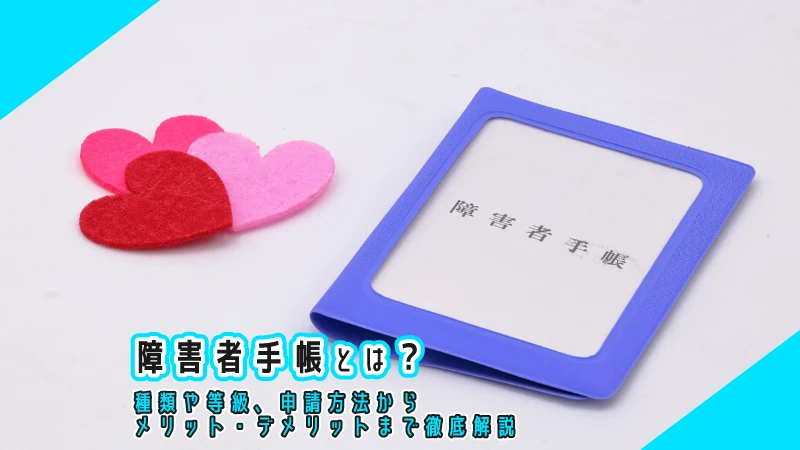公開日:2025.05.09
統合失調症による休職から復職までの完全ガイド~成功への道筋と支援制度~
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- 統合失調症による休職から復職までの完全ガイド~成功への道筋と支援制度~

- このコラムのまとめ
- 統合失調症による休職から復職までのガイドです。症状の基本知識から休職手続き、休職中の過ごし方、復職準備のポイントまで解説。服薬管理や再発サインの早期発見など働き続けるためのコツや、現職復帰が難しい場合の選択肢も紹介。統合失調症があっても適切な支援と自己管理で充実した職業生活を送ることができます。
もくじ
もっと見る
統合失調症と仕事の両立が難しくなったときの選択肢
統合失調症は約100人に1人がかかるとされている精神疾患で、症状によって仕事に影響が出ることがありますが、適切な対応で両立も可能です。症状が悪化して働きづらさを感じたとき、どのような選択肢があるか知っておくことが大切です。
統合失調症の症状が仕事に与える影響
統合失調症の症状は、職場での業務遂行能力や人間関係に様々な影響を与えます。
- 集中力の低下:幻覚や妄想により、仕事に集中することが難しくなります。職場の同僚が自分の噂をしているように感じたり、監視されているような感覚を持つことで、業務に集中できなくなることがあります。
- 意欲の低下:陰性症状による社会性の喪失や感情の平板化によって、仕事への興味や意欲が低下します。
- 認知機能の障害:記憶力の低下により新しい業務を覚えるのに時間がかかったり、判断力の低下により計画的に仕事を進めることが困難になります。
休職すべきタイミングとその判断基準
統合失調症の症状が悪化し、仕事に支障が出ている場合は、休職を検討するタイミングかもしれません。
- 症状の悪化:幻覚や妄想が強くなり、現実との区別が困難になっている
- 業務への影響:ミスが増える、納期に間に合わない、業務の質が低下している
- 医師の判断:主治医から休職を勧められている
- 再発のサイン:睡眠障害、イライラの増加、食欲不振などの前兆が見られる
産業医
休職以外の選択肢(時短勤務・配置転換など)
症状の程度によっては、完全に休職せずに働き方を調整することで仕事を続けられる場合もあります。
- 時短勤務:フルタイムではなく、短時間の勤務から始めることで、体調や症状に合わせた働き方ができます。
- 配置転換:現在の業務が症状に負担を与えている場合、より負担の少ない部署や業務への異動を検討します。
- 業務内容の調整:担当する仕事の量や難易度、締め切りなどを調整してもらいます。
| 統合失調症に適した仕事の特徴 | 統合失調症に不向きな仕事の特徴 |
|---|---|
| ・人と接する機会が少ない仕事 ・判断力をあまり必要としない単純作業 ・新たに覚えることが少ない仕事 ・残業が少なく定時で帰れる仕事 |
・時間が不規則な仕事 ・高いストレスがかかる仕事 ・複雑な判断や交渉が必要な仕事 ・締め切りに追われる仕事 |
統合失調症の症状は人によって異なるため、自分の特性や症状をよく理解し、それに合った働き方を選択することが重要です。必要に応じて、医師や専門機関のアドバイスを受けながら、最適な選択肢を検討しましょう。
統合失調症の基本知識~休職・復職を考える前に~
統合失調症は以前「精神分裂病」と呼ばれていましたが、2002年に現在の名称に変更されました。この疾患について正しく理解することは、休職から復職へのプロセスを円滑に進める上で非常に重要です。
統合失調症の主な症状
統合失調症の症状は大きく「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分類されます。
陽性症状(幻覚・妄想・自我障害)
健康な状態では見られない症状が新たに加わった状態です。
- 幻覚:実際には存在しないものを感覚として感じること。最も多いのは「幻聴」で、誰もいないのに声が聞こえます。
- 妄想:あり得ないことを強く信じ、訂正されても受け入れられない状態。被害妄想や関係妄想などがあります。
- 自我障害:自分の考えが人に伝わっていると感じたり、誰かに考えや体を操られていると感じたりします。
陰性症状(意欲低下・感情の平板化)
健康な時にはあったものが失われる症状です。
- 社会性の喪失:他人との関わりに興味を失い、引きこもる傾向があります。
- 感情鈍麻:喜怒哀楽の表現が乏しくなり、表情が平板になります。
- 意欲の低下:何事にも関心を示さず、自発的な行動が減少します。
認知機能障害
思考や記憶、注意力などの知的な機能に影響が出ます。
- 記憶力の低下:物事を覚えるのに時間がかかったり、覚えられなくなります。
- 集中力の低下:仕事や活動に集中できなくなります。
- 判断力の低下:計画を立てたり優先順位をつけることが難しくなります。
精神科医
治療法と服薬の重要性
統合失調症の治療は「薬物療法」「精神療法」「リハビリテーション」の3つの柱から成り立っています。
- 薬物療法:抗精神病薬による治療が基本です。「寛解」状態になっても、服薬を中止すると1年以内に60~70%の人が再発するため、継続が非常に重要です。
- 精神療法:医師やカウンセラーとの対話を通じて、病気の理解や症状への対処法を学びます。
- リハビリテーション:社会復帰に向けた訓練やサポートを行います。
統合失調症は、適切な治療と支援があれば、症状をコントロールしながら充実した生活を送ることができます。
自分の症状や治療について理解を深め、医療専門家と協力しながら、休職から復職へのプロセスを進めていきましょう。
統合失調症での休職手続きと準備
統合失調症の症状が悪化し、医師から休職を勧められた場合や自身で仕事の継続が難しいと判断した場合、適切な手続きを踏んで休職することが重要です。ここでは、スムーズに休職するための手続きと経済的支援制度について解説します。

医師への相談と診断書の取得
休職を検討する場合、まず主治医に相談し、休職の必要性を判断してもらうことが重要です。
- 診断書の依頼:会社に提出するための診断書を発行してもらいます。診断書には通常、診断名、症状、休職の必要性と推奨期間などが記載されます。
- 発行期間:診断書の発行には1日〜2週間程度かかるため、早めに依頼しましょう。
会社への休職申請の伝え方
医師から休職の必要性を認められたら、会社に休職の申請を行います。
- 上司への報告:直属の上司に休職の意向を伝えます。体調が優れない場合は電話やメールでも構いません。
- 診断書の提出:医師から発行された診断書を会社に提出します。
- 休職期間と条件の確認:休職期間中の給与や手当、復職条件などについて確認します。
産業医
休職中に利用できる経済的支援制度
休職中の収入減少に備え、以下の支援制度を活用できます。
- 傷病手当金:健康保険から支給される手当で、標準報酬日額の3分の2が最長1年6ヶ月支給されます。
- 自立支援医療制度:医療費の自己負担が原則1割に軽減される制度です。
- 障害年金:症状の程度により等級が決まり、長期的な所得保障を受けられます。
これらの支援制度を適切に活用することで、経済的な不安を軽減し、治療に専念することができます。症状や状況に応じて、どの制度が最適かを医師やソーシャルワーカーなどの専門家に相談しながら判断するとよいでしょう。
統合失調症の休職中の過ごし方~復職への土台作り~
統合失調症による休職期間は、単に症状を回復させるだけでなく、将来の復職に向けた準備期間としても大切です。この時期をどのように過ごすかによって、復職後の適応や再発リスクも大きく変わってきます。
治療に専念するための環境整備
休職期間中は、まず治療に専念できる環境を整えることが最優先です。
- 信頼できる医師との関係構築:同じ医師のもとで継続的に治療を受けることが重要です。医療機関を頻繁に変えると治療の一貫性が損なわれます。
- 服薬管理の徹底:処方された薬は医師の指示通りに服用しましょう。自己判断での減薬や断薬は避けてください。
- 静かで落ち着ける生活空間の確保:自宅内にリラックスできる空間を作り、過剰な刺激を避けましょう。
規則正しい生活リズムの確立
統合失調症の回復と再発予防には、規則正しい生活リズムが非常に重要です。
- 睡眠リズムの安定:毎日同じ時間に起床・就寝し、特に朝日を浴びることで体内時計を整えます。
- 規則正しい食事:1日3食、決まった時間に栄養バランスの良い食事を摂りましょう。
- 適度な活動と休息のバランス:体調に合わせて軽い家事や散歩などの活動を取り入れつつ、疲れを感じたらしっかり休みましょう。
リワーク施設の活用方法
休職から職場復帰を目指す過程で、リワーク施設の活用が効果的です。
- リワークプログラムの内容:生活リズムの改善、ビジネススキルの向上、ストレス対処法、体力づくり、集中力・持続力の向上などのプログラムが提供されています。
- リワーク施設の効果:職場と同様の環境で訓練することで復職への準備ができ、専門家のサポートも受けられます。利用した場合の職場定着率は、利用しなかった場合の3倍以上という調査結果もあります。
リワーク施設スタッフ
統合失調症からの復職準備と成功のポイント
休職期間中の治療や生活リズムの改善により症状が安定してきたら、いよいよ復職に向けた具体的な準備を始める段階です。統合失調症からの復職は、焦らず段階的に進めることが重要です。
復職のタイミングを見極める方法
復職のタイミングは、早すぎても遅すぎても問題があります。適切な時期を見極めましょう。
- 医師の判断を最優先:復職可能かどうかの判断は、まず主治医に相談しましょう。
- 症状の安定:幻覚や妄想などの陽性症状が十分にコントロールされ、認知機能も回復していることが必要です。
- 生活リズムの安定:職場と同様の生活リズムが維持できているか確認します。
- 体力の回復:通勤や勤務時間中の活動に耐えられる体力が回復しているか確認します。
段階的な復職プラン作成のコツ
一気に元の働き方に戻るのではなく、段階的に負荷を上げていくプランを立てましょう。
- 時間的配慮:最初は週2〜3日の半日勤務から始め、徐々にフルタイム勤務へ移行します。
- 業務内容の調整:復職初期は単純作業や補助的業務から始め、徐々に通常業務に戻します。
- 定期的な振り返り:週単位や月単位で状況を振り返り、必要に応じてプランを調整します。
復職時に会社に求められる配慮事項
復職を成功させるためには、会社側の適切な配慮も重要です。
- 業務量の調整:最初は少ない業務量から始め、徐々に増やしていく配慮が必要です。
- フレックスタイム制の活用:通院や体調に合わせて勤務時間を調整できると便利です。
- 静かな作業環境:集中しやすい環境で作業できるよう配慮してもらえると良いでしょう。
産業医
復職は焦らず、段階的に、そして必要な配慮を受けながら進めることが成功の鍵です。小さな成功体験を積み重ねていくことが、長期的な職場定着につながります。
統合失調症と上手に付き合いながら働き続けるためのポイント
統合失調症は完全に治すことは難しいですが、適切な治療と自己管理によって症状をコントロールしながら、長期的に働き続けることが可能です。復職後も安定した就労を続けるためのポイントを紹介します。
服薬管理と通院の継続
症状コントロールと再発防止において、最も重要なのが服薬の継続と定期的な通院です。
- 服薬の重要性:「寛解」状態でも、薬の服用を止めると1年以内に60~70%の人が再発します。症状がなくなっても、薬が効いているからこそ症状が抑えられています。
- 服薬管理のコツ:毎日決まった時間に服薬する習慣をつけ、お薬カレンダーやアプリを活用しましょう。
- 定期的な通院:症状が安定していても、定期的に通院して状態を報告することが大切です。
再発サインの早期発見と対処法
再発する前の兆候に早期に気づき、適切に対処することが重要です。
- 自分の再発サインを知る:眠れない日が続く、イライラしやすい、食欲がない、不安や焦りが強いなど、自分に当てはまるサインを把握しておきましょう。
- 対処法:再発の兆候を感じたら、すぐに主治医に相談し、十分な休息をとり、ストレスとなる状況を避けましょう。
ストレスを溜めない働き方の工夫
統合失調症の再発にはストレスが関わっています。過度なストレスを溜めない工夫が大切です。
- 業務の管理:仕事の優先順位をつけ、一度に一つの業務に集中し、定期的に短い休憩をとりましょう。
- コミュニケーションの工夫:困ったことがあれば早めに相談し、自分の状態や限界を適切に伝えましょう。
- ストレス管理:趣味や楽しみの時間を定期的に確保し、リラクゼーション技法を実践しましょう。
カウンセラー
統合失調症と上手に付き合いながら働き続けるためには、これらのポイントを意識し、必要に応じて医療機関や支援機関のサポートを受けながら、自分らしい働き方を見つけていきましょう。
統合失調症で現職復帰が難しい場合の選択肢
統合失調症の治療を続け、症状が安定してきても、元の職場に戻ることが難しいと感じる場合があります。これは決して珍しいことではなく、新たな選択肢を検討することが、より良い働き方につながることもあります。
転職を考えるタイミングと判断基準
現職への復帰が難しいと感じた場合、転職を検討することも一つの選択肢です。
- 転職を考えるタイミング:現職の環境が症状悪化の要因になっている、適切な配慮が得られない、休職を繰り返している、復職プログラムを行っても適応が難しいといった状況になったときです。
- 判断基準:主治医の意見、現在の症状と職場環境の相性、経済的状況、自分の適性に合った職種の有無などを総合的に判断します。
キャリアカウンセラー
障害者雇用での就労
統合失調症により一般雇用での就労が難しい場合、障害者雇用枠での就労を検討することも選択肢です。
- 障害者雇用のメリット:障害特性に配慮された環境、柔軟な勤務時間、通院への理解、就労支援機関のサポートを受けやすいなどがあります。
- 障害者手帳の取得:精神障害者保健福祉手帳を取得すると、障害者雇用枠での就労や各種サービスの利用が可能になります。統合失調症の初診から6ヶ月以上経過していることが条件です。
就労支援機関の活用
新たな就労先を探す際には、専門の支援機関を活用することが効果的です。
- ハローワーク(障害者窓口):障害特性に配慮した職業紹介や就労支援が受けられます。障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば利用可能です。
- 就労移行支援事業所:一般企業への就労を目指す障害者に対して、就労に必要なスキルの習得や求職活動のサポートを行います。最長2年間利用でき、就職後も最長3年間の定着支援があります。
- 障害者就業・生活支援センター:就労と生活の両面から総合的な支援を行います。
これらの選択肢は「後退」ではなく、自分に合った働き方を見つけるための「新たな一歩」として捉えることができます。専門家のサポートを受けながら、自分のペースで進めていきましょう。
関連記事

統合失調症の人に向いている仕事とは?特性に合った職種と仕事を続けるためのポイントを解説
統合失調症の方の「長く続く仕事選び」にはコツがあります。マイペースに取り組める事務や軽作業などの適職例から、ストレスを溜めない職場環境の見極め方までを解説。一人で抱え込まず、医師や就労支援機関を味方につけて復職するための具体的なステップを紹介します。無理せず自分らしく働くためのヒントをまとめました。

就労継続支援A型とは?仕事内容・平均給料・利用条件を徹底解説
就労継続支援A型は、障害や難病のある方が雇用契約に基づいて働ける障害福祉サービスです。最低賃金が保障され、個々の障害特性に配慮した就労環境で、自分のペースで働きながらスキルを習得できます。

就労継続支援B型とは?仕事内容・工賃・選び方まで徹底解説
就労継続支援B型は、障害や難病のある方が自分のペースで働ける福祉サービスです。雇用契約を結ばずに働き、様々な作業を通じて就労経験を積むことができます。工賃や利用条件、選び方、利用手続きなど、就労継続支援B型について知っておきたい情報を詳しく解説した記事です。
まとめ:統合失調症があっても充実した職業生活は可能
統合失調症は、適切な治療と支援、そして自己管理があれば、充実した職業生活を送ることが十分に可能です。重要なのは、治療の継続、自己理解、段階的なアプローチ、そして専門機関の活用です。
休職から復職への道のりは平坦ではありませんが、自分のペースで進み、必要な配慮を受けながら取り組むことで、多くの方が職場復帰を果たしています。
統合失調症と診断されても、希望を持って前に進んでください。病気があっても、その人らしく働き、社会とつながり、人生を歩んでいける時代になっています。焦らず、一歩ずつ進んでいきましょう。