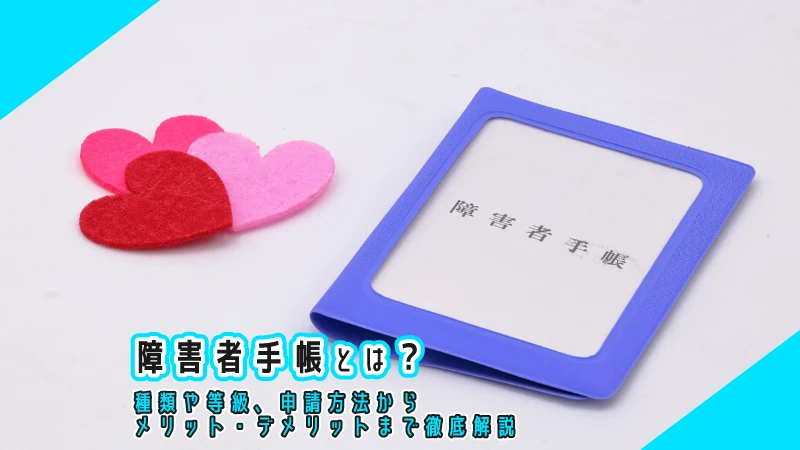公開日:2025.05.12
パーソナリティ障害の方に向いている仕事と長く働き続けるためのポイント
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- パーソナリティ障害の方に向いている仕事と長く働き続けるためのポイント

- このコラムのまとめ
- パーソナリティ障害の方が長く仕事を続ける鍵は、根性で苦手を克服することではなく、「自分の特性を知り、守ってくれる環境を選ぶこと」です。「性格の問題だから」と一人で抱え込まず、医療や支援機関を味方につけましょう。無理なく働くための具体的なステップと、相性の良い職場の見つけ方を解説します。
パーソナリティ障害の方に向いている仕事
パーソナリティ障害の方が仕事を選ぶ際には、自分の特性を理解し、それに合った環境を選ぶことが重要です。適切な仕事選びが長期的な就労継続への鍵となります。
人との関わりが少ない仕事
パーソナリティ障害の特徴のひとつに、対人関係の構築や維持が難しいことがあります。このため、人との直接的な関わりが比較的少ない環境は多くの方に向いています。
就労支援専門家
特に向いている職種としては、Webデザイナー、プログラマー、データ入力、在宅事務職などが挙げられます。これらは比較的独立して作業を進められ、報告や連絡もメールやチャットで済ませられることが多いためです。
マイペースに行うことができる仕事
パーソナリティ障害には感情の起伏が大きい、体調が不安定になりやすいといった特徴があります。そのため、自分のペースで業務を進められる仕事を選ぶことでストレスを軽減できます。
フレックスタイム制度のある職場やリモートワークが可能な仕事、納期さえ守れば作業時間を自分で調整できる仕事などが適しています。具体的には、ライター、データアナリスト、図書館の司書などが挙げられます。
自分の得意分野を活かせる仕事
パーソナリティ障害の方は一般的に仕事のストレスを感じやすい傾向がありますが、自分の興味や強みを活かせる仕事であれば、モチベーションを維持しやすく、ストレスも軽減されます。
特定の分野に強い関心や才能を持つ方も多いため、それを活かせる仕事を見つけることが重要です。細部への注意力が高い方は校正・校閲者や品質管理、創造的な思考が得意な方はクリエイティブ職、論理的思考が得意な方はプログラマーなどが向いています。
安定した環境で働ける仕事
特にC群(回避性、依存性、強迫性)の特性を持つ方は、環境の変化に不安を感じやすい傾向があります。そのため、業務内容や手順が明確で、突発的な変更が少なく、人間関係が比較的安定している職場が向いていることが多いです。
公共機関や大企業の事務職、図書館や病院などの公共サービス関連の仕事が例として挙げられます。
最終的には個人の特性や好み、経験によって向いている仕事は異なります。自分に合った仕事を見つけるためには、就労支援機関のサポートを受けながら、自己分析を行い、適性を見極めていくことが大切です。
パーソナリティ障害の方が長く働き続けるためのポイント
パーソナリティ障害の方が職場で長く働き続けるためには、自分の特性を理解した上で適切な対処法を身につけることが重要です。ここでは、職場での安定した就労を実現するための具体的なポイントを紹介します。
自分の特性を理解し受け入れる
長く働き続けるための第一歩は、自分自身のパーソナリティ障害の特性を正しく理解し、受け入れることです。自己理解があれば、困難な状況に直面したときの対処法も見えてきます。
産業医
自分の行動パターンや考え方のクセを振り返る習慣をつけ、困った場面でどのような感情が起きるかを記録しておくことが効果的です。
適切な治療・支援を継続する
パーソナリティ障害は放置すると症状が悪化する可能性があります。安定して働き続けるためには、適切な治療を継続することが重要です。定期的な通院と治療計画の遵守、症状の変化を記録し医師と共有することを心がけましょう。
特に注意したいのは、症状が安定してきたからといって自己判断で治療を中断しないことです。治療は長期間にわたることが多く、根気強く続けることが大切です。
職場での合理的配慮を求める方法
必要に応じて合理的配慮を求めることも検討しましょう。信頼できる上司や産業医に相談し、自分の特性と仕事への影響を具体的に説明して、必要な配慮を明確に伝えることが大切です。すべての情報を開示する必要はありませんが、仕事を円滑に進めるために必要な範囲で特性を伝えることで、適切なサポートを受けやすくなります。
ストレスを「ゼロ」にせず、「逃がす」技術を持つ
パーソナリティ障害の方は、対人関係のアンテナが非常に敏感です。そのため、周りの人は気にしていないような些細な空気の変化でも、脳が全力で反応してしまい、ただ座っているだけでも人一倍エネルギーを消耗してしまいます。
長く働くために必要なのは、鋼のメンタルを作ることではありません。「あ、今疲れているな」と早めに気づき、こまめにガス抜きをする「自分をメンテナンスする習慣」です。
- 睡眠による「強制終了」:嫌なことがあった日は、反省会をせずに早めに布団に入る。脳を物理的に休ませることが、感情の波を鎮める特効薬です。
- トイレでの「深呼吸」:イライラや不安が押し寄せたら、席を立ってトイレなどの個室へ。物理的に場所を変えて、浅くなった呼吸を整えるだけで脳がクールダウンします。
- 休日は「生産性」を捨てる:休みの日にまで「何かしなきゃ」と焦る必要はありません。好きな動画をダラダラ見る、美味しいものを食べるなど、自分を甘やかす時間をスケジュールに組み込みましょう。
ストレスを感じ始めたら早めに対処し、必要に応じて休息を取ることも大切です。自分のペースを守ることが長期的な就労継続につながります。
長く働き続けるためには、自分の特性を理解した上で適切な環境を選び、必要なサポートを受けながら自己管理を行うことが重要です。焦らず、自分のペースで働き続けられる環境を整えていきましょう。
周囲の人ができるサポート
パーソナリティ障害の方が職場で安定して働くためには、周囲の人の理解とサポートが不可欠です。適切な支援があれば、本人の強みを活かした働き方が可能になります。ここでは、家族や職場の同僚・上司ができるサポートについて解説します。
職場の上司・同僚による理解と配慮
パーソナリティ障害の方が職場で安心して働くためには、上司や同僚の理解と適切な配慮が大きな助けとなります。まずは障害の特性を正しく理解することが重要です。
産業医
職場での効果的なサポート方法としては、指示や期待を明確に伝える、定期的なフィードバックの機会を設ける、本人の特性を考慮した業務配分を行うなどが挙げられます。
コミュニケーションの工夫
パーソナリティ障害の方とのコミュニケーションでは、特有の困難が生じることがあります。効果的なコミュニケーションのためには、具体的かつ明確な言葉で伝える、一度に多くの情報を伝えすぎない、感情的にならず冷静に対応することが大切です。
特にデータや記録をもとに客観的に話し合うことで、感情的な対立を避け、建設的な対話が可能になります。
家族のサポート方法
家族は最も身近な支援者として重要な役割を担います。しかし、過度に関わりすぎると共依存の関係になることもあるため、適切な距離感を保つことが大切です。
家族ができる効果的なサポートとしては、治療の継続を支援する、本人の状態を観察し変化に気づいたら声をかける、家庭内での安定した生活リズムを整える、本人の自立を尊重し過保護にならないなどがあります。
精神科医
「冷たさ」ではなく「一貫性」のある距離を保つ
パーソナリティ障害の方と接する際、熱心な人ほど「親身になってあげたい」と距離を詰めすぎてしまいがちです。しかし、あまりに親密になりすぎると、相手の感情の波に巻き込まれ、共倒れになってしまうリスクがあります。
大切なのは、「仲良くなること」ではなく「安定した関係を続けること」です。
サポートする側も疲れを感じたら休息を取り、必要に応じて他の人と役割を交代するなど、持続可能な支援を心がけることが大切です。パーソナリティ障害の方が職場で長く活躍するためには、周囲の人の理解と適切なサポートが大きな助けとなります。
パーソナリティ障害の方が利用できる支援制度
パーソナリティ障害の方が働き続けるためには、様々な公的支援制度を活用することで経済的・社会的な助けを得ることができます。ここでは、利用可能な主な支援制度について解説します。
就労支援サービス
パーソナリティ障害の方が自分に合った仕事を見つけ、長く働き続けるためには、専門的な就労支援サービスの利用が効果的です。
ハローワークの専門窓口
全国のハローワークには、障害や疾患のある方の就労を支援する「専門援助部門」が設置されています。障害特性に配慮した職業相談・紹介、障害者向け求人情報の提供、職場適応のためのジョブコーチ支援などを受けることができます。障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書があれば支援を受けられる場合があります。
就労移行支援・定着支援
就労支援専門家
就労移行支援では原則2年間、職業訓練や就職活動サポートを受けられます。就職後は就労定着支援を利用して、最長3年間職場定着のための相談支援を受けることができます。利用には市区町村の障害福祉課で「障害福祉サービス受給者証」の発行を受ける必要があります。
関連記事
経済的支援
パーソナリティ障害により就労が困難な状況や、治療で休職が必要な場合など、経済的な支援を受けられる制度があります。
傷病手当金の活用
会社員や公務員など健康保険に加入している方が、パーソナリティ障害の治療のために仕事を休む必要がある場合、標準報酬日額の3分の2程度を最長1年6ヶ月受け取ることができます。申請には医師の診断書が必要です。
障害者手帳の取得について
症状の程度によっては精神障害者保健福祉手帳(精神手帳)を取得できる場合があります。税金の控除や減免、公共交通機関の運賃割引、障害者雇用枠での就職機会の拡大などのメリットがあります。手帳の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉課で行います。
医療費の負担軽減
パーソナリティ障害の治療を続けるためには、医療費の負担軽減も重要です。自立支援医療(精神通院医療)を利用すると通院医療費の自己負担が原則1割になります。高額療養費制度や医療費控除なども活用できます。
パーソナリティ障害の方が利用できる支援制度は多岐にわたります。自分の状況に合った制度を活用することで、治療を継続しながら安定した就労生活を送ることができます。制度の利用に迷ったら、主治医やソーシャルワーカー、市区町村の相談窓口に相談することをお勧めします。
パーソナリティ障害が仕事に与える影響

パーソナリティ障害の特性は、職場の人間関係や仕事の進め方にさまざまなかたちで影響を与えることがあります。ご本人だけでなく、まわりの人たちがその特徴を理解しておくことで、よりよい関係を築いたり、必要な配慮を行ったりしやすくなります。この項目では、パーソナリティ障害のタイプごとに、仕事への影響や注意したい点について紹介していきます。
A群が仕事に与える影響
A群(猜疑性・シゾイド・統合失調型など)に分類されるパーソナリティ障害を持つ方は、他人との距離感が独特だったり、周囲への関心が薄かったりすることがあります。また、警戒心が強く、職場の人たちと信頼関係を築くのに時間がかかる傾向も見られます。
そのため、チームで協力するような仕事では、誤解が生じやすかったり、コミュニケーションのズレが生まれやすかったりすることがあります。本人のペースを尊重しつつ、業務の割り振りやコミュニケーションの取り方を工夫することで、働きやすさが大きく変わってくるでしょう。
産業医
B群が仕事に与える影響
B群(境界性・自己愛性・演技性・反社会性など)のパーソナリティ障害を持つ方は、感情の振れ幅が大きかったり、人間関係が不安定になりがちだったりする特徴があります。特にストレスが強まると、感情をコントロールするのが難しくなる場面があり、思わぬトラブルに発展してしまうことも少なくありません。また、ちょっとした言葉に強く反応したり、批判を受けると激しい怒りを感じてしまうケースもあります。職場では、状況に応じたサポートや、過剰な刺激を避けるような環境づくりが必要になるかもしれません。
境界性パーソナリティ障害(BPD)の職場での困難
境界性パーソナリティ障害の方は、「見捨てられ不安」から過剰に仕事に打ち込み、疲弊してしまうことがあります。また、物事がうまくいかないと自己破壊的な行動に走ることもあるため、職場での支援が重要です。
C群が仕事に与える影響
C群のパーソナリティ障害(回避性・依存性・強迫性)は、不安や恐怖心の強さが特徴で、慎重さが過度になることで仕事に影響を与えることがあります。責任ある立場や目立つ役割を避けたがり、失敗への恐れから意思決定に時間がかかることがあります。完璧を求めるあまり、効率や生産性が低下する場合もあるでしょう。
全てのパーソナリティ障害に共通する影響
多くのパーソナリティ障害に共通するのが「二極思考」と呼ばれる思考パターンです。「完璧か失敗か」という極端な評価になりやすく、一部の失敗が全体の失敗と捉えられてしまうことがあります。
多くのパーソナリティ障害に共通して見られる傾向として、「感情のコントロールが難しい」「ストレスに影響を受けやすい」「生活リズムが乱れがち」といった点が挙げられます。こうしたことが重なると、出勤のリズムが安定しづらくなることもあります。
本人自身が自分の状態を客観的に把握し、無理のないスケジュールや職場環境を整えていくこと。そして周囲の理解とサポートを得ること。この2つが揃えば、仕事を長く続けることも十分に可能です。
パーソナリティ障害の方が避けた方がよい仕事環境
パーソナリティ障害の方が長く安定して働くためには、自分の特性に合った職場環境を選ぶことが重要です。一方で、特性によっては避けた方がよい仕事環境もあります。ここでは、パーソナリティ障害の方が避けた方がよい仕事環境や職種について解説します。
対人コミュニケーションが多い職場
パーソナリティ障害の多くは対人関係の構築や維持に困難を抱えています。特にA群(猜疑性・シゾイド・統合失調型)やC群(回避性・依存性・強迫性)の方にとって、対人コミュニケーションが中心となる職場は大きなストレス源となる可能性があります。
精神科医
特に避けた方がよい職種としては、接客業(飲食店、小売店など)、営業職(特にノルマが厳しいもの)、コールセンターなどが挙げられます。これらの職種は即時的な対人反応が求められるため、パーソナリティ障害の特性によっては大きな負担となります。
プレゼンテーションや説明が求められる仕事
人前で話したり、自分の考えを説明したりすることが多い職種は、特に回避性パーソナリティ障害や社交不安を伴うパーソナリティ障害の方にとって大きな負担となります。講師・教員など教育関連職、プレゼンテーションが頻繁に求められる企画職などは、緊張や評価への不安が強まり、症状の悪化を招く可能性があります。
「安心」が積み上がらない職場(異動・変化)
パーソナリティ障害の方、特に不安を感じやすいタイプ(C群など)の方にとって、最も重要な安定剤は「慣れ」です。
しかし、転勤や部署異動が頻繁にある職場では、やっと仕事を覚え、人間関係に慣れてきた頃に「リセットボタン」を押されてしまいます。数年おきにゼロから関係性を作り直すことは、想像以上にメンタルを削る作業です。
- 全国転勤がある総合職:物理的な住環境まで変わってしまい、拠り所がなくなるリスクがあります。
- 流動的なプロジェクト単位の仕事:「はじめまして」の挨拶を繰り返す環境は、対人緊張が強い方には過酷なマラソンになります。
隣の人が「敵」に見える職場(競争・成果主義)
「自分には価値がないのでは」という自己否定感や、他者からの評価に対する過敏さを持っている場合、競争の激しい職場は心が休まらない「戦場」になってしまいます。
常に数字で順位づけられたり、同僚と成果を競わせたりする環境では、「失敗=人格否定」のように受け取ってしまい、精神的に追い詰められやすくなります。
- グラフが貼り出される営業職:自分の成績が可視化されることで、常に「見られている」「責められている」という感覚に陥ります。
- インセンティブ重視の給与体系:安定した固定給ではなく、成果で給料が乱高下する環境は、生活の不安(予期不安)を増幅させます。
キャリアアドバイザー
パーソナリティ障害の基礎知識
パーソナリティ障害とは何か、どのような種類があるのか理解することは、適切な対処法を見つける第一歩となります。ここでは、基本的な知識について解説します。
パーソナリティ障害とは
パーソナリティ障害は、物事の考え方やとらえ方、感情表現、対人関係のパターンなどに長期的かつ柔軟性のない偏りがあり、それによって社会生活や仕事に支障をきたす精神疾患です。
精神科医
パーソナリティ障害の主な種類と特徴
アメリカ精神医学会の診断基準(DSM-5)では、パーソナリティ障害は3つのグループに分けられています。
A群(猜疑性・統合失調質・統合失調型)
A群は奇妙または風変わりな行動や考え方が特徴です。猜疑性パーソナリティ障害では他者への不信感が強く、シゾイドパーソナリティ障害では他者への関心が低く一人を好みます。統合失調型パーソナリティ障害は奇妙な考え方や行動が見られます。
B群(反社会性・境界性・演技性・自己愛性)
B群は感情的で移り気な様子が特徴です。境界性パーソナリティ障害では感情の波が激しく、見捨てられ不安が強いです。自己愛性パーソナリティ障害では自分は特別だと考え、批判に敏感です。
C群(回避性・依存性・強迫性)
C群は不安や恐れを強く抱いているのが特徴です。回避性パーソナリティ障害では拒絶への恐れから対人関係を避け、依存性パーソナリティ障害では自分で決断できず他者に依存します。強迫性パーソナリティ障害では完璧さへのこだわりが強いです。
パーソナリティ障害の原因:「犯人」がいるわけではない
「親の育て方が悪かったのか」「生まれつきの脳の病気なのか」。原因について悩むご本人やご家族は多いですが、現代の医学では、どちらか一方だけが原因とは考えられていません。
生まれ持った「繊細な気質(生物学的要因)」という種があり、そこに育ってきた「環境や体験(心理社会的要因)」という水や土が複雑に関わり合って、長い時間をかけて形成されていくものです。
パーソナリティ障害は適切な治療によって症状の改善が期待できます。主な治療としては認知行動療法などの精神療法が中心で、症状に応じて薬物療法も併用されます。年齢とともに症状が緩和されることも多いため、適切な支援を受けながら長期的な視点で取り組むことが大切です。
よくある質問
パーソナリティ障害と仕事に関して、多くの方が抱える疑問や不安について、よくある質問とその回答をまとめました。
パーソナリティ障害で障害者手帳は取得できますか?
パーソナリティ障害で精神障害者保健福祉手帳を取得することは可能です。ただし、診断名だけでなく、障害が日常生活や社会生活にどの程度影響しているかという点が重視されます。
精神保健福祉士
職場に「障害のこと」を伝えるべきですか?
診断名を伝える義務はありません。判断基準は「配慮が必要かどうか」です。
もし「通院で休みたい」「感情の波がある時に一人にしてほしい」といった具体的な配慮が必要なら、伝える(オープン就労)ほうが働きやすくなります。逆に、自分でコントロールできていて、配慮が不要なら、あえて伝えず(クローズ就労)偏見のリスクを避けるのも賢い戦略です。
治療を続ければ、性格は治りますか?
パーソナリティ障害の治療は、性格を矯正するものではなく、「極端な考え方のクセ」や「感情のブレーキのかけ方」を練習するものです。
また、この障害には「年齢とともに角が取れていく(マイルドになる)」という希望のある特徴があります。
治療は一般的に長期間を要しますが、焦らず治療を続ければ、波は少しずつ穏やかになっていきます。
仕事が続かないのは、病気のせいですか?
パーソナリティ障害の方は、対人関係の摩擦で消耗しやすいため、確かに離職率は高くなりがちです。しかし、それは「働けない」ということではありません。
「人と関わらない仕事に変える」「在宅ワークにする」など、自分の特性と喧嘩しない環境さえ見つかれば、驚くほど長く続いている方もたくさんいらっしゃいます。
休職中ですが、また働けるようになりますか?
復職は可能です。ただし「ただ休むだけ」では同じことを繰り返します。
復職の条件は、体力の回復だけではありません。「なぜ辛くなったのか」を分析し、「次はこうやって対処しよう」という新しい武器(対処スキル)や防具(環境調整)を手に入れてから戦場に戻ることが重要です。産業医と相談し、時短勤務などから少しずつ慣らしていきましょう。
まとめ:「普通」を目指さず、あなただけの「安定」を探しましょう
パーソナリティ障害の特性は、時にあなたを激しく揺さぶり、仕事や人間関係を難しくさせるかもしれません。しかし、それはあなたが「劣っている」からではなく、少しだけ「感じ方が強い」だけなのです。
精神科医
治療や支援を継続しながら、適切なストレス管理と自己ケアを心がけ、必要に応じて周囲のサポートを受けることで、自分らしい働き方を実現することができるでしょう。