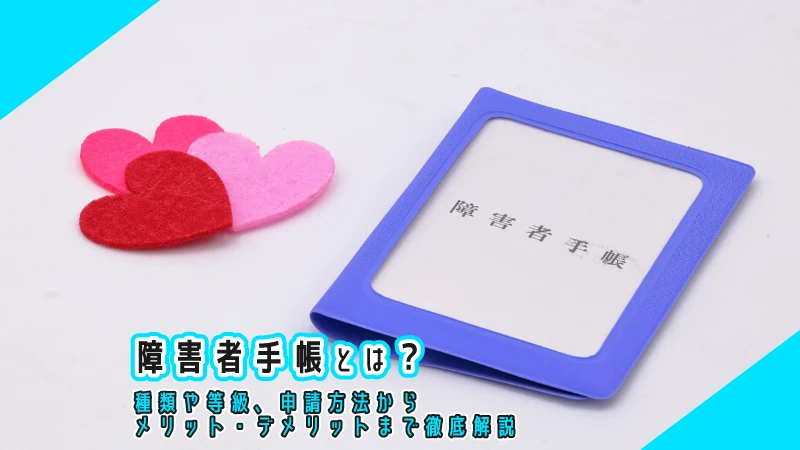公開日:2025.06.20
パーソナリティ障害の人に向いている仕事と働きやすい環境の作り方
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- パーソナリティ障害の人に向いている仕事と働きやすい環境の作り方

- このコラムのまとめ
- パーソナリティ障害がある方が安定して働くための情報をまとめた記事です。各障害タイプ別に向いている仕事の特徴や具体的な職業、長く働き続けるためのポイント、利用できる支援制度と相談先、職場での障害開示の考え方などを解説しています。自分の特性を理解し、適切な環境で無理なく働くための実践的なアドバイスが得られます。
もくじ
もっと見る
パーソナリティ障害の人に向いている仕事の特徴
パーソナリティ障害がある方が安定して働き続けるためには、自分の特性に合った仕事選びが重要です。適切な環境を選ぶことで、症状による影響を最小限に抑え、自分の能力を発揮することができます。ここでは、パーソナリティ障害の方に一般的に向いている仕事の特徴を紹介します。
人との関わりが少ない業務環境
パーソナリティ障害の多くのタイプに共通する特徴として、対人関係の構築や維持が難しいという点があります。そのため、人との関わりが比較的少ない仕事環境が向いている場合が多いです。
- 在宅ワーク可能な職種(Webデザイン、プログラミングなど)
- 報告・連絡・相談をメールやチャットで済ませられる職場
- 個人作業が中心の仕事(研究職、ライターなど)
ルーティン化された明確な作業内容
予測可能性が高く、毎日同じような流れで進められる仕事は、パーソナリティ障害の方にとって安心して取り組みやすい環境となります。特に、感情の起伏が大きい方や不安を感じやすい方には、明確な指示やマニュアルのある仕事が適しています。
- 工場でのライン作業
- データ入力や事務作業
- マニュアル完備の仕事
- 図書館業務などの整理・分類作業
マイペースで取り組める仕事
パーソナリティ障害の方は、感情の波や体調の変動が大きい場合があります。そのため、自分のペースで仕事を進められる環境が適していることが多いです。
- フレックスタイム制度のある職場
- リモートワークが可能な職種
- 納期までの進め方を自分で調整できる仕事
精神科医
自分の強みや特技を活かせる職種
パーソナリティ障害のある人は、仕事のストレスを抱えやすいといった特徴があります。あなたと相性のよい仕事を見つけるために「自分の得意分野は何か」を考えてみましょう。自分の得意分野を仕事に取り入れることができれば、ストレスの軽減につながります。
- 特定の分野に詳しい場合、その知識を活かせる専門職
- プログラマーやデザイナーなどのクリエイティブ職
- 集中力や緻密さを活かせる品質管理や校正校閲
パーソナリティ障害の種類や個人の特性によって向いている仕事は異なります。自分自身の強みと弱みを正確に把握し、無理なく続けられる仕事を選ぶことが大切です。
「こういうことができる」「これは苦手」と、自分のできることや不得意なことを把握し、それに合った職場環境を探していきましょう。
パーソナリティ障害のタイプ別:おすすめの具体的な職業
パーソナリティ障害には様々なタイプがあり、それぞれの特性によって向いている仕事も異なります。ここでは主なパーソナリティ障害のタイプ別に、特性を活かせる具体的な職業を紹介します。自分の特性を理解し、それに合った職業選択をすることで、より働きやすい環境を見つけることができるでしょう。
境界性パーソナリティ障害の方に向いている仕事
境界性パーソナリティ障害(BPD)の方は、感情の起伏が激しく、対人関係が不安定になりやすいという特徴があります。一方で、感受性が豊かで創造性に優れている面もあります。
- 芸術関連の仕事(イラストレーター、デザイナーなど)
- 個人で完結する創作活動(ライター、コンテンツクリエイターなど)
- 短期集中型の仕事(プロジェクト単位の業務など)
回避性パーソナリティ障害の方に向いている仕事
回避性パーソナリティ障害の方は、他者からの否定や批判を恐れる傾向があり、注意深く綿密な作業を得意とすることが多いです。
- データ入力オペレーター(個人作業が中心で、明確なルールに基づいた作業)
- プログラマー/ソフトウェア開発者(技術を活かして自己完結型の作業が多い)
- 図書館の司書(静かな環境で、限定的な対人関係)
- データアナリスト(データに集中でき、対人ストレスが少ない)
就労支援カウンセラー
自己愛性パーソナリティ障害の方に向いている仕事
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の方は、自分の能力や魅力に対する強い自信がある一方で、批判に敏感で承認欲求が強いという特徴があります。
- 独立したコンサルタント
- 起業家・経営者
- セールス・営業職(特に成果報酬型)
- クリエイティブディレクター
パーソナリティ障害全般で検討すべき働き方
パーソナリティ障害のタイプを問わず、柔軟な働き方を選択できることは大きなメリットとなります。特に近年は多様な働き方が可能になってきています。
- リモートワーク:対面でのコミュニケーションストレスを軽減
- フリーランス:自分のペースで仕事を選び、調整できる
- フレックスタイム制:体調や精神状態に合わせて勤務時間を調整できる
どの職業を選ぶ場合でも、自分の特性や症状の傾向を理解し、それに合った環境を選ぶことが大切です。必要に応じて、主治医や就労支援機関などに相談しながら、最適な仕事を探していくことをおすすめします。
パーソナリティ障害の人が長く働き続けるためのポイント
パーソナリティ障害がある方が長く働き続けるためには、適切な仕事選びだけでなく、日常的な対処法や環境調整も重要です。ここでは、職場でのストレスを軽減し、安定して働き続けるためのポイントを紹介します。
自己理解を深め、適切な環境を選ぶ
パーソナリティ障害と上手く付き合いながら働くためには、まず自分自身の特性を正確に理解することが大切です。自分の強みと弱み、ストレス要因を把握することで、適切な仕事環境を選べるようになります。
- 自分が苦手とする状況や環境を書き出してみる
- 集中して取り組める条件や環境を整理する
- 過去の職場経験から、うまくいった点・いかなかった点を分析する
産業医
治療・カウンセリングを継続する重要性
パーソナリティ障害は、放置しておくと症状が悪化したり、他の精神症状を引き起こしたりすることがあります。安定して働き続けるためには、継続的な治療やカウンセリングが欠かせません。
- 定期的な通院と治療の継続
- 心理療法などを通じた対処スキルの習得
- セルフケアと生活リズムの維持
ストレス管理と働き方の調整方法
パーソナリティ障害があると、職場のストレスがより強く感じられることがあります。ストレスをためないための工夫と、自分の状態に合わせた働き方の調整が重要です。
- 十分な睡眠と規則正しい生活リズムを保つ
- 可能であれば、フレックスタイム制やリモートワークを活用する
- 業務量が多すぎると感じたら早めに相談する
- 感情のコントロールが難しくなったら、一時的に場を離れる習慣をつける
職場での合理的配慮の求め方
パーソナリティ障害がある方が働きやすくなるためには、職場での合理的配慮が重要です。配慮を求める際には、以下のポイントを意識すると伝わりやすくなります。
- 具体的な困りごとと、それに対する具体的な解決案を提示する
- 自分の強みと、それをどう活かせるかも伝える
- 一度に多くを求めず、優先順位をつけて段階的に相談する
パーソナリティ障害があっても、自分の特性を理解し、適切な環境や支援を得ることで、長く安定して働き続けることは十分に可能です。症状の波があるときも、自分を責めすぎず、必要なサポートを求めながら、自分のペースで働き続けることが大切です。
パーソナリティ障害の人が利用できる支援制度と相談先
パーソナリティ障害がある方が安定して働き続けるためには、様々な支援制度や相談先を活用することが有効です。適切なサポートを受けることで、就労の可能性が広がり、職場定着率も高まります。ここでは、パーソナリティ障害のある方が利用できる主な支援制度と相談先を紹介します。
障害者雇用制度の活用について
パーソナリティ障害がある方は、症状の程度によって精神障害者保健福祉手帳を取得することができ、障害者雇用制度を利用することが可能です。障害者雇用制度は、障害のある方の就労機会を確保し、安定した職業生活を支援する仕組みです。
- 障害特性への理解と配慮がある環境で働ける
- 業務内容や勤務時間などの配慮を受けやすい
- 職場での支援体制が整っていることが多い
- 就労支援機関などが定着支援を行ってくれる
就労支援機関と利用方法
パーソナリティ障害がある方の就労をサポートする専門機関があります。自分に合った仕事探しから職場定着までをサポートしてくれます。
| 支援機関 | 主なサービス内容 |
|---|---|
| 就労移行支援事業所 | 一般企業への就労を目指す方向けの訓練・支援 就活サポートや職場定着支援 |
| 障害者就業・生活支援センター | 就業面と生活面の一体的な支援 職場定着のためのフォローアップ |
| ハローワーク(専門援助部門) | 障害者向け求人情報の提供 職業相談・紹介 |
32歳 女性
医療機関との連携の仕方
パーソナリティ障害の方が働き続けるためには、医療機関との適切な連携も重要です。治療を継続しながら、職場での状況も医師に伝えることで、より効果的な支援を受けることができます。
- 定期的な通院を継続し、体調や症状の変化を報告する
- 職場でのストレスや困りごとも伝える
- 自立支援医療制度を利用して経済的負担を軽減する
家族や周囲のサポートの重要性
パーソナリティ障害がある方が安定して働くためには、家族や周囲の人のサポートも重要な要素となります。適切なサポートにより、本人の負担が軽減され、仕事の継続につながります。
パーソナリティ障害があっても、適切な支援を受けながら自分に合った職場で働くことは十分に可能です。一人で抱え込まず、これらの支援制度や相談先を積極的に活用していきましょう。
パーソナリティ障害と職場での開示について

パーソナリティ障害がある方が働く際に、多くの方が悩むのが「職場に自分の障害を開示すべきか」という問題です。開示するかどうかには、メリットとデメリットの両面があり、個人の状況や職場環境によって最適な選択は異なります。ここでは、障害開示に関する考え方やポイントを紹介します。
職場に障害を開示するメリットとデメリット
パーソナリティ障害を職場に開示することには、様々なメリットとデメリットがあります。自分の状況に合わせて、慎重に検討することが大切です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・必要な配慮を受けやすくなる ・誤解を防ぎ、理解を得られる ・通院などの時間調整がしやすい |
・偏見や差別を受ける可能性がある ・能力を過小評価される恐れがある ・プライバシーが守られない可能性 |
34歳 女性
開示する場合のタイミングと伝え方
パーソナリティ障害を職場に開示する際には、タイミングや伝え方が重要です。適切な方法で伝えることで、理解を得やすくなります。
開示するタイミング
- 応募・面接時: 障害者雇用を希望する場合
- 採用決定後・入社時: 基本的な能力を評価された後に配慮事項を伝える
- 就労開始後: 実際に仕事をする中で必要性が生じた場合
効果的な伝え方のポイント
- 具体的な症状や特性を分かりやすく説明する
- 仕事にどのような影響があるかを具体的に伝える
- 必要な配慮事項を明確に伝える
- 自分の強みや工夫していることも一緒に伝える
非開示で働く場合の対処法
パーソナリティ障害を開示せずに働く選択をした場合でも、工夫次第で働きやすい環境を作ることは可能です。
- 自分の特性や症状を理解し、悪化のサインを把握しておく
- ストレスマネジメント技術を身につける
- 自分の強みを活かせる業務に積極的に取り組む
- 休憩時間を効果的に活用してリフレッシュする
どのように開示するかは、個人の状況、職場環境、症状の程度によって大きく異なります。一人で悩まず、主治医や就労支援の専門家に相談しながら、自分に合った方法を見つけていくことをお勧めします。
パーソナリティ障害の基本と仕事への影響
パーソナリティ障害は、思考、感情、行動の長期的なパターンに偏りがあり、社会的・職業的な機能に問題が生じる精神疾患です。この章では、パーソナリティ障害の基本的な知識と、仕事や職場環境にどのような影響を与えるのかについて解説します。
パーソナリティ障害とは何か
パーソナリティ障害は、青年期から成人早期の間に発症する精神疾患の一種で、頑固で柔軟性がなく、本人や周囲の人に苦痛をもたらす考え方や行動が長期にわたって続くという特徴があります。
- 硬直した思考パターンと行動様式
- 状況に応じた適切な対応が難しい
- 対人関係の構築や維持に困難を抱えることが多い
- 感情のコントロールが難しい場合がある
精神科医
パーソナリティ障害が仕事に与える一般的な影響
パーソナリティ障害があると、仕事面で様々な影響が生じることがあります。ただし、これらの影響は個人差が大きく、すべての人に当てはまるわけではありません。
対人関係への影響
- 同僚や上司とのコミュニケーションの困難
- チームワークや協力作業における困難
- 信頼関係の構築や維持が難しい
仕事のパフォーマンスへの影響
- 感情の波が大きく、安定した作業が難しい場合がある
- ストレス耐性が低下し、プレッシャーに弱くなることがある
- 自己評価の偏りにより、能力を発揮しきれないことがある
パーソナリティ障害の種類と特徴(A群・B群・C群)
パーソナリティ障害は、アメリカ精神医学会の診断基準(DSM-5)によれば、症状や特徴によってA群、B群、C群の3つのグループに分類されます。
- A群(風変わり・奇妙型):妄想性、統合失調質、統合失調型など。独特な思考や行動パターンを持つ。
- B群(演技的・感情的型):境界性、自己愛性、反社会性、演技性など。感情表現が激しく、不安定な行動が特徴。
- C群(不安・恐怖型):回避性、依存性、強迫性など。不安や恐怖が強く、内向的な傾向がある。
パーソナリティ障害は完治が難しい面もありますが、適切な治療や支援によって症状を軽減し、より適応的に生活することは十分に可能です。
自分の特性を理解し、それに合った環境や仕事を選ぶことが、安定した職業生活を送るための第一歩となります。
パーソナリティ障害のタイプ別:仕事への影響と特徴
各タイプのパーソナリティ障害は、仕事環境において異なる影響を与えます。ここでは、主なパーソナリティ障害のタイプごとに、職場でどのような特徴や課題が現れやすいか、またどのような対応が効果的かを解説します。
境界性パーソナリティ障害(BPD)と仕事
境界性パーソナリティ障害(BPD)は、感情の起伏が激しく、対人関係が不安定になりやすいという特徴があります。
職場での主な特徴と課題
- 感情の波による仕事の質の変動
- 見捨てられ不安に起因する確認行動の増加
- 白黒思考による極端な評価
- 衝動的な行動(突然の退職など)
効果的な対応と環境調整
- 明確で一貫した指示やフィードバック
- 感情が高ぶった時に一時的に離席できる柔軟さ
- 定期的な面談で不安を軽減する機会を設ける
回避性パーソナリティ障害と仕事
回避性パーソナリティ障害は、批判や否定を極度に恐れ、社会的状況を避ける傾向が特徴です。
職場での主な特徴と課題
- 新しい挑戦や責任ある役割の回避
- 意見表明や会議での発言の困難
- 評価や批評に対する過敏さ
臨床心理士
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)と仕事
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)は、自分の重要性に対する誇大感や共感性の欠如が特徴です。
職場での主な特徴と課題
- 批判や評価に過敏に反応する
- 他者は自分のために動くべきという考え
- 特別扱いを求める傾向
強迫性パーソナリティ障害と仕事
強迫性パーソナリティ障害は、完璧主義や柔軟性の欠如、細部へのこだわりが特徴です。
- 納期よりも完璧さを優先し、仕事が遅れる
- 変更や新しい方法への抵抗
- 過度の計画性と柔軟性の欠如
パーソナリティ障害の特性は個人差が大きく、また状況によっても表れ方が異なります。一人ひとりの特性を理解し、個別に適した対応を心がけることが重要です。
障害の特性だけでなく、その人の強みや能力にも目を向け、それを活かせる環境を整えることが、働きやすさにつながります。
よくある質問(FAQ)
パーソナリティ障害と仕事に関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。ここでは、よく寄せられる質問とその回答を紹介します。
パーソナリティ障害で障害者手帳は取得できますか?
パーソナリティ障害があっても、精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。ただし、診断名だけでなく、症状の重さや日常生活・社会生活への影響度によって判断されます。
- 申請には精神科医の診断書が必要です
- 症状が安定していない場合や、社会生活に顕著な支障がない場合は認められないこともあります
- パーソナリティ障害に加えて二次障害を併発している場合は、総合的に判断されます
治療をしながら働くコツはありますか?
パーソナリティ障害の治療を継続しながら安定して働くために、以下のようなコツがあります。
- 通院しやすい勤務体系や職場を選ぶ
- 自分の状態をこまめにチェックし、悪化のサインを見逃さない
- ストレス軽減法を日常的に実践する
- 職場での状況や困りごとを主治医に伝える
30代 女性
パーソナリティ障害は完治しますか?
パーソナリティ障害は、完全に「治る」というよりも、症状をコントロールし、より適応的な行動パターンを身につけていくという視点で考えるのが一般的です。
- 適切な治療や支援によって症状は改善することが可能です
- 年齢を重ねるにつれて、特に40代以降には症状が自然と緩和することもあります
- 個人の特性として受け入れながら、生活に支障がないよう対処法を身につけていくことが重要です
テレワークはパーソナリティ障害に向いていますか?
テレワークは、多くのパーソナリティ障害の方にとってメリットがある働き方ですが、タイプや個人によって向き不向きがあります。
- 対面でのコミュニケーションストレスが軽減される
- 自分のペースで仕事を進められる
- 感情コントロールが難しい時に一時的に離席しやすい
- ただし、孤独感や自己管理の難しさといった課題もある
まとめ:自分に合った仕事と環境で無理なく働くために
パーソナリティ障害があっても、自分の特性に合った仕事や環境を選び、適切なサポートを受けながら働くことで、充実した職業生活を送ることは十分に可能です。
自己理解を深め、自分の強みと弱みを把握すること、継続的な治療やサポートを受けること、そして無理をせず自分のペースを大切にすることが重要です。必要な配慮を求めることも恐れず、自分に合った働き方を模索していきましょう。
精神科医