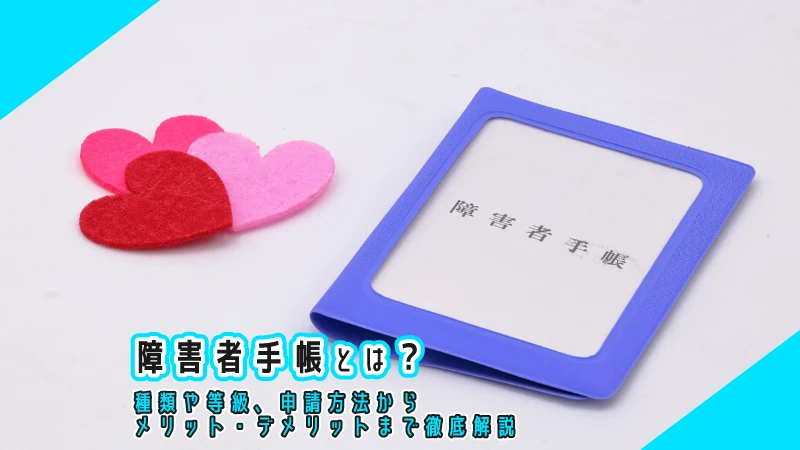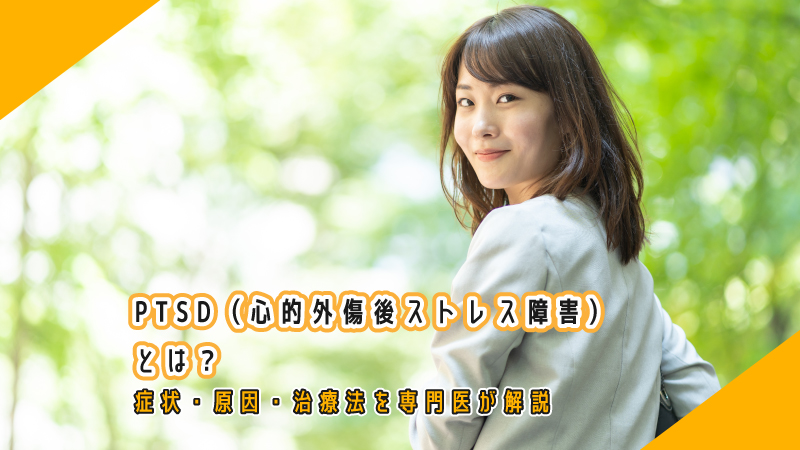公開日:2025.06.25
PTSDと診断された方の休職から復職までの流れ|支援制度や職場復帰のポイント
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- PTSDと診断された方の休職から復職までの流れ|支援制度や職場復帰のポイント

- このコラムのまとめ
- PTSDと診断された方が働き続けるための情報をまとめました。症状の特徴や仕事への影響、休職・復職の手順、受けられる支援制度について解説。回復のポイントや職場との関わり方、転職が必要な場合の選択肢まで、PTSDと上手く付き合いながら働くための具体的な方法を紹介しています。
もくじ
もっと見る
PTSDからの復職に向けた準備と手順
PTSDの症状が改善し、職場に戻る準備が整ってきたら、計画的に復職への道筋を立てていくことが大切です。復職は一つの大きな節目であり、十分な準備と適切な手順を踏むことで、スムーズな職場復帰が可能になります。
復職の条件と判断基準
復職するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。一般的な判断基準を把握しておきましょう。
- 医師から復職許可の診断が出ていること
- 本人が復職の意思と十分な体調の回復を自覚していること
- 企業が求める業務遂行能力の水準に達していること
PTSDの症状が改善し医師から復職許可の診断が出ても、最終的に復職の可否を判断するのは会社側になります。復職するには、どのような条件が揃うことが必要か、休職する前に確認しておきましょう。
産業医
主治医との相談と診断書
復職を考える際には、まず主治医との相談が必要不可欠です。医師と相談して復職の準備を進めていきましょう。
- 定期的な通院を継続し、復職の意思を医師に伝える
- 症状の改善状況を客観的に報告する
- 必要な配慮事項を相談し、診断書に記載してもらう
復職のタイミングについては、自身も「はたらきたい」という意欲が出るまで待つことが大切です。急いで復職すると再びPTSDの症状が出て、再度休職が必要になることもあります。
職場との復職前面談
主治医から復職の許可が出たら、職場の上司や人事部門との面談を設定し、復職に向けた調整を行います。
面談では次のような点を話し合うとよいでしょう。
- 現在の体調と回復状況
- 希望する復職のタイミングと働き方
- 必要な配慮や環境調整
もし回復に時間がかかった場合には、休職期間の延長を相談してみましょう。また「試し出勤制度(リハビリ出勤)」が認められる企業もあります。不安があれば、試し出勤ができないか会社に相談してみましょう。
段階的な復職計画の立て方
PTSDからの復職は、一気にフルタイム勤務に戻るよりも、段階的に業務量や勤務時間を増やしていく方法が効果的です。
| 期間 | 勤務時間 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 1~2週目 | 半日勤務 | 軽作業中心 |
| 3~4週目 | 6時間勤務 | 通常業務の70%程度 |
| 5週目以降 | 通常勤務 | 通常業務(調整あり) |
PTSDの原因となるストレスが休職前の職場や業務に関係している場合は、別な部署への異動や業務の変更を相談してみましょう。ただし新しい環境もストレスになり得るため、業務内容については会社とよく相談しましょう。
復職の成功には、自分の体調と相談しながら無理のないペースで進めることが重要です。症状の波があることを理解し、調子の良い日も悪い日も含めて上手に対処できるよう準備しておきましょう。
PTSDの方が受けられる支援制度
PTSDで休職や療養が必要になった場合、経済的な不安が大きな負担となることがあります。様々な公的支援制度を活用することで、治療に専念しながら生活を安定させることができます。
傷病手当金
「傷病手当金」は、会社員など健康保険に加入している方が病気のために働けなくなった際に受け取れる制度です。PTSDなどの精神疾患も対象となります。
- 業務外の傷病によって働けないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
- 休業期間中に給与の支払いがないこと
支給額は直近12ヶ月の平均給与の約3分の2で、最長1年6ヶ月まで受給できます。
社会保険労務士
出典:
障害年金
PTSDの症状が長期間続き、日常生活や就労に大きな支障がある状態が続く場合、「障害年金」の申請を検討することができます。
- 障害基礎年金:国民年金の加入者が対象
- 障害厚生年金:厚生年金の加入者が対象
PTSDだけでは受給が難しい場合もありますが、うつ病などを併発している場合には受給できる可能性が高まります。
出典:
就労移行支援サービス
「就労移行支援」は、一般企業への就職や復職を目指す方を支援するサービスです。以下のようなサポートを受けられます。
- 職業能力の評価
- 職場でのコミュニケーションスキルのトレーニング
- ストレス管理や症状対処法の習得
- 就職活動のサポート
原則として障害者手帳を持っている方が対象ですが、自立支援医療の対象となっている場合も利用できることがあります。
精神障害者保健福祉手帳の活用
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳です。取得すると以下のメリットがあります。
- 税金の減免(所得税、住民税など)
- 公共交通機関の運賃割引
- 障害者雇用枠での就労機会
PTSDと診断された方は、これらの支援制度をうまく活用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に専念し、社会復帰を目指すことができます。どの制度が自分に合っているかは症状の程度や生活状況によって異なりますので、主治医や専門家に相談しながら検討することをお勧めします。
PTSDと診断された場合の働き方の選択肢

PTSDと診断されると、「このまま仕事を続けられるだろうか」「休職した方がいいのか」など、働き方について悩むことが多いでしょう。症状の程度や原因、職場環境によって、最適な選択は人それぞれ異なります。
現職で継続して働く場合のポイント
PTSDの症状が比較的軽度で、職場環境がトラウマと直接関連していない場合は、適切な配慮を受けながら現職を続けることも可能です。
業務調整を申し出る
PTSDの症状により仕事の効率が落ちていると感じる場合は、上司や人事部に相談し、業務量や内容の調整を検討しましょう。
- 残業や休日出勤を減らす
- 一時的に業務量を減らしてもらう
- 短時間勤務や時差出勤を検討する
職場環境の改善を相談する
PTSDの症状を悪化させる要因が職場環境にある場合は、環境の調整を依頼することも検討しましょう。
精神科医
ストレス対処法を身につける
日常的なストレスを管理するためのスキルを身につけることで、症状の悪化を防ぎながら働き続けることができます。
- 呼吸法や筋弛緩法などのリラクゼーション技術を習得する
- 十分な睡眠と栄養バランスの良い食事を心がける
- 適度な運動を取り入れる
休職を選択する場合
PTSDの症状が強く、仕事を続けるのが難しい場合は、休職を検討することも重要な選択肢です。
休職制度とは
休職とは、雇用契約は維持したまま、一定期間会社を休む制度です。休職は各企業が独自に定めている制度であり、期間や条件は会社ごとに異なります。
休職中は基本的に給与は支給されませんが、傷病手当金などの制度を利用できる場合があります。まずは自分が勤める会社の休職制度について確認しましょう。
PTSDの診断を受けた場合、自分の症状と職場環境を考慮し、継続して働くか休職するかを慎重に判断することが大切です。どちらの選択が適切かは、医師や家族、職場の理解者と相談しながら決めていきましょう。
PTSDとは?症状と仕事への影響
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、強いショックや恐怖を伴う出来事を体験したことで発症する精神疾患です。適切な治療と周囲の理解があれば、症状の改善が期待できます。
PTSDの主な症状
PTSDの症状は大きく分けて以下の3つのタイプに分類されます。
侵入症状
トラウマとなった記憶が突然蘇り、強い苦痛を伴います。これらの症状は本人の意思とは関係なく発生します。
- トラウマ場面が繰り返し頭に浮かぶ
- 悪夢にうなされる
- フラッシュバック(過去の体験が現実のように感じられる)
回避症状
トラウマを思い出す状況や会話を避け、感情が麻痺することがあります。
臨床心理士
過覚醒症状
常に警戒状態にあり、以下のような症状が見られます。
- 睡眠障害(寝つきが悪い、中途覚醒)
- 集中力の低下や注意力の散漫
- 些細なことでも過剰に驚く
- イライラや怒りっぽさ
PTSDが仕事に与える影響
| 症状 | 仕事への主な影響 |
|---|---|
| 侵入症状 | ・業務の中断 ・集中力の低下 ・ミスの増加 |
| 回避症状 | ・特定の業務や場所の回避 ・対人関係の構築困難 |
| 過覚醒症状 | ・疲労の蓄積 ・感情コントロールの困難 |
これらの影響は個人によって異なりますが、適切な治療やサポート、職場の理解と配慮があれば、多くの場合は仕事を続けることができます。症状が重い場合は、一時的な休職や業務調整などを検討することも大切です。
PTSDで休職中の過ごし方と回復のポイント
PTSDの症状により休職することになった場合、その期間をどのように過ごすかが回復の鍵となります。計画的に回復に向けた取り組みを行うことが大切です。
ストレスの少ない環境を整える
休職直後は、まず心身をしっかり休め、ストレスの少ない環境で過ごすことが最優先です。
- 自分を責めないこと(休職することに罪悪感を持たない)
- PTSDの症状を引き起こす可能性のある刺激を避ける
- リラックスできる空間を自宅に作る
心理カウンセラー
休職中は時間に余裕があることから、飲酒や喫煙の増加など生活習慣の悪化に気をつけましょう。またカフェインは不安を強めることがあるので注意が必要です。
専門的な治療を受ける
休職中は、PTSDの症状を改善するための専門的な治療を継続して受けることが重要です。
- 認知行動療法(CBT)
- 眼球運動脱感作再処理法(EMDR)
- 持続エクスポージャー療法
- 薬物療法
リワークプログラムの活用
症状が改善してきたら、リワークプログラムを活用して復職に向けた準備を始めましょう。
- 通勤リズムの再構築
- 集中力や持続力のトレーニング
- ストレス対処法の習得
職場との適切なコミュニケーション
休職中であっても、職場との適切なコミュニケーションを維持することが重要です。最低でも月に1回は現在の状態について、会社の人事部や上司に連絡をしましょう。
症状が改善して、主治医から復職可能と診断されたら、復職の時期について会社と相談しましょう。自分の状態や復職に向けての希望を具体的に伝えることで、スムーズな復職につながります。
復職が難しい場合の転職・再就職のポイント
PTSDの治療を続けていても、元の職場への復帰が難しいと感じる場合があります。特にトラウマの原因が職場環境に関連している場合は、転職や再就職を検討することも選択肢の一つです。
自分に合った職場環境を見極める
転職先でもPTSDの症状の原因に関係するストレスがある場合は、症状が再発する可能性があります。症状の悪化や再発を防ぐため、転職活動を始める前に自分にとって何がストレスとなるかを把握しましょう。
- トラウマとなった状況とは異なる職場を選ぶ
- 自分のストレス耐性に合った仕事量や責任の範囲を考慮する
- 柔軟な勤務体制がある企業を検討する
キャリアカウンセラー
障害者雇用枠の活用
PTSDだけでは精神障害者保健福祉手帳の取得が難しい場合もありますが、うつ病や不安障害などを併発している場合には手帳を取得できる可能性があります。手帳があれば障害者雇用枠での就職という選択肢が広がります。
就労支援サービスの利用
様々な就労支援サービスを利用することで、効果的に転職活動を進めることができます。
- ハローワークの専門援助窓口(障害者窓口)
- 障害者就業・生活支援センター
- 障害者向け転職エージェント
面接時の自己開示の考え方
面接でどこまで自分の状態を開示するべきか、自己開示の程度は個人の状況や希望する働き方によって異なります。
- オープン就労:障害や病気があることを企業に伝える方法
- クローズ就労:障害や病気があることを伝えない方法
- セミオープン就労:障害名は伝えずに必要な配慮のみを伝える方法
PTSDを抱えての転職は不安も多いですが、適切な支援を受けながら自分に合った職場を見つけることで、充実した職業生活を送ることができます。
関連記事

オープン就労とは?メリット・デメリットと適性がある人の特徴
オープン就労は障害を開示して働く形態で、特性に合わせた配慮を受けながら働くことができます。障害者雇用枠での応募が一般的で、精神的負担の軽減や職場定着率の向上等のメリットがあります。デメリットとしては給与水準が低めで、職種選択肢が限られることが挙げられます。自分の障害特性や希望する働き方に合わせて選択することが重要です。

クローズ就労の徹底ガイド:メリット・デメリットと成功するためのポイント
クローズ就労は、自分の障害を企業に開示せず、一般雇用枠で働く方法です。これにより給与水準が高く、職種の選択肢が広がる反面、障害への配慮が受けられない、体調管理が難しくなるなどのデメリットもあります。成功するためには、適切な就職先選びや自己管理が重要です。自分の特性に合った働き方を選ぶことが長期的な活躍につながります。
まとめ:PTSDと上手く付き合いながら働くために
PTSDは適切な治療と支援、周囲の理解があれば、症状を管理しながら職業生活を送ることができます。大切なのは、自分の状態を正しく理解し、無理をせず、必要な時には休息を取ること。そして医師のサポートを受けながら、自分に合った働き方を見つけていくことです。
精神科医
焦らず、一歩一歩、自分のペースで回復と社会参加を目指していくことが、PTSDと上手く付き合いながら働くための鍵となります。