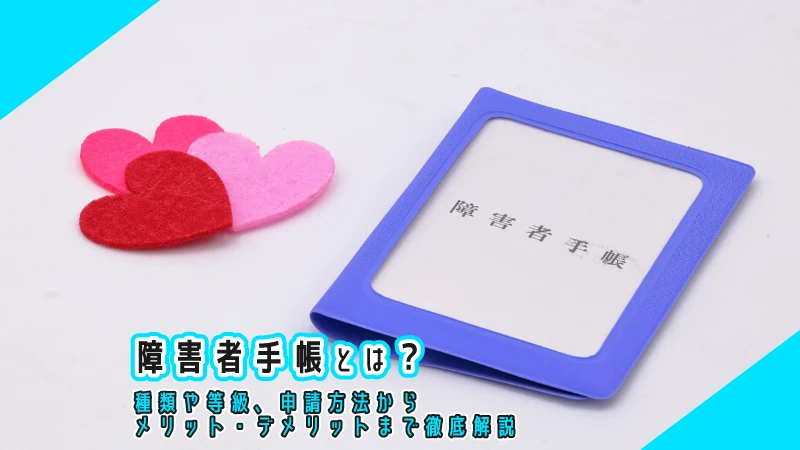公開日:2025.07.04
てんかんとは?症状・原因・治療法から生活・就労支援まで徹底解説
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- てんかんとは?症状・原因・治療法から生活・就労支援まで徹底解説

- このコラムのまとめ
- てんかんは脳の神経細胞の過剰興奮によって発作が繰り返す慢性疾患です。本記事では、てんかんの基礎知識から症状・発作の種類、誘因と予防法、診断・治療方法、日常生活の管理、就労支援制度まで徹底解説。適切な治療と自己管理により、てんかんがあっても充実した生活を送るためのポイントを紹介しています。
もくじ
もっと見る
てんかんの基礎知識
てんかんは、脳の神経細胞(ニューロン)が過剰に興奮することで発作を繰り返す慢性的な脳の疾患です。日本国内には約60万~100万人の患者がいると推定され、1,000人に5~8人の割合でてんかんを患っているとされています。
出典:
てんかんの定義と特徴
世界保健機関(WHO)では、てんかんは「脳の慢性疾患であり、脳の神経細胞に突然発生する激しい電気的興奮により、繰り返し起きる発作に伴い、さまざまな臨床症状が現れる病気」と定義されています。特徴としては、脳に慢性的な異常があること、神経細胞が過剰に興奮すること、そしててんかん発作が繰り返し起こることが挙げられます。
てんかんは特定の人だけがかかる特別な病気ではなく、誰もが発症する可能性がある疾患です。小児や高齢者に発症率が高いものの、30~40代での発症も珍しくありません。
神経内科医
脳内での異常放電のメカニズム
脳内には数百億の神経細胞があり、それらが電気信号を介して情報をやり取りしています。通常は必要な部分の神経細胞が適切に電気信号を伝えていますが、何らかの原因で一部の神経細胞に不必要な電気信号(異常放電)が発生し、過剰な興奮が起こると「てんかん発作」となります。
発作中には大脳の機能がうまく発揮されなくなるため、意識障害や運動障害、感覚障害などさまざまな症状が現れます。発作の表れ方は、異常放電が起きる脳の部位によって異なります。
てんかんの発症原因と遺伝性について
てんかんの発症原因は主に2つのタイプに分けられます。脳に病変があってそこから発作が起きる「症候性てんかん」と、明らかな病変はないが脳が興奮しやすい体質による「特発性てんかん」です。症候性てんかんの原因としては、脳梗塞、頭部外傷、脳血管障害、脳腫瘍などが挙げられます。
てんかんの遺伝性については、一般的に遺伝性は薄いとされています。家族性のてんかんはてんかん全体の1%未満で、多くは環境要因や後天的な要因が関係しています。
てんかんの症状の重さは個人差が大きく、小児期に発作を起こしていても成人になれば完治する良性のてんかんもあれば、頻繁に発作を繰り返す難治のてんかんもあります。しかし、全体の6~7割の患者は適切な抗てんかん薬の服用によって発作が止まるため、多くの人は通常の社会生活を送ることが可能です。
てんかんのある方が利用できる支援制度
てんかんのある方が安定した生活や就労を送るためには、さまざまな公的支援制度を活用することが有効です。症状や状況に応じて利用できる主な制度を紹介します。
医療費助成(自立支援医療制度)
てんかんの治療費は自立支援医療制度(精神通院医療)の対象となります。この制度を利用することで、通常3割の医療費負担が原則1割に軽減されます。対象は通院している方(発作がなくても予防のために通院・服薬している方も含む)で、診察料、検査費用、薬代が軽減の対象となります。申請はお住まいの市区町村の障害福祉窓口で行います。
障害者手帳の取得と福祉サービス
てんかんの症状の程度によっては、精神障害者保健福祉手帳の取得が可能です。手帳があると、税金の控除や公共料金の割引、障害者雇用枠での就職など様々な福祉サービスを受けることができます。てんかんに加えて知的障害を伴う場合は療育手帳、身体に障害が生じている場合は身体障害者手帳の取得も検討できます。
障害年金と経済的支援
てんかん発作によって生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金(国民年金加入者向け)と障害厚生年金(厚生年金加入者向け)があり、症状の程度や加入期間によって支給額が決まります。
就労支援サービス
就労移行支援事業所では、一般企業への就職を目指す方に、最長2年間、職業能力評価や訓練、就職活動支援などを受けることができます。また、障害者就業・生活支援センターでは、就労面と生活面の両方からサポートを受けられます。これらの機関では、てんかんの特性に配慮した就労支援を行っており、症状に合った仕事探しから企業との調整、就職後のフォローまでを一貫して支援してくれます。
就労支援員
これらの支援制度を上手に活用することで、てんかんのある方も安心して社会生活を送ることができます。症状や状況に応じて、どの制度が自分に合っているかを福祉窓口や医療機関に相談してみましょう。
てんかんのある方の就労成功事例と雇用のポイント

てんかんがあっても、適切な配慮と環境調整によって多くの方が活躍されています。ここでは実際の成功事例と、雇用側が知っておくべきポイントについて紹介します。
職場での合理的配慮の例
てんかんのある方が働く際に効果的な配慮は、発作の種類や頻度、個人の特性によって異なります。勤務時間の調整(フレックスタイム制、時差出勤など)、業務内容の調整(長時間のPC作業を避ける、定期的な休憩など)、職場環境の調整(点滅光の少ない照明、休憩スペースの確保など)が有効です。これらの配慮は特別なものではなく、多くの職場ですでに実施されている働き方改革の一環と考えることもできます。
就労成功事例
本人の声
雇用主向け:てんかんのある方の雇用ポイント
てんかんのある方を雇用する際は、正しい知識と理解を持つことが重要です。てんかんは脳の一時的な電気的異常であり、適切な治療と環境調整で多くの場合コントロール可能です。「発作=危険」という先入観だけで判断せず、個人の状態を正確に把握しましょう。また、本人の同意のもと、適切な範囲で情報を共有し、発作時の対応方法を周知しておくことも大切です。
安定した就労継続のためのコツ
てんかんのある方が長く安定して働き続けるためには、健康管理の徹底(規則正しい生活リズム、十分な睡眠、正しい服薬管理)、体調変化の早期報告、職場環境の定期的な見直し、支援ネットワークの活用が重要です。本人と職場の双方が一定の工夫を続けることで、長期的な就労成功につながります。
適切な治療と自己管理、そして職場の理解と配慮があれば、てんかんのある方も十分に能力を発揮し、やりがいを持って長く働き続けることができます。
それぞれの特性を活かした働き方を実現することが、本人にとっても企業にとっても価値あるものとなるでしょう。
てんかんと就労・社会生活
てんかんがあっても、適切な治療と自己管理によって、多くの方が充実した社会生活を送ることができます。ここでは、就労や社会生活におけるいくつかの重要な側面を紹介します。
運転免許と移動手段について
てんかんのある方の運転免許取得や更新については、道路交通法で一定の基準が設けられています。発作が2年以上ないこと、医師が「運転に支障がない」と判断していること、服薬などの治療を適切に継続していることが重要です。
てんかん発作の種類や頻度によっては、条件付きで運転免許を取得できる場合もあります。運転が難しい場合は、公共交通機関の利用や福祉タクシーなどの代替手段を検討しましょう。
就労時の配慮と職場での伝え方
てんかんについて職場に伝えるかどうかは、症状の程度や頻度によって判断が分かれます。発作の頻度が高い場合や業務中に配慮が必要な場合は開示を検討し、発作が完全にコントロールされている場合は非開示も選択肢となります。伝える際は、簡潔で正確な情報、発作時の具体的な対応方法、必要な配慮を明確に伝えることがポイントです。
会社員(30代・女性)
妊娠・出産・育児とてんかん
てんかんのある女性が妊娠・出産を考える場合、事前の準備と適切な医療サポートが重要です。妊娠前から主治医と相談し、抗てんかん薬の調整や葉酸の摂取など必要な対策を行いましょう。
多くの方が安全に妊娠・出産を経験できますが、ホルモンバランスの変化で発作頻度が変わることもあるため、定期的な診察が大切です。育児中はパートナーや家族との分担、必要に応じた外部サポートの活用を検討しましょう。
学校生活での対応
学齢期のてんかんのあるお子さんや学生にとって、学校側の適切な理解と対応は重要です。発作の種類や頻度、対応方法などの情報を学校に伝え、必要に応じて個別の教育支援計画を作成してもらうことも検討しましょう。年齢が上がるにつれて、本人が自分の状態を管理し、必要に応じて周囲に伝える力を身につけていくことも大切です。
てんかんのある方の日常生活の管理
てんかんの症状をコントロールし、安定した生活を送るためには、日常生活での自己管理が非常に重要です。適切な生活習慣と発作への備えによって、てんかんがあっても充実した毎日を過ごすことができます。
規則正しい生活習慣の重要性
てんかん発作を予防するためには、規則正しい生活リズムが基本となります。睡眠不足は発作の最も一般的な誘因のため、毎日同じ時間に就寝・起床し、成人は6~8時間、子どもは8~10時間の睡眠を確保しましょう。また、バランスの良い食事を規則正しい時間に摂り、過度な空腹状態やカフェイン・アルコールの過剰摂取を避けることも大切です。適度な運動はストレス軽減や睡眠の質向上に役立ちますが、過度な疲労は発作のリスクを高めるため、自分に合った強度と時間で行いましょう。
服薬管理のポイント
抗てんかん薬の適切な服用は発作予防の最も重要な要素です。毎日決まった時間に薬を飲むために、ピルケースの活用やスマートフォンのアラーム機能の利用、日常の習慣と一緒に服薬する習慣づけなどの工夫をしましょう。服薬を忘れた場合は、気づいた時点ですぐに1回分を服用し、次の服用時間が近い場合は1~2時間遅らせて服用するようにします。
救急医療専門家
発作時の対処法と安全対策
発作が起きた際の適切な対応について、本人も周囲の人も理解しておくことが重要です。全身けいれん発作の場合は、周囲の危険物を取り除き、頭の下に柔らかいものを敷き、衣類の締め付けをゆるめ、無理に動きを抑えようとせず横向きに寝かせるなどの対応が必要です。発作が5分以上続く場合や連続して起きる場合は救急車を呼びましょう。
入浴中の発作は溺水の危険があるため特に注意が必要です。できるだけ一人での入浴を避け、浴槽の水は浅めにする、シャワーのみの入浴も検討するなどの対策を取りましょう。
外出時は医療情報カードの携帯や、可能であれば信頼できる人と一緒に行動するなどの安全対策を心がけることも大切です。
てんかん発作の種類と症状
てんかん発作は、脳内での異常放電がどの領域で起こり、どのように広がるかによって様々な症状を示します。発作のパターンを正確に把握することは、適切な治療法の選択や日常生活での対策に重要です。
全般起始発作(全身に及ぶ発作)
全般起始発作は、脳の両半球が同時に異常放電に巻き込まれて起こる発作です。最初から脳全体に異常放電が広がるため、意識障害を伴うことが多く、両側性の症状が現れます。
- 強直間代発作:突然の意識消失から始まり、全身の筋肉が硬直する「強直期」の後、全身がリズミカルに震える「間代期」が続く、てんかんの中で最も知られている発作
- 欠神発作:数秒~30秒程度意識がなくなり、動作が停止してぼんやりとした表情になる、主に小児期に見られる発作
- ミオクロニー発作:意識がある状態で身体の一部がピクッと動く短時間の発作
- 脱力発作:突然全身の力が抜けて転倒する発作
神経内科医
焦点起始発作(部分発作)
焦点起始発作は、脳の特定の領域(焦点)から異常放電が始まる発作です。症状は異常放電が起きている脳の部位によって異なります。
- 焦点意識保持発作:意識が保たれたまま、手足のけいれん、特定の感覚(しびれ、幻覚など)、自律神経症状(動悸、発汗など)が現れる発作
- 焦点意識減損発作:意識が低下または消失し、口をもぐもぐ動かす、衣服をいじるなどの自動症を伴うことがある発作
- 二次性全般化発作:焦点発作から始まり、その後脳全体に異常放電が広がって全般発作へ移行する発作
てんかんと間違えやすい疾患
てんかんに似た症状を示す主な疾患には、心理的要因による心因性非てんかん発作、脳血流の一時的低下による失神、片頭痛、一過性脳虚血発作などがあります。正確な診断のためには専門医による評価が重要です。
てんかん発作の誘因と予防
てんかん発作は、特定の状況や環境要因によって誘発されることがあります。これらの誘因(トリガー)を理解し、適切に対処することで、発作の頻度を減らし、より安定した生活を送ることが可能になります。
睡眠不足・疲労・ストレス
睡眠不足や過度の疲労、ストレスは、てんかん発作の最も一般的な誘因の一つです。睡眠は脳の回復に重要な役割を果たすため、不足すると脳の興奮性が高まり発作の閾値が下がります。特に若年性ミオクロニーてんかんなどでは、睡眠-覚醒リズムの変化が発作を誘発しやすくなります。また、身体的・精神的疲労やストレスもホルモンバランスの変化を通じて脳の興奮性を高めます。
てんかん専門医
光刺激・音・温度変化
外部からの感覚刺激がてんかん発作を誘発することもあります。特に光過敏性てんかん(全てのてんかんの約5%)では、テレビやコンピュータ画面のちらつき、ストロボライト、点滅する光などが発作を引き起こすことがあります。また、特定の音や急激な温度変化、高熱なども一部の方では発作の誘因となります。
月経や体調変化
女性のてんかん患者の中には、月経周期に関連して発作頻度が変化する「カタメニアルてんかん」を経験する方がいます。エストロゲンには脳を興奮させる作用があり、プロゲステロンには鎮静作用があるため、これらのホルモンバランスの変動が発作頻度に影響します。月経以外にも、発熱、低血糖、脱水、電解質バランスの乱れなどの体調変化も発作を誘発することがあります。
発作を予防するための日常生活の注意点
てんかん発作の予防には、誘因を避けるための生活習慣の調整が重要です。
規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス管理、そして何よりも抗てんかん薬の確実な服用が基本となります。アルコールや刺激物の過剰摂取は避け、発作の記録をつけて自分の発作パターンや誘因を特定することも大切です。
てんかんの診断と治療法
てんかんの適切な診断と治療は、安定した日常生活を送るために非常に重要です。症状の正確な把握から始まり、様々な検査を経て診断が確定し、個々の状態に合わせた治療計画が立てられます。
診断に必要な検査と流れ
てんかんの診断は、詳細な問診から始まります。発作の様子や状況、頻度、家族歴などの情報が重要です。本人が発作中の状態を覚えていないことも多いため、周囲の人からの情報も貴重です。発作時の様子を動画で記録しておくと診断の助けになります。
脳波検査(EEG)はてんかんの診断において最も基本的な検査です。通常脳波検査、睡眠脳波検査、長時間ビデオ脳波モニタリングなどがあります。また、脳の構造を調べるMRIやCT、機能を評価するPETやSPECTなどの画像検査も重要です。
神経内科医
薬物療法(抗てんかん薬)
てんかん治療の基本は薬物療法です。抗てんかん薬はてんかんのタイプや患者の特性に合わせて選択されます。通常は1種類の薬剤(単剤療法)から開始し、効果不十分な場合は別の薬剤への切り替えや併用を検討します。約60~70%の患者さんは、適切な薬物療法で発作がコントロールできるようになります。
出典:
外科治療の適応と方法
薬物療法で効果が不十分な「難治性てんかん」の場合、外科治療が検討されます。特に発作の起始部位が特定できる焦点性てんかんでは、てんかん焦点の切除や離断術、脳刺激療法などの選択肢があります。側頭葉てんかんの焦点切除術では、60~80%の患者で発作が消失または著明に減少するという成績が報告されています。
その他の治療法(食事療法など)
高脂肪・低炭水化物の「ケトン食療法」は、主に薬剤抵抗性の小児てんかんに効果が期待できます。また、迷走神経刺激療法などの神経調節療法や、特定の状況でのホルモン療法なども補助的治療として検討されることがあります。
まとめ:てんかんとともに充実した生活を送るために
てんかんは、適切な理解と治療、そして自己管理によって、多くの方が充実した生活を送ることができる疾患です。自分のてんかんのタイプや発作のパターンを正確に把握し、医療専門家とのパートナーシップを築くことが重要です。
てんかんとともに20年を過ごしてきた50代男性
規則正しい生活習慣の維持、適切な服薬管理、周囲の理解と支援を得ながら、てんかんは多くの場合コントロール可能です。自分の可能性を広げ、てんかんがあっても自分らしい人生を歩んでいきましょう。