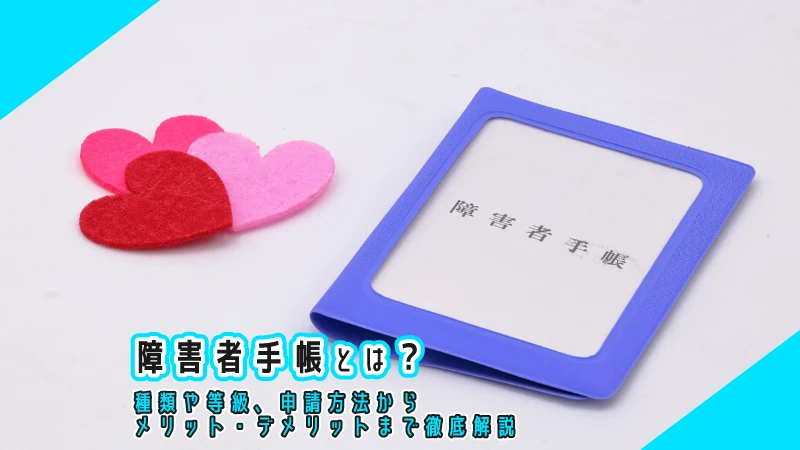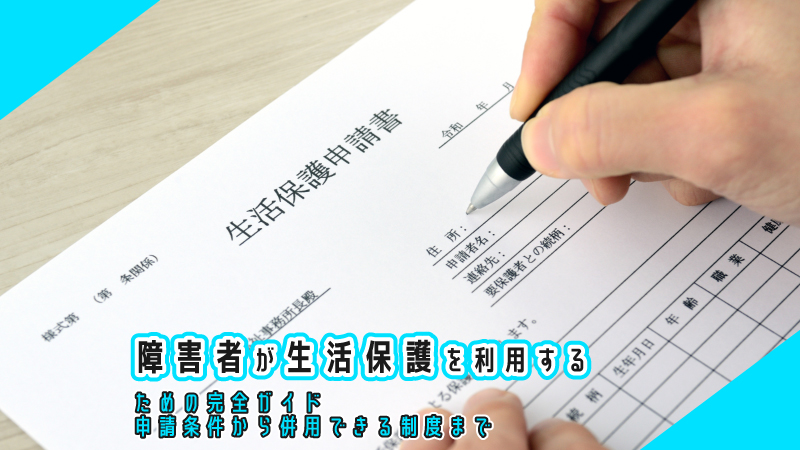公開日:2025.10.20
慢性疲労症候群と共に生きる:利用できる制度と支援サービスの完全ガイド
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- 慢性疲労症候群と共に生きる:利用できる制度と支援サービスの完全ガイド

- このコラムのまとめ
- 慢性疲労症候群(CFS)の基本知識と公的支援制度、就労支援、仕事との両立方法、治療法とセルフケアについて解説。難病であるCFSと診断された方が利用できる障害年金や傷病手当金などの制度や相談窓口、症状と付き合いながら働くためのポイントを紹介し、生活の質を向上させるための実践的なアドバイスを提供します。
もくじ
もっと見る
慢性疲労症候群で利用できる公的支援制度
慢性疲労症候群(CFS)は日常生活に大きな影響を与える疾患です。症状の程度により仕事を続けることが難しくなったり、治療費の負担が大きくなったりする場合に利用できる公的支援制度について解説します。
障害年金の申請と受給条件
慢性疲労症候群の症状が重く、日常生活や就労に支障をきたす場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
社会保険労務士
障害年金の申請には、初診日から1年6ヶ月経過後の障害認定日における症状の程度が判断されます。医師の診断書には患者の疲労度合いや日常生活における制限が具体的に記載される必要があります。
障害者手帳の取得方法とメリット
症状が重く療養生活を送っている方は二次障害で障害者手帳の取得ができる可能性があります。手帳取得で得られるメリットには以下のようなものがあります。
- 医療費の助成
- 各種手当の支給
- 税の軽減
- 交通機関などの割引
傷病手当金の申請手続き
会社員で健康保険に加入している方が病気で働けなくなった場合、傷病手当金を受給できることがあります。標準報酬日額の3分の2程度が最長1年6ヶ月まで支給されます。申請には医師の診断書と勤務先の証明が必要です。
国民健康保険の加入者は対象外のため注意が必要です。また、業務外の理由で生じた場合に限られます。
出典:
自立支援医療制度の利用方法
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療費の自己負担額を軽減する制度です。通常3割の医療費負担が原則1割になります。指定の医療機関・薬局のみで利用可能です。
慢性疲労症候群の場合、二次障害として精神症状が出ている場合は精神通院医療の対象となる可能性があります。
出典:
生活保護制度の申請条件
長期間働けず経済的に困窮した場合は、生活保護の申請も選択肢となります。申請条件には以下のようなものがあります。
- 資産や能力など、あらゆるものを活用しても生活が困難であること
- 親族からの援助を受けられないこと
- 他の制度をすでに利用していること
福祉担当者
慢性疲労症候群により長期間働けない状態が続く場合、これらの公的支援制度を適切に活用することで、生活の安定と治療に専念できる環境を整えることが大切です。申請手続きが複雑な場合は、社会保険労務士や医療ソーシャルワーカーなどの専門家に相談することも検討しましょう。
慢性疲労症候群と就労支援
慢性疲労症候群(CFS)があっても、症状と上手に付き合いながら就労することは可能です。ここでは、利用できる就労支援サービスや就職活動のポイントについて解説します。
就労移行支援サービスの活用法
就労移行支援とは、障害者総合支援法に基づく福祉サービスで、就職に必要なスキル習得や就職活動のサポートを行う制度です。
就労支援専門員
慢性疲労症候群の方には、体調管理の指導や自分のペースでの職業訓練が特に有効です。事業所選びでは、体調管理への理解や柔軟な通所条件を確認しましょう。
関連記事

就労移行支援とは?対象者・支援内容から利用の流れまで徹底解説
就労移行支援は、障害者が一般企業で働くためのサポートを提供するサービスです。対象は18歳から65歳未満で、スキル習得や就職活動の支援が行われます。最大2年間の利用が可能で、個別の支援が提供されます。サービスは施設内での訓練や実習を通じて行われます。

就労移行支援で資格取得を目指そう!おすすめ資格と支援内容を完全ガイド
就労移行支援事業所で取得できる人気資格と、資格取得がもたらす自信や就職活動での強みなどのメリットを紹介。資格取得に強い事業所の選び方や地域別おすすめ事業所、さらに就労移行支援以外の資格取得支援制度まで、障害のある方のキャリアアップを総合的にサポートする情報が満載です。
ハローワークの専門支援窓口
ハローワークには障害のある方の就労を支援する専門窓口があります。障害特性に配慮した職業相談・紹介、トライアル雇用の紹介などが受けられます。医師の診断書があれば障害者手帳がなくても利用可能です。
障害者雇用制度を活用した就職活動
症状が重く一般雇用が難しい場合は、障害者雇用での就職も選択肢です。労働時間や業務内容の配慮を受けやすく、通院など治療との両立がしやすいメリットがあります。
面接時には症状と必要な配慮だけでなく、「どのような環境や働き方であれば能力を発揮できるか」という前向きな提案を含めると良いでしょう。
関連記事

障害者雇用とは?制度の仕組みやメリット・デメリットを徹底解説
障害者雇用の基本知識から実践方法までを解説。制度の仕組みや法定雇用率、一般雇用との違い、メリット・デメリット、実例の紹介、そして企業が進めるためのステップまで網羅。障害のある方の就労支援制度や最新動向も取り上げ、多様な人材が活躍できる社会づくりに向けた障害者雇用の理解を深める内容です。

障害者雇用促進法とは?企業の義務や雇用率、支援制度まで徹底解説
障害者雇用促進法の基本から企業の義務、支援制度まで徹底解説。法定雇用率や納付金制度、差別禁止と合理的配慮の提供義務などの重要ポイントをわかりやすく紹介。最新の法改正情報や違反時の対応も網羅し、企業が障害者雇用を適切に進めるための実践的なガイドです。
テレワークなど柔軟な働き方の選択肢
通勤による疲労は大きな負担となるため、テレワークなどの柔軟な働き方は有効な選択肢です。
- 在宅勤務(テレワーク)
- フレックスタイム制
- 時短勤務
- 隔日勤務
慢性疲労症候群の方に向いている職種としては、事務職、IT関連職、コンテンツ制作、カスタマーサポートなどが挙げられます。
自分の症状と体力に合った働き方を選ぶことが、長く安定して働き続けるための鍵となります。就労支援サービスを利用しながら、自分に合った働き方を見つけていきましょう。
相談窓口と支援ネットワーク
慢性疲労症候群(CFS)と診断されたとき、あるいは症状で悩んでいるときに、どこに相談すればよいのか分からず孤立感を抱える方も少なくありません。ここでは、相談できる機関や支援団体を紹介します。
都道府県・市町村の難病相談支援センター
難病相談支援センターは、難病患者さんやその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や支援を行う公的機関です。慢性疲労症候群は日本の指定難病には含まれていませんが、相談することは可能です。
保健師
各都道府県や指定都市に設置されており、療養生活や医療、就労に関する相談が可能です。
患者会と当事者コミュニティ
同じ病気を持つ人同士の交流は、情報共有や精神的な支えとなります。患者会では実際の体験に基づく生活の工夫や対処法についての情報交換ができます。体調によって直接参加が難しい場合は、オンラインでの交流の場も増えています。
オンラインでの情報収集と相談先
インターネットを活用することで、自宅にいながら様々な情報を得たり相談したりすることができます。信頼性の高い情報源としては、厚生労働省や国立精神・神経医療研究センターのウェブサイト、専門学会のガイドラインなどがあります。
情報源の信頼性を確認し、個人の体験談は参考程度にとどめ、医学的な判断は医師に相談することが大切です。
家族向けサポート情報
患者をサポートする家族も様々な困難や不安を抱えることがあります。家族向けの相談窓口としては、地域包括支援センター、市区町村の介護相談窓口、家族会などがあります。
家族が疲れ切ってしまうと、患者さんへの支援も難しくなります。必要なときには支援を求めることをためらわないようにしましょう。
慢性疲労症候群と共に生きていくために、一人で悩みを抱え込まず、様々な相談窓口や支援ネットワークを活用することが大切です。
慢性疲労症候群と仕事の両立
慢性疲労症候群(CFS)を抱えながら仕事を続けることは挑戦となりますが、適切な対策と環境調整によって症状と上手に付き合いながら働き続けることは可能です。
体調管理と無理のない働き方
慢性疲労症候群と仕事を両立するためには、何よりも体調管理が最優先です。自分の体調のパターンを理解し、エネルギーを効率的に使うことが重要です。
リハビリテーション医
働き方の工夫としては、時短勤務やフレックスタイム、在宅勤務の活用、通勤ラッシュを避ける時間帯の出勤などが効果的です。
職場での理解を得るためのコミュニケーション
慢性疲労症候群は「見えない障害」のため、職場での理解を得るには効果的なコミュニケーションが不可欠です。信頼できる上司や人事担当者に相談し、具体的にどのような配慮があれば業務遂行が可能かを提案しましょう。
「疲れやすい」と言うだけでなく、具体的な症状と業務への影響、そして対策を伝えることが重要です。
業務調整と合理的配慮の申し出方
合理的配慮として検討できるのは、勤務時間の調整、業務内容の調整、休憩スペースの確保、作業環境の調整などです。配慮を申し出る際は、医師の意見書があると説得力が増します。
休職制度の活用と復職支援
症状が悪化した場合は、休職制度を活用し治療と回復に専念することも検討しましょう。復職に向けては、医師と相談しながら段階的に職場復帰を目指すことが大切です。
復職後も症状の波に合わせた働き方の調整が必要です。定期的に上司や産業医と面談し、無理のない働き方を継続的に検討していきましょう。
慢性疲労症候群と仕事を両立させるためには、自己管理能力とコミュニケーション能力が鍵となります。
自分の体調と向き合いながら、職場との良好な関係を構築することで、長期的に安定した就労を続けることができるでしょう。
慢性疲労症候群(CFS)とは
慢性疲労症候群(Chronic Fatigue Syndrome: CFS)は、筋痛性脳脊髄炎(Myalgic Encephalomyelitis: ME)とも呼ばれ、長期間にわたる極度の疲労感や様々な身体症状を特徴とする疾患です。
慢性疲労症候群の基本知識と特徴
慢性疲労症候群は、普段どおりの日常生活を送れないほどの強い倦怠感や睡眠障害などの症状が、6ヶ月以上にわたって続く神経免疫系の疾患です。通常の疲労とは異なり、休息を取っても回復しないことが大きな特徴です。
神経内科医
主な症状と日常生活への影響
主な症状には、強い疲労感、筋肉痛や関節痛、頭痛、喉の痛み、認知機能の低下(「ブレインフォグ」)、光や音に対する過敏症などがあります。症状の重さによって日常生活への影響も異なり、重度の場合は基本的な自己ケアも困難になることがあります。
診断基準と受診すべき医療機関
慢性疲労症候群の診断は、特定の血液検査や画像検査で確定できるものではなく、他の疾患を除外しながら症状のパターンや経過から総合的に判断します。受診先としては内科(総合内科、神経内科)、総合診療科、心療内科などが考えられます。
原因と発症メカニズム
正確な原因はまだ解明されていませんが、ウイルス感染、免疫系の異常、神経内分泌系の機能障害、自律神経系の調節障害など、複数の要因が関与している可能性があります。多くの患者は感染症様の症状の後や強いストレスの後に発症することが多いとされています。
慢性疲労症候群は目に見えない症状が多く理解されにくい病気ですが、実際の生物学的異常に基づく疾患であることが科学的にも明らかになってきています。
慢性疲労症候群の治療とセルフケア
慢性疲労症候群(CFS)は根治が難しい疾患ですが、適切な治療とセルフケアによって症状を軽減し、生活の質を向上させることが可能です。
医学的アプローチと治療法
現在のところ、慢性疲労症候群を完全に治す特効薬はありませんが、症状に応じた様々な治療アプローチが行われています。
- 薬物療法:痛み止め、抗うつ薬(少量)、睡眠薬など症状を緩和する薬
- 認知行動療法(CBT):症状への対処能力を高める心理療法
- 段階的運動療法:非常に軽い運動から少しずつ活動量を増やす方法
理学療法士
日常生活での体調管理のコツ
日々の生活習慣の調整は症状の安定に重要です。睡眠の質を高める工夫(同じ時間に寝起き、寝室環境の整備)、バランスの取れた食事(消化しやすい食事、抗酸化作用のある食品)、ストレス管理(リラクゼーション技法、マインドフルネス)を心がけましょう。
活動とエネルギーの配分(ペーシング)
ペーシングとは、限られたエネルギーを効率的に使い、「活動と休息」のバランスを取る方法です。活動日記をつけて自分のエネルギー消費を把握し、活動を小さなステップに分け、活動の前後に休息を取るなどの工夫が効果的です。
慢性疲労症候群の治療とセルフケアは、医学的なアプローチと日常生活での工夫の両方が重要です。
症状や体調は人それぞれ異なるため、自分に合った方法を見つけていくプロセスが大切になります。
よくある質問と回答
慢性疲労症候群(CFS)に関する疑問に専門家の視点からお答えします。
慢性疲労症候群で障害年金はもらえますか?
症状が重く日常生活に大きな支障がある場合は受給可能性があります。診断書に症状の具体的な影響を詳細に記載してもらうことが重要です。
慢性疲労症候群は完治しますか?
リハビリテーション医
一人で悩まず、専門家のサポートを受けながら、症状と上手に付き合う方法を見つけていきましょう。