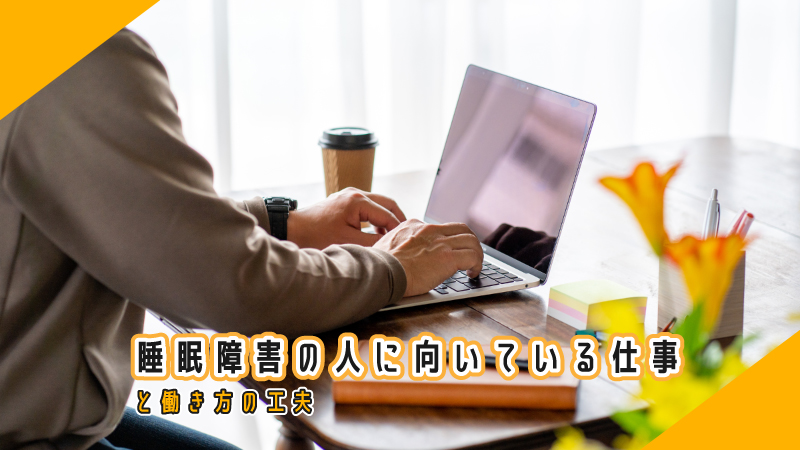
- このコラムのまとめ
- 眠れない夜が続いたり、日中の強い眠気に悩まされたりする睡眠障害。悪化すると仕事の生産性や人間関係に大きな影響を与えてしまうケースもあります。「このまま正社員として働き続けられるのか」「どんな仕事なら両立できるのか」と不安を抱える人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、睡眠障害の種類や症状の特徴、仕事への悪影響などの基本的な情報を紹介。さらに睡眠障害と仕事を両立させるための対策や、働き方の選び方、睡眠障害の人でも働きやすい仕事などを解説します。
もくじ
もっと見る
自分はどの睡眠障害?種類や症状の特徴、仕事への悪影響をチェック
睡眠障害にはさまざまな種類がありますが、仕事に支障をきたすものとしては、大きく分けて不眠症・過眠症・概日リズム睡眠障害があります。それぞれ症状が異なるため、どれが自分に当てはまっているかをチェックしてみてください。
不眠症は寝つけない・途中で起きる・早朝覚醒で日中の集中力を奪う
不眠症は「寝つけない(入眠困難)」「途中で目が覚める(中途覚醒)」「早朝に目覚めてその後寝られない(早朝覚醒)」といった睡眠問題から、不調が出る病気です。不眠状態が慢性的に続くと、睡眠時間や質が確保できず、脳や身体の回復が不十分になり、日中におけるパフォーマンス低下を招いてしまいます。
よくある症状は、起床時から疲労感が残っているケースです。また集中力が続かず仕事の効率が下がる、記憶力や注意力が散漫になりミスをしてしまう、イライラ・気分の変動が起こるなど、さまざまな弊害が生じる可能性がある疾患だといえるでしょう。
厚生労働省のe-ヘルスネットでも、不眠症の条件として「夜間の不眠が続き、日中に倦怠感・意欲低下・集中力低下などの不調が出ること」を挙げています。
参照:
過眠症は強い眠気や居眠り発作で仕事や生活に深刻な支障をきたす
過眠症は、夜に十分な睡眠をとっているにも関わらず、日中に強い眠気が続き、時に居眠り発作を起こす点が特徴。国立精神・神経医療研究センターによれば、過剰な日中の眠気と居眠りが主な症状です。
参照:
また、居眠りが1時間以上続く、起きてもすっきりせず疲労感が残るといった症状もあります。
これらは通勤や会議、作業中に予期せず眠り込むリスクを伴い、業務遂行に支障をきたすだけでなく、大きな事故や誤解の原因になるケースも。運転手や機械のオペレーターなど、操作ミスが即事故に直結するような職業の場合は、とくに注意が必要だといえるでしょう。
概日リズム睡眠障害は昼夜のサイクルと体内時計のリズムが合わず、生活が困難になる
概日リズム睡眠障害は、体内時計と昼夜のサイクルがずれることで、望ましい時間に眠れなかったり、起きられなくなったりする状態を指します。例えば夜遅くにしか眠れず朝が起きられない、毎日眠る時間がずれていく、交替勤務の影響で覚醒リズムが乱れるなどのパターンが典型的です。
リズムが乱れると、例え睡眠時間を確保できていても、決められた時間での通勤・勤務がしづらくなり、遅刻・欠勤・集中力低下・生活リズム崩壊といった影響を招きやすくなります。
睡眠障害の原因はストレス・生活習慣・夜勤など複数の要因が重なって起こる
睡眠障害の原因は一つではなく、ストレス・生活習慣の乱れ・夜勤・交替勤務による生活リズムのズレなど、複数の要因が重なって発症や悪化を引き起こします。
例えば心理的な緊張や不安、過重労働、人間関係の悩みなどのストレスを感じると、睡眠が妨げられるケースも。また就寝時間や起床時間が不規則、夜遅くまでのスマホ使用、カフェイン・アルコールの乱用、運動不足なども睡眠リズムを乱す原因になります。
体内時計が狂いやすい夜勤・交替勤務も、睡眠障害の代表的な原因です。例えば、看護師など交代勤務者の場合では、連続夜勤や不規則シフトが睡眠覚醒リズムを乱し、慢性的な不眠を引き起こす例が報告されています。
睡眠障害があっても仕事を続けるために実践したい4つの対策
睡眠障害があっても仕事を続けるためには、次のような4つの対策が考えられます。
- ①生活リズムを整えて、睡眠障害の改善を図る
- ②セルフケアで限界を感じたら、専門医での治療を検討する
- ③職場に相談して理解を得て、合理的配慮をしてもらう
- ④場合によっては休職やリワークも視野に入れる
以下の項目で、各対策を詳しく解説します。

日中の眠気を防ぐなら仮眠・光・カフェインに注目
日中の強い眠気に悩む人は、生活リズムを整えたうえで仮眠・光・カフェインを上手に活用することが効果的です。
例えば昼間の強い眠気には、15〜30分程度の短い仮眠をとることで集中力の回復が期待できます。ただし、長く眠ると逆にぼんやりしたり、夜の睡眠に影響が出るため注意しましょう。
また、起床後すぐに太陽光を浴びるのもおすすめです。自然光を浴びることで体内時計がリセットされ、日中は覚醒しやすく、夜は眠りに入りやすくなる効果が期待できます。
カフェインは眠気を抑える有効な手段ですが、摂りすぎは禁物。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠ガイド2023」によれば、1日のカフェインの摂取量は400mgを超えないことが推奨されています。また、夕方以降の摂取は睡眠を悪化させるリスクがあるため、控えるのが無難です。
参照:
セルフケアだけで限界を感じたら、専門医での治療も検討しよう
睡眠障害はセルフケアで改善できる場合もありますが、症状が長引いたり、日中の生活に大きな影響が出ていたりするときには専門医での治療も検討する余地があります。
睡眠障害には不眠症・過眠症・概日リズム睡眠障害など複数のタイプがあるため、当事者では正確に見極めることが困難です。生活習慣を整えても休養感が得られないなら、医療的支援が必要なケースである可能性が高いといえます。
睡眠障害の具体的な治療方法は、睡眠薬や体内時計に作用する薬を用いる薬物療法や、認知行動療法、生活習慣指導など。適切な治療法は人によって異なるため、まずは専門医に症状を相談し、診断してもらいましょう。
治療を続けながら働くには、職場に相談して理解を得よう
睡眠障害の治療を続けながら働くには、職場に自分の状態を相談し、理解を得ることが欠かせません。医療的サポートと同時に働く環境も整えられれば、精神的にも安心感を得られるでしょう。
働く環境を整えること自体は、実は難しくありません。現在は、法律的にも職場に一定の配慮が求められているからです。2024年4月に改定された障害者差別解消法では、企業に「合理的配慮」の提供が義務化されています。
参照:
具体的には、フレックス勤務・在宅勤務・夜勤回避・仮眠スペースの活用などが配慮の可能性として挙げられます。睡眠障害の治療をしつつ、業務量や就業時間を調整できれば、無理なく働ける可能性も高くなるといえるでしょう。
職場での配慮だけで難しいときは、休職やリワークも検討してみて
職場での配慮を受けても働くのが難しいと感じる場合は、休職やリワークの活用を検討してみてください。無理に働き続けて症状を悪化させるより、一時的に休職して治療や回復に専念したほうが、長期的には安定して働けますよ。
リワークでは、医療機関や地域の就労支援センターで生活リズム・ストレス対処・体力気力の回復などを目指すプログラムに取り組み、復職に向けた準備を進めます。自宅での療養から直に職場に復帰するのではなく、一旦復職プログラムを挟むことで、求職・復職間のギャップが乗り越えやすくなるのもメリットです。
現在の仕事を睡眠障害と両立するには?正社員・在宅勤務・フリーランスなど勤務形態別の工夫を紹介
現在の仕事を睡眠障害と両立するには、業務調整や自己管理を行うなどの工夫が重要です。以下の項目では、正社員・在宅勤務・シフト勤務・フリーランスなどの勤務形態別に、工夫すべきポイントを紹介します。
正社員なら、業務調整や残業の削減などを職場に相談してみよう
正社員の場合は、業務調整や残業の削減などを職場に相談してみるのがおすすめ。業務の過重負担や長時間残業は睡眠障害の悪化につながりやすいため、業務量の調整を図る工夫が必要です。
例えば残業を削減する以外にも、業務量を他のメンバーと分担する、フレックスタイムや在宅勤務、時短勤務を組み合わせるなどの方法があります。また、産業医や人事部に相談し、医師の意見書をもとに就業制限をかけてもらうケースも考えられるでしょう。
シフト勤務は夜勤を避けたり固定化したりすることで悪化リスクを減らせる
シフト勤務では、夜勤を避けたり勤務時間を固定化したりすることで、睡眠障害の悪化リスクの減少が期待できるでしょう。夜勤や不規則な交替勤務を続けると、体内リズムが崩れ、不眠や過眠が悪化しやすくなってしまいます。
具体的な工夫としては、夜勤回数を減らす、連続夜勤を避ける、できるだけ日勤を中心にする、といった方法が考えられるでしょう。また、どうしても夜勤が必要な場合には、シフトを早番→中番→遅番の順で組んだり、交替間隔を十分に確保したりすると、体内リズムの乱れを比較的抑えられます。
個人事業主・業務委託は自己管理を徹底するための工夫が大切
個人事業主や業務委託契約で働く場合は、自己管理の工夫が欠かせません。勤務時間の自由さがある反面、生活リズムが不規則になりやすく、睡眠障害の症状を悪化させる可能性があるからです。
例えば仕事時間をあらかじめ決めておく、睡眠時間を毎日一定に保つ、作業の合間に仮眠や休憩を入れるといった工夫が有効。また、自宅兼仕事場の場合は、オン・オフを切り替えるために作業環境を整えることも大切です。
さらに、定期的に健康診断や医師のチェックを受けるのも重要。個人事業主や業務委託契約を行うフリーランスは、こと不摂生になりがちです。しっかりと生活習慣を整え、計画的に休息を取ることが、睡眠障害と仕事を両立するうえで不可欠な取り組みだといえるでしょう。
睡眠障害に向いている仕事は、働き方で変わる
睡眠障害に向いている仕事は、働き方で変わります。例えば正社員で働きたいなら、定時勤務のある事務・経理職などが適職。裁量性のある仕事なら、プログラマーやライターを検討してみてもよいでしょう。以下で、働き方別に向いている仕事を解説します。
定時勤務・裁量性のある仕事なら事務・経理職やプログラマー・ライターがおすすめ
定時勤務や裁量性のある仕事は、睡眠障害を抱える人にとって体調管理と両立させやすい働き方のひとつです。定時勤務であれば、比較的始業・終業時間が一定しています。裁量性は自分の裁量で業務時間・内容を調整できるため、規則正しいリズムを保ちやすいといえるでしょう。
具体的な職種としては、定時勤務が多い事務職や経理職などが挙げられます。また、企画職やライター、プログラマーといった裁量性のある職種は、体調に合わせて作業時間を調整しやすいのが特徴です。
在宅勤務や時短勤務は職種を問わず継続しやすい働き方
在宅勤務や時短勤務は、職種を問わず継続しやすい働き方のひとつです。在宅勤務は、自分の生活リズムに合わせて休憩や仮眠を取りやすく、睡眠障害による日中の眠気に対応できるのが大きな魅力。通勤・退勤時の負担がなくなるので、ストレスを軽減できるのもメリットだといえるでしょう。
時短勤務では、就労時間を減らすことで疲労の蓄積を抑え、治療や通院に時間を割くことも可能です。例えば合理的配慮として時短勤務・在宅勤務を活用できれば、身体的・精神的な負担はかなり軽減できるでしょう。
フリーランスや業務委託契約はプログラマー・ライター・デザイナーなどの自由度が高い仕事を選ぼう
フリーランスや業務委託契約の働き方は、自由度が高く自分の生活リズムに合わせやすいため、睡眠障害を抱える人にとって有効な選択肢のひとつです。固定的な出勤や長時間労働に縛られにくく、体内時計の乱れや慢性的な疲労を避けやすいといえるでしょう。
向いている職種としては、ライターやデザイナー、プログラマーなど、時間や場所を選ばず働ける仕事が挙げられます。自分の睡眠リズムや通院予定に合わせて、業務を進めやすいのがメリットです。一方で、働きすぎて生活リズムが崩れないよう、1日の業務量を調整したり、予め勤務時間を定めたりするなどの自己管理が欠かせません。
睡眠障害が原因で仕事を辞めるべきか迷ったときの判断基準は?
睡眠障害が原因で仕事を辞めるべきか迷ったときには、健康・経済・治療の3項目から総合的に判断するのがおすすめです。また、辞める決断を下す前に、まずは職場に働き方を変えられないか相談してみるのも重要。以下で、各ポイントを詳しく解説します。
仕事を辞めるかどうかは健康・経済・治療の3つのポイントから判断しよう
仕事を辞めるかどうか迷ったときは、健康・経済・治療の両立が可能かどうかの3つを判断基準にすることが大切です。感情的に決めるのではなく、複数の観点から冷静に考えることで後悔しない決断ができるでしょう。
例えば、健康面の理由だけで退職してしまうと、その後の生活費や治療費などの経済面での問題が生じることがあります。逆に経済面のみ考えて仕事を継続すると、睡眠障害が悪化してしまう可能性もあるでしょう。
この悪循環を避けるためには、3つの観点をバランスよく考えるのが重要。健康面では治療を続けながら働けるか、経済面では収入が生活に十分か、医療費や休職制度で補えるか、治療面では通院やリワークに時間を割けるかなどを多角的に考えていけば、自分にとって現実的な選択肢が見てくるはずです。
辞める前に休職・異動・時短勤務など改善策を試すのが賢明
仕事を辞めるか迷った際には、休職や異動、時短勤務といった手段がとれないかを検討・相談してみるのも重要です。上記の働き方改善を行うことで、健康を守りながら働き続ける可能性を残せるケースも少なくありません。
例えば、まず休職で治療や回復に専念し、その後は異動で業務内容を変える、あるいは時短勤務を活用して労働時間を減らす方法があります。辞める決断を下す前に、まずは職場に働き方を変えることができないか相談してみるとよいでしょう。
睡眠障害と仕事でよくある悩みQ&A
本項目では、睡眠障害と仕事に関してよくある悩みや質問に回答します。いずれも重要なポイントなので、ぜひご一読ください。
睡眠障害があっても正社員として働ける?
睡眠障害があっても、正社員として働くことは十分可能です。重要なのは、1人で悩みを抱え込まないこと。職場に相談し、残業削減や勤務時間の調整などができるかを話し合いましょう。さらに治療やセルフケアを並行すれば、長期的に安定して働き続けられる可能性が高まります。
不眠症や過眠症でもできる仕事はある?
不眠症や過眠症でも取り組みやすい仕事はあります。例えば上述したように、経理職や事務職など、定時勤務の多い仕事は生活リズムが崩れにくいといえるでしょう。また、プログラマーやライター、デザイナーなどの裁量性がある職種も、自分で業務量を調整しやすいため向いています。
上司に睡眠障害を相談するべき?
睡眠障害を1人で抱えるよりも、信頼できる上司に相談するほうが働きやすさにつながります。睡眠障害は合理的配慮の対象となる場合もあり、勤務時間の調整や業務の軽減を受けられる可能性があります。相談する際は、医師の診断書を添えると理解を得やすくなりますよ。
薬を飲みながらでも仕事は続けられる?
睡眠障害の薬を飲みながらでも仕事を続けることは可能です。副作用や眠気には個人差があるため、主治医に相談するのがベター。必要に応じて職場にも伝え、勤務内容を工夫すれば、身体や心への負担を減らしながら働き続けられるでしょう。
まとめ
今回は、睡眠障害の種類や仕事への影響を紹介するとともに、睡眠障害と仕事を両立させるためにとるべき対策や睡眠障害に適した働き方、職種などを解説しました。
睡眠障害は、不眠症や過眠症といった症状により、集中力の低下や疲労感の蓄積など、仕事への影響が大きいもの。しかし、生活習慣の見直しや専門医での治療、職場への相談や合理的配慮の活用によって、働きながら改善を目指すことも可能です。また、定時勤務や在宅ワーク、フリーランスなど体調に合わせやすい仕事を選ぶことで、無理なくキャリアを続ける道も広がるでしょう。
睡眠障害に悩んでいる人は、ぜひ本記事を参考にして自分にあった働き方や仕事を見つけてみてください。



