公開日:2025.10.17
学習障害でもできる仕事は?学習障害の人に向いている職業と働き方
- ホーム
- コラム
- 「障がいについて」のコラム
- 学習障害でもできる仕事は?学習障害の人に向いている職業と働き方
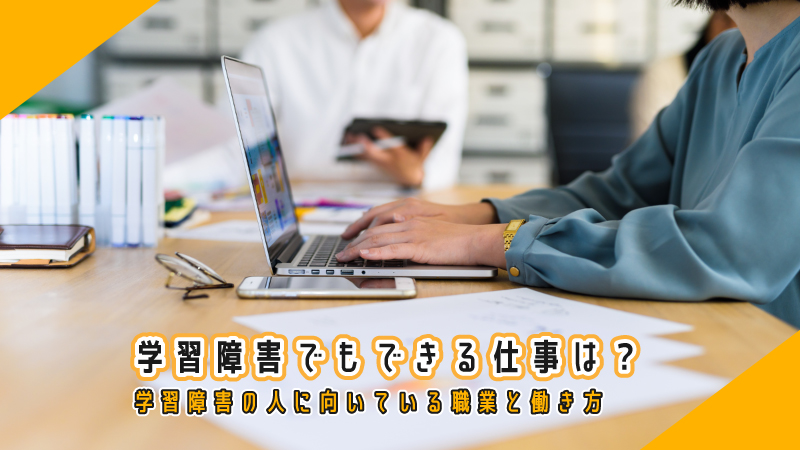
- このコラムのまとめ
- 「学習障害があっても働ける仕事はあるの?」「LDの人に向いている職業ってどんなもの?」と悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。学習障害(LD)は、知的な発達に問題がない一方で、読み書きや計算などの分野でつまずきを感じる発達障害の一種。とはいえ自分の特性を理解して、得意分野を活かせる職種を選べば、無理なく長く働くのは十分可能です。そこで今回は、学習障害の特徴やタイプを紹介するとともに、タイプ別の向いている仕事や働きやすい職場環境の整え方、合理的配慮の受け方、就労支援サービスの活用方法などを詳しく解説します。学習障害を抱えていて、仕事について悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
学習障害(LD)とは?どのような特徴がある?
学習障害とは、知的な発達に遅れは見られないものの、読み書きや計算などを行う際に困難が生じる発達障害の一種。その一方で、苦手分野以外の学習や仕事は問題なくこなせるケースが多いのも特徴です。
学習障害には、主に3種類のタイプがあります。一般的に文字を読むのが困難な識字障害(ディスレクシア)、文字・文章を書くのが苦手な書字障害(ディスグラフィア)、数字や記号などの認識が困難な(ディスカリキュア)に分類される障害です。
なお学習障害になる原因は、特定されていないのが現状。文部科学省の発表でも「学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。」とされています。
参照:
大人の学習障害は仕事にどのような影響を及ぼす?
学習障害のある人が仕事をするうえでは、障害がさまざまな影響を及ぼします。例えば読字障害の場合、メールや報告書などの文書を短時間で把握するのが難しく、内容を正確に捉えるのに時間がかかることも。また、会議資料やマニュアルのように文字情報が多い業務では、情報処理の遅れがストレスにつながることもあります。
書字障害は、手書をはじめとした文章作成に時間がかかる傾向。メモを取るスピードが追いつかない、誤字脱字が多くなるといった困難があり、正確な書類作成を求められる場面では負担が大きくなりがちです。また、字が読みにくいことで周囲の理解が得られず、誤解を招くこともあります。
算数障害は、金銭管理や数値の扱いに関する業務で苦労するケースが一般的。売上の集計や経費計算のような数値処理が多い仕事では、桁を読み間違えたり計算の途中で混乱したりするケースも。またグラフや表の読み取りが必要な職種でも、情報の整理に時間がかかる傾向があります。
学習障害の人に向いている職業は?タイプ別に紹介
学習障害の人に向いている職業は、読字・書字・算数どの障害があるかで異なります。以下でタイプ別に適した職業や仕事内容を紹介しているので、参考にしてみてください。
なお、障害の程度や仕事の向き・不向きは人によって大きく異なります。またADHD・ASDなどのほかの障害を併発しているかどうかでも違うため、あくまで参考程度に捉えておきましょう。
読字障害(ディスレクシア)は創作系の仕事が向いている可能性がある
読字障害のある人は、創作系の仕事が向いている可能性があります。読字障害の人は「視空間認知能力」が高い傾向を持つといわれていることが理由です。言葉による情報処理は難しくても、形や構造、空間の配置を直感的に把握する力に優れているケースは少なくありません。
そのため、字を扱う作業が中心でない職種のなかでも、創造的な仕事内容が向いているといえるでしょう。例えば図面やデザイン、色彩構成といった視覚で考える仕事は、視空間認識能力と相性が良いとされています。ほかにも建築士やデザイナー、イラストレーターなどでは、独自の感覚や発想を活かして活躍できる可能性がありますよ。
また言語をあまり使わない職種としては、カメラマンやスタイリストなどのクリエイティブ系の仕事もおすすめ。感覚や観察力、構成力が重視されるため、読字に関する困難が直接的な支障になりにくいといえます。
書字障害(ディスグラフィア)はPCを扱う職業がおすすめ
書字障害のある人は、PCを扱う職業がおすすめです。書字障害は、文字を書くことや文章を構成することに困難を抱える傾向。しかし、パソコンやタブレットなどのデジタル機器を活用することで、その負担を大きく軽減できる場合があります。また入力補助や音声入力を利用することで、業務をスムーズに進められるケースも少なくありません。
PCを扱う職業のなかで、書字障害に向いている職種としては、ITエンジニアやデータ入力、Webデザイナーなどのオフィスワークなどは比較的適性があるといえます。タイピングやコード入力などが中心となり、文章を手で書く場面がほとんどないため、障害の影響を受けにくいといえるでしょう。
また、そもそも文字を扱う機会が少ない仕事も向いています。例えば建築・土木・製造などの現場作業や機械を扱う工場業務などは、書字障害の人にとっては取り組みやすい職場環境です。
ほかには発想力や構想力を必要とするような、言葉よりもイメージや感覚で構築していく作業が多い仕事も向いている可能性も。3Dモデリングや映像制作、音楽編集などのデジタルクリエイティブが当てはまります。
算数障害(ディスカリキュア)は数字を使用しない領域の仕事を検討してみよう
算数障害のある人は、数字をなるべく使わない領域の仕事がおすすめです。算数障害は数式や金額、グラフなどを正確に処理する作業では混乱が生じやすく、事務や経理など数字を扱う職種では負担が大きくなる場合があります。そのため、数値を中心とした業務から離れ、体感的・実践的に覚えられる仕事を選ぶことが、能力を活かすうえで効果的です。
例えば製造業・建築・整備などの現場で身体を使う仕事は、数字よりも感覚や手順の理解が重視されるため、算数障害の人に向いていることが多いといえます。
また、感覚的な観察力や創造性を生かせる分野が向いているケースも。例えばカメラマン・スタイリスト・美容師などは、数値的な精度よりもセンスや丁寧さ、対人スキルが求められるため、算数障害による不便さを感じにくい環境を作りやすいといえるでしょう。加えて接客業・介護・動物関係なども数字より人にフォーカスした仕事のため、適している可能性があります。
学習障害の人の仕事の続け方や、職場選びのコツ
学習障害の人が長く働くためには、仕事をしたり職場選びをしたりするうえでいくつかの抑えておきたいポイントがあります。以下で、障害があっても働きやすい環境づくりをするためのコツや工夫を紹介しているので参考にしてください。
大前提として、自分の症状を明確に把握しておく
学習障害のある人が自分に合った仕事を見つけるためには、まず自分の症状を正確に理解しておくことが大前提。同じ学習障害でも、読字・書字・算数のどの分野に困難があるのかや、障害の程度や影響の出方は人によって大きく異なります。例えば読むスピードが遅い人もいれば、文字の形を正確に認識しにくい人もおり、同じ診断名でも日常や仕事で感じるつまずきはさまざまです。
自分の症状や不得意なことを把握しておけば、働くうえでどのようなサポートや配慮が必要かを具体的に伝えやすくなるのがメリット。例えば、文字情報が苦手な場合は口頭での指示を希望したり、計算が苦手な場合は自動計算ソフトの導入を相談したりといった対策が立てやすくなりますよ。
自分の特性を客観的に把握することは、どんな仕事が向いているかを判断する土台になるだけでなく、就職活動や職場定着の支援を受ける際の重要な情報にもなります。障害特性の理解を深めることで、安心して働ける環境づくりがしやすくなるでしょう。
障がい者雇用枠で働くことを検討する
学習障害でもハンデを感じずに働ける環境を整えたい場合は、障がい者雇用枠での就職を検討することも有効な選択肢です。障がい者雇用枠とは、障害者雇用促進法に基づき、企業や公的機関などに一定割合の障がい者を雇用することを義務づけた制度。障害者雇用枠で採用されると、職場環境の配慮や勤務形態の柔軟化など、障害に合わせた支援を受けられる可能性が高まります。
障がい者雇用枠で働くためには、障害者手帳を所持していることが前提条件です。学習障害の場合、症状の程度が基準を満たしていれば、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられる場合があります。
申請の手続きは、住んでいる市町村の障害福祉担当窓口で行いましょう。申請後は各自治体の精神保健福祉センターで審査が実施され、基準を満たすと手帳が交付されます。ただし、学習障害があっても、症状の程度や生活・就労への影響が軽い場合は交付されないケースも。手帳の取得を検討している場合は、まず主治医や自治体の福祉窓口に相談してみてください。
参照:
職場で合理的配慮を受けられないか相談してみる
現在の職場や就職先で働きにくさを感じている場合は、合理的配慮を受けられないか相談してみることも大切です。合理的配慮とは、障がいのある人が業務を行ううえで、事業主に対して働きやすくするための調整を求められる仕組み。2024年4月の障害者差別解消法の改正により、民間企業にも合理的配慮の提供が義務化されています。
例えば読字障害のある人には、文書情報を音声で提供したり、会議資料を事前に共有して内容を把握しやすくしたりする配慮が考えられるでしょう。文字を追う負担を軽減し、理解に集中できる環境を整えられれば、業務効率を大きく改善できる可能性がありますよ。
書字障害のある人の場合は、パソコンやタブレットでの入力を認めてもらうことが有効です。また、会議などでメモを取る代わりに録音を許可してもらうなどすれば、負担を減らしながら情報を正確に扱えるようになります。
算数障害のある人には、数値を自動で計算・整理できるツールの導入や、集計・経理など数字を扱う作業を他のメンバーと分担するなどが効果的。またグラフや表の説明を口頭や図解で補足してもらうといった配慮を受ければ、誤解を防ぎながら業務を進めやすくなるでしょう。
参照:
学習障害について相談できる窓口が設置されている会社を選ぶ
学習障害でも働きやすい職場を選ぶ際には、障害を相談できる窓口が整備されているかを確認しておくことが重要です。学習障害を抱えながら働いていると、業務の進め方や人間関係、理解のされにくさなど、日常の中でさまざまな問題に直面する可能性があります。こうした状況が続くと、ストレスが蓄積して心や体の不調を引き起こすことも。安心して話せる場があるかどうかは、働きやすさを左右する大きな要素です。
例えば労働者が50人以上在籍する事業所では、法律により産業医の選任が義務付けられています。産業医とは、職場での健康管理やメンタルヘルス支援を行う専門家。従業員のストレスや業務上の問題を業務との関係の観点から分析し、改善策を提案します。職場の環境調整や勤務内容の見直しなど、実務的なアドバイスを受けられるため、困ったときに相談できる存在として心強い味方になってくれるでしょう。
また、近年ではメンタルヘルス対策の一環として、法律上の義務がなくても独自に相談窓口を設ける企業が増えています。社内のカウンセラーや外部機関と提携して従業員の悩みに対応する体制を整えている企業もあり、安心して長く働ける環境づくりを重視する傾向が強まっているため、小規模な企業でも窓口があるかを確認してみるとよいでしょう。
学習障害のある人が就職・転職を考えるなら就労サービスを活用しよう
学習障害のある人が就職や転職を考える際には、公的な就労支援サービスの活用が効果的です。自分の特性に合った働き方を見つけるには、個人の努力だけでなく、専門的なサポートを受けながら就職活動を進めることが重要。とくに学習障害に理解のある支援機関では、職業訓練・面接練習・職場定着支援などを通して、長く働ける環境づくりを手伝ってくれますよ。
例えば就労移行支援事業所は、求職中や離職中の人を対象に、通所形式で就職に必要なスキルや知識を身につける支援を行う機関です。ビジネスマナーやパソコン操作の訓練、模擬職場での実習などを通じて、一般就労を目指すことができます。実際の企業と連携して実習や面接の練習を行うケースも多く、初めての就職やブランクのある人にも利用しやすい支援形態だといえるでしょう。
就労継続支援事業所は、障害や難病の影響で一般就労が難しい人を対象に、作業所での仕事を通して働くリズムを整えたり、職業スキルを身につけたりするサービスです。A型とB型の2種類があり、A型は事業所と雇用契約を結んで働く形態で、最低賃金が保証されます。B型は雇用契約を結ばず、作業量に応じた工賃が支払われる仕組みです。自分の体調やスキルに合わせて段階的に働くことができるため、無理のないペースで参加できますよ。
発達障害者支援センターでは、生活上の困りごとや仕事に関する悩みについて相談できるほか、発達検査や支援計画の作成を通して、他の支援機関と連携したサポートが受けられます。
ほかにも障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、ハローワークなども、学習障害に対するさまざまなサポートを用意しているので、ぜひ自分にあったサービスの活用を検討してみてください。
まとめ
本記事では、学習障害が仕事にどのような影響を与えるのかや、学習障害の種類、タイプ別の特徴や向いている職業、職場で受けられる合理的配慮の例、学習障害のある人が利用できる公的支援制度などを解説しました。
学習障害があっても、自分らしく働くことは十分に可能です。自分の特性を理解し、強みを活かせる環境を選んだり、就労サービスを活用したりして、働きやすい職場や職種を見つけてみてください。



