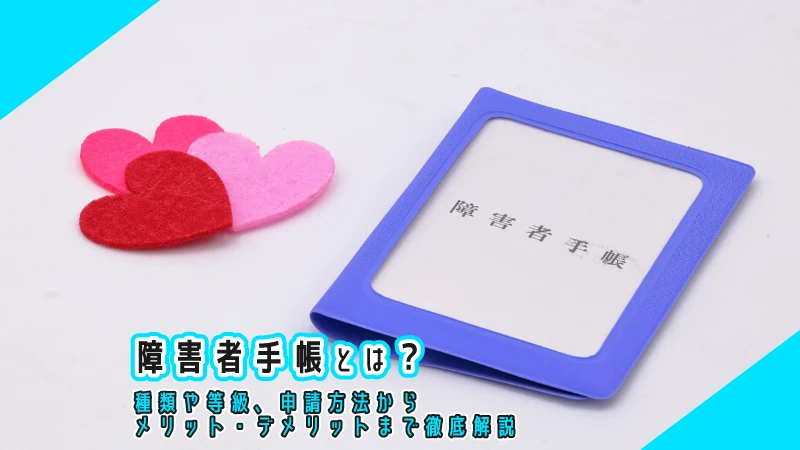公開日:2025.04.30
障害年金とは?受給条件から申請方法まで徹底解説【2025年最新版】
- ホーム
- コラム
- 「法律・制度」のコラム
- 障害年金とは?受給条件から申請方法まで徹底解説【2025年最新版】

- このコラムのまとめ
- 障害年金の基本的な仕組みから受給条件、申請方法、受給額まで徹底解説します。精神障害や発達障害も対象となる障害年金は、就労しながらでも受給可能なケースがあります。年金種類別の特徴や併用できる支援制度、不支給時の対応など、障害年金を適切に活用するための情報が満載です。
もくじ
もっと見る
障害年金とは?基本的な仕組みを解説
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に制限を受ける方を経済的に支援するための公的年金制度です。老齢年金と異なり、現役世代でも受給できる点が大きな特徴です。
障害年金の概要と目的
障害年金は、公的年金制度の一つで、病気やケガによって生活や仕事などに制限を受ける方に対して、生活の安定を図るために支給される年金です。公的年金には「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3種類があります。
| 年金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 老齢年金 | ある一定の年齢になった後の生活保障 |
| 遺族年金 | 一家の働き手が亡くなり、遺された家族の生活保障 |
| 障害年金 | 病気やケガで、働くことが難しいときの生活保障 |
障害年金を受給できる人の条件
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、年金制度に加入していること
- 保険料納付要件:初診日の前日において、保険料の納付済期間や免除期間などが一定以上あること
- 障害状態該当要件:障害の程度が法令で定められた基準に該当していること
これらの条件はいずれも重要ですが、特に「初診日要件」は、どの種類の障害年金を受給できるかを決める基準となります。
障害者手帳がなくても受給できる可能性
障害年金と障害者手帳は別々の制度であり、障害の認定基準も異なります。障害者手帳がなくても障害年金を受給している人は多くいます。逆に、障害者手帳を持っていても障害年金の受給条件を満たさない場合もあります。
障害年金の等級は独自に定められており、障害者手帳の等級とは連動していません。大切なのは、医師の診断書などによって障害の程度が障害年金の認定基準に該当することを証明することです。
働きながらでも受給可能な場合
障害年金は原則として就労の有無にかかわらず受給できます。実際に、障害年金受給者の約34%が就労しています。
ただし、働き方や障害の種類によって審査の際に考慮される点があります。特に精神障害や内部障害の場合、就労していることで「障害の程度が軽い」と判断される可能性があります。審査では以下のような点が重要となります:
- 障害者雇用や短時間勤務など、配慮された環境で働いていること
- 職場での援助や配慮の内容
- 就労によって健康状態に影響が出ていないかどうか
- 日常生活での困難さが継続していること
障害年金の審査は書類のみで行われるため、診断書や申立書などに就労状況や日常生活の困難さをしっかりと記載することが重要です。
出典:
障害年金の種類と特徴
障害年金には主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。どちらの年金を受給できるかは、初診日時点での加入年金制度によって異なります。
障害基礎年金の特徴と対象者
障害基礎年金は、国民年金に加入している方が受給対象となる年金制度です。初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していた場合に受給できます。
障害基礎年金の受給対象者となるのは、主に以下の方々です:
- 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、無職の方、学生など)
- 20歳未満で障害の原因となる病気やケガをした方
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間に初診日がある方
障害基礎年金の特徴として、対象となる等級は1級と2級のみで、3級はありません。また、金額は等級によって定額が定められており、子どもがいる場合には加算があります。
障害厚生年金の特徴と対象者
障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している方が受給対象となる年金制度です。初診日に厚生年金保険に加入していた場合に受給できます。障害厚生年金の受給者は、同時に障害基礎年金も受給することになります。
障害厚生年金の受給対象者となるのは、主に以下の方々です:
- 初診日に厚生年金保険に加入していた方(会社員、公務員など)
- 加入期間中に国民年金の保険料納付要件を満たしている方
障害厚生年金の特徴として、対象となる等級は1級から3級までです。1級と2級の場合は障害基礎年金に上乗せして支給され、3級の場合は障害厚生年金のみが支給されます。
障害手当金(一時金)について
障害手当金は、厚生年金加入者が対象となる一時金制度です。厚生年金に加入中に病気やケガをし、その症状が固定した時に、障害厚生年金3級よりも軽い障害が残った場合に支給されます。
障害手当金の主な特徴は以下の通りです:
- 一時金として1回のみの支給
- 初診日から5年以内に症状が固定した場合に受給可能
- 厚生年金加入者のみが対象
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害基礎年金と障害厚生年金の主な違いをまとめると、以下のようになります:
| 比較項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象者 | 国民年金加入者、20歳未満の方など | 厚生年金保険加入者 |
| 等級 | 1級・2級のみ | 1級・2級・3級 |
| 金額 | 定額制(等級によって固定) | 報酬比例制(過去の給与により変動) |
| 子の加算 | あり | 1級・2級の場合あり(基礎年金分) |
| 配偶者加給 | なし | 1級・2級の場合あり |
障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされるため、一般的に障害基礎年金のみを受給するよりも受給額が多くなります。また、障害厚生年金には3級があるため、比較的軽度の障害でも年金を受給できる可能性があります。
障害年金の受給条件を詳しく解説
障害年金を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。このセクションでは、初診日や保険料納付要件、障害認定日、障害等級などの受給条件について詳しく解説します。
初診日の重要性とは
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。この初診日は障害年金の受給資格を判断する上で非常に重要な日付となります。
初診日によって、どの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたかが確認され、受給できる障害年金の種類が決まります。また、保険料納付要件を確認する際の基準日にもなります。
初診日証明の方法と注意点
初診日を証明するためには、「受診状況等証明書」という書類を初診時の医療機関に記入してもらう必要があります。初診から長い時間が経過していて証明が難しい場合は、診察券のコピー、お薬手帳、領収書などの資料で補完することもできます。
保険料納付要件について
障害年金を受給するためには、保険料の納付状況が一定の条件を満たしている必要があります。基本的な条件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あることです。
ただし、2026年3月末日までに初診日がある場合は、「特例要件」として初診日において65歳未満であり、初診日の前日において直近1年間に保険料の未納がないことでも要件を満たせます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の状態を医学的に判断する基準となる日です。具体的には、初診日から1年6ヶ月を経過した日、または初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定した日となります。
障害認定日における障害の状態が、障害年金の等級に該当するか否かが審査されます。障害認定日に障害の状態が年金の支給対象となる等級に該当していなくても、その後症状が悪化した場合は「事後重症請求」という形で請求することができます。
障害等級の判定基準
障害年金の等級は、主に1級・2級・3級に分かれています。障害の程度によって等級が判定され、等級によって受給できる年金の種類や金額が異なります。
| 等級 | 障害の状態 | 受給できる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 障害基礎年金・障害厚生年金 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 障害厚生年金のみ |
障害の程度の判定は、医師が作成する診断書と、本人が提出する「病歴・就労状況等申立書」などの書類をもとに行われます。身体的な機能障害だけでなく、その障害が日常生活や就労にどの程度影響を与えているかも重要な判断材料となります。
障害年金の受給額はいくら?2025年最新情報
障害年金の受給額は、年金の種類や障害等級、家族構成などによって異なります。2025年現在の障害年金の受給額について、種類別に解説します。
障害基礎年金の受給額
障害基礎年金の受給額は、障害の等級によって定額が決められています。2025年度の障害基礎年金の基本受給額は以下の通りです:
| 等級 | 年間受給額(2025年度) | 月額換算(約) |
|---|---|---|
| 1級 | 1,039,625円 | 86,635円 |
| 2級 | 831,700円 | 69,308円 |
障害基礎年金は原則として1級と2級のみが対象となります。また子どもがいる場合、「子の加算」として追加の年金が支給されます。
- 第1子・第2子:1人につき年額239,300円
- 第3子以降:1人につき年額79,800円
出典:
障害厚生年金の受給額
障害厚生年金の受給額は、加入期間や過去の報酬などによって個人差があります。基本的な計算方法は以下の通りです:
- 1級:報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級の額
- 2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級の額
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障額あり)
3級の障害厚生年金には最低保障額が設定されており、2025年度は年額623,800円となっています。また、1級または2級の障害厚生年金を受給している方に65歳未満の配偶者がいる場合、「配偶者加給年金」として年額239,300円が加算されます。
障害手当金の金額
障害手当金は、初診日から5年以内に症状が固定し、障害等級3級より軽い障害が残った場合に一時金として支給されます。支給額は、報酬比例の年金額の2年分で、2025年度の最低保障額は1,247,600円です。
税金や社会保険料との関係
障害年金には税制上の優遇措置があります。主なポイントは以下の通りです:
- 所得税・住民税:非課税所得のため課税されません
- 国民健康保険料:保険料計算の所得に含まれません
- 国民年金保険料:障害等級1級または2級の方は法定免除の対象となります
ただし、障害年金を受給している方が扶養に入っている場合、受給額によっては健康保険の被扶養者要件から外れる可能性があることに注意が必要です。また、20歳前の傷病による障害基礎年金については、本人の所得に応じて支給停止となることがあります。
障害年金の申請方法と流れ
障害年金の申請は手続きが複雑ですが、適切な準備と理解があれば円滑に進めることができます。このセクションでは申請の流れと注意点を解説します。
申請前の準備と確認事項
障害年金の申請を始める前に、以下の点を確認・準備しておくことが重要です。
- 初診日の確認:障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日
- 加入年金の確認:初診日時点でどの年金制度に加入していたか
- 保険料納付状況の確認:年金事務所やねんきんネットで確認
- 障害認定日の確認:初診日から1年6ヶ月後または症状固定日
必要書類の一覧と入手方法
障害年金の申請には、以下の書類が必要です。
- 障害年金請求書:年金事務所や市区町村の窓口で入手
- 診断書:所定の用紙に医師に記入してもらう
- 病歴・就労状況等申立書:本人が記入
- 受診状況等証明書:初診時の医療機関に記入してもらう
- 戸籍謄本・住民票:市区町村役場で取得
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預金通帳のコピー:振込先の口座情報
診断書の作成依頼のポイント
診断書は障害年金の審査で最も重要な書類です。医師に依頼する際は、日常生活の困難さや就労状況を具体的に伝え、正確に診断書に反映してもらいましょう。
申請書類の提出先と方法
申請書類の提出先は、初診日の年金加入状況によって異なります。
- 障害基礎年金:住所地の市区町村役場の国民年金窓口
- 障害厚生年金:管轄の年金事務所
申請から支給決定までの期間と流れ
障害年金の申請から支給決定までの流れは以下の通りです。
- 申請書類の提出
- 審査(約2〜3ヶ月)
- 決定通知の受領
- 支給開始(決定後約1〜2ヶ月)
年金は2ヶ月に1回、偶数月の15日に2ヶ月分がまとめて指定口座に振り込まれます。初回の支給では、認定された支給日までさかのぼって支給されるため、まとまった金額が振り込まれることがあります。
障害年金受給後の注意点と手続き
障害年金の受給が決まった後も、いくつかの重要な手続きや注意点があります。このセクションでは、年金を継続して受給するために知っておくべき事項を解説します。
定期的な更新手続きについて
障害年金は、多くの場合、定期的に障害の状態を確認するための更新手続きが必要です。更新の種類には、以下の2つがあります。
- 永久認定(終身認定):両眼の失明、肢体の欠損など、状態が改善しない障害の場合で、更新手続きは不要
- 有期認定:1年、3年、5年ごとの更新が必要で、障害の程度によって期間が設定される
有期認定の場合、更新時期が近づくと日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送付されます。これを医師に記入してもらい、誕生月末日までに提出する必要があります。
状態変化時の届出
障害の状態や生活状況に変化があった場合には、以下のような届出が必要です。
- 障害が重くなった場合:「障害給付額改定請求書」で等級変更を請求できる
- 支給停止中に障害が重くなった場合:「支給停止事由消滅届」で支給再開を請求できる
- 住所や氏名が変わった場合:「住所・氏名・支払機関変更届」の提出が必要
- 受取口座を変更したい場合:「振込先口座変更届」の提出が必要
受給中に就労する場合の注意点
障害年金は原則として就労していても受給できますが、以下の点に注意が必要です。
- 所得制限:20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、年収が一定額を超えると支給停止や減額の対象となる
- 更新審査への影響:特に精神障害や内部障害の場合、フルタイム勤務は「障害が軽減した」と判断される可能性がある
- 扶養からの離脱:障害年金の受給により年収が増えると、健康保険の被扶養者要件から外れる可能性がある
老齢年金との併給について
65歳になると老齢年金の受給資格が発生します。基本的に障害年金と老齢年金は選択制ですが、65歳以降は特例として一部の組み合わせで併給できる場合もあります。どの選択が有利かは個人の状況によって異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
障害年金が不支給だった場合の対応
障害年金の申請をしても、必ずしも支給が認められるわけではありません。審査の結果、「不支給」となってしまうケースも少なくありません。このセクションでは、不支給となった場合の理由と対応策について解説します。
不支給決定の主な理由
障害年金が不支給となる主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 障害等級に該当しない:障害の程度が、障害年金の等級に該当するほど重くないと判断された場合
- 初診日が確認できない:診療録(カルテ)が保存期間を超えて廃棄されているなどの理由で、初診日を証明できない場合
- 保険料納付要件を満たしていない:初診日前の保険料納付状況が要件を満たしていない場合
- 書類の不備や内容の矛盾:提出書類に不備があったり、診断書と申立書の内容に矛盾がある場合
不支給決定通知書には、不支給となった理由が記載されています。この理由を確認することで、今後の対応を判断する材料となります。
再審査請求の方法と期限
不支給決定に納得がいかない場合は、「審査請求」および「再審査請求」という不服申立ての制度を利用することができます。
- 審査請求:不支給決定通知書が届いた日の翌日から3ヶ月以内に「審査請求書」を提出
- 再審査請求:審査請求の結果にも納得できない場合、決定を知った日の翌日から2ヶ月以内に「再審査請求書」を提出
不服申立てとは別に、「再請求」という方法もあります。これは不支給となった後に、新たに障害年金の請求を行うことです。不支給理由が明確で対応可能な場合や、症状が悪化した場合に適しています。
社会保険労務士への相談のメリット
障害年金の不支給決定に対応する場合、社会保険労務士に相談するメリットは大きいです。専門家のサポートを受けることで、以下のような支援が期待できます。
- 不支給理由の分析:専門的な知識をもとに対応策を提案
- 審査請求の代行:請求書の作成や必要書類の準備などを代行
- 証拠書類の収集・整理:障害の状態を適切に示す証拠書類の準備
- 医師との連携:診断書の内容について医師と相談するサポート
社会保険労務士に相談する際は、障害年金の専門性を持つ社労士を選ぶことが重要です。適切なサポートを得ることで、不支給からの逆転受給の可能性が高まります。
障害年金を受給するメリットと注意点
障害年金は、障害を持つ方の生活を経済的に支援するための重要な社会保障制度です。このセクションでは、受給することで得られるメリットと注意すべき点を解説します。
メリット①経済的な安定を得られる
障害年金の最大のメリットは、安定した収入源を確保できることです。障害によって就労が制限されても、定期的に年金が支給されることで経済的な基盤を維持できます。
障害の程度や加入していた年金制度によって金額は異なりますが、1級の障害基礎年金であれば年間約100万円、障害厚生年金ならさらに上乗せされた金額を受け取れます。子どもや配偶者がいる場合は加算もあるため、家族構成によっては生活の大きな支えとなります。
メリット②国民年金保険料が免除される
障害基礎年金の1級または2級を受給している方は、申請により国民年金保険料が免除される「法定免除」の対象となります。これにより、毎月の保険料(2025年度は月額17,000円程度)の支払いが不要になり、経済的な負担がさらに軽減されます。
メリット③他の支援制度も活用できる
障害年金を受給することで、さまざまな公的支援制度や優遇措置を併せて利用できるようになります。
- 医療費の助成:自立支援医療制度などによる負担軽減
- 税金の優遇:障害者控除や自動車税の減免
- 公共料金の割引:電気・ガス・水道料金などの割引
- 各種福祉サービス:障害の種類や程度に応じたサービス利用
注意点①定期的な更新が必要
多くの場合、定期的な更新手続きが必要です。更新時には現在の障害状態を証明する診断書の提出が求められ、状態の改善が認められると等級が下がったり、支給停止になったりする可能性があります。
注意点②収入制限がある場合も
特に20歳前の障害や20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限があり、前年の所得が一定額を超えると年金額が減額されたり、支給停止になることがあります。
注意点③扶養や税金への影響
障害年金の受給により、健康保険の被扶養者要件から外れる可能性があります。障害年金そのものは非課税ですが、就労収入と合わせた総収入により、各種減免制度が利用できなくなる場合もあるため注意が必要です。
障害年金と併用できるその他の支援制度
障害年金を受給している方は、その他の様々な支援制度も併せて利用することができます。これらの制度を適切に活用することで、経済的な負担の軽減や生活の質の向上につながります。
傷病手当金との関係性
傷病手当金は、会社員など健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガで働けなくなった場合に支給される制度です。
- 障害基礎年金:傷病手当金と同時に受給できます
- 障害厚生年金:傷病手当金の日額が厚生年金の日額より多い場合のみ、その差額が支給されます
労災保険との関係
労災保険は、仕事中や通勤途中の事故によるケガや病気に対する保険制度です。
- 障害基礎年金:労災保険の障害補償年金と同時に受給できます
- 障害厚生年金:労災保険と同時に受給できますが、一定の調整が行われます
生活保護との併給について
障害年金は生活保護の収入認定の対象となるため、障害年金分が生活保護費から差し引かれます。ただし、障害年金だけでは最低生活費に達しない場合、生活保護を併せて受給することで、最低生活が保障されます。
障害者手当や特別障害者手当との関係
これらの手当は障害年金と併給が可能です。主な手当には以下のようなものがあります:
- 特別障害者手当:重度の障害があり常時特別の介護を必要とする20歳以上の方
- 障害児福祉手当:重度の障害がある20歳未満の方
- 特別児童扶養手当:障害児を養育している父母等に支給
これらの手当には所得制限があるため、条件を確認した上で申請しましょう。
障害年金の相談窓口と専門家の活用法
障害年金の制度は複雑で申請手続きも煩雑なため、適切なサポートを受けることが重要です。このセクションでは、障害年金に関する相談窓口や専門家の活用方法について解説します。
年金事務所での相談方法
年金事務所は障害年金に関する公的な相談窓口です。無料で相談できますが、以下の点に注意しましょう。
- 予約制:混雑緩和のため、電話(「ねんきんダイヤル」0570-05-1165)で予約しておくと便利です
- 持参するもの:年金手帳や基礎年金番号通知書、身分証明書を持参しましょう
- 質問事項の整理:事前に質問をメモしておくと効率的です
社会保険労務士への相談のメリット
社会保険労務士(社労士)は年金の専門家として、以下のようなサポートを提供します。
- 専門的なアドバイス:個々の状況に合わせた申請戦略の提案
- 書類作成のサポート:病歴・就労状況等申立書の作成など
- 申請手続きの代行:書類提出などの手続き代行
- 不支給対応:不支給となった場合の審査請求や再請求のサポート
障害者支援団体の活用
各障害に関連する支援団体やNPO法人も障害年金の相談に対応していることがあります。当事者の視点からのアドバイスが得られ、無料または低額で相談できる場合が多いです。
就労支援サービスとの連携
就労支援サービスでも障害年金に関する情報提供を行っていることがあります。主なサービスとしては以下のようなものがあります。
- 障害者就業・生活支援センター:就業面と生活面の一体的な支援
- 就労移行支援事業所:一般企業への就職を目指す訓練
- ハローワーク(障害者専門窓口):障害者の就職サポート
よくある質問(Q&A)
障害年金について、皆さんからよく寄せられる質問にお答えします。
Q.精神障害や発達障害でも障害年金は受給できる?
はい、精神障害や発達障害でも障害年金を受給できます。うつ病や統合失調症などの精神疾患、自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害も対象です。日常生活や社会生活での制限の程度が重要な判断基準となります。
Q.いつまで遡って申請できる?
障害認定日請求の場合、時効により請求日から5年前までさかのぼって受給できます。事後重症請求の場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。
Q.海外在住でも受給できる?
日本国籍を持つ方は海外在住でも障害年金を受給できます。提出書類や手続きが異なるため、在外公館や日本年金機構に相談しましょう。
Q.障害年金はいつまで受給できる?
障害の状態が続く限り、原則として生涯にわたって受給できます。ただし、状態の改善や所得制限などにより支給停止となることもあります。
Q.年金額の改定はどのように行われる?
物価の変動や賃金の変動に応じて、年金額が改定されます。通常、毎年度ごとに改定率が決まり、4月分から新しい金額が適用されます。
まとめ:障害年金の理解を深めて適切な支援を受けよう
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限を受ける方を経済的に支援するための重要な社会保障制度です。制度を適切に活用することで、より安定した生活を送ることができます。
障害年金の申請は複雑ですが、初診日の確認、必要書類の準備、医師との連携など、ポイントを押さえることで受給の可能性が高まります。また、障害年金と併用できるその他の支援制度も積極的に活用しましょう。
不明点があれば、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。適切なサポートを受けながら、自分らしい生活を実現していきましょう。