公開日:2025.05.02
障害者手帳とは?種類や等級、申請方法からメリット・デメリットまで徹底解説
- ホーム
- コラム
- 「法律・制度」のコラム
- 障害者手帳とは?種類や等級、申請方法からメリット・デメリットまで徹底解説
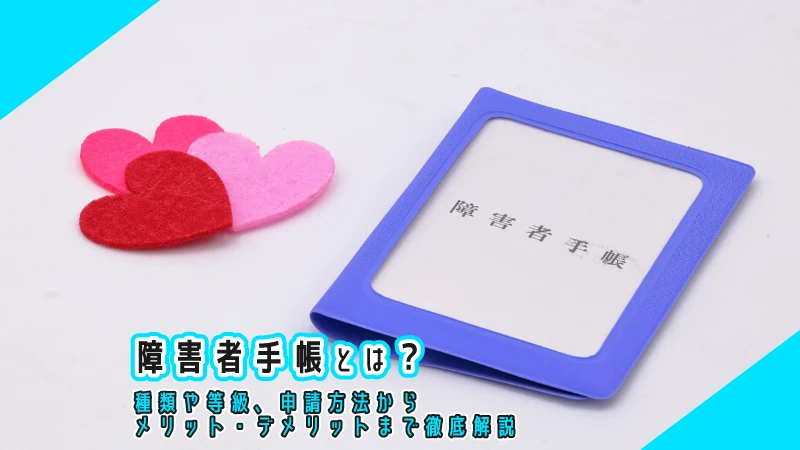
- このコラムのまとめ
- 障害者手帳の基本知識から申請方法、メリットまで徹底解説。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の種類や等級、取得方法、受けられる支援サービスを詳しく紹介。手帳がなくても利用できる支援制度も解説しています。障害のある方の生活をサポートする情報が満載です。
もくじ
もっと見る
障害者手帳とは?基本的な知識と役割
>「障害者手帳」という名前を聞くと、少し重たいイメージを持たれるかもしれません。しかし、これはあなたに障害があることを周囲に宣伝するためのものではなく、公的なサポートを受けるための「会員証」や「パスポート」のようなものです。
障害者手帳の定義と目的
日本には大きく分けて以下の3種類があり、これらをまとめて「障害者手帳」と呼んでいます。
- 体の不自由な方向けの「身体障害者手帳」
- うつ病や統合失調症などの方向けの「精神障害者保健福祉手帳」
- 知的障害のある方向けの「療育手帳」
手帳を持つ最大の目的は、あなたの生活を「楽にする」ことです。
障害によって生じるハンディキャップを、自分一人の努力で埋める必要はありません。手帳を取得することで、以下のような「社会の仕組み」を堂々と使えるようになります。
- 社会とつながる:交通費や施設利用料の割引を受け、外出のハードルを下げる
- 生活を守る:税金の控除などで、出ていくお金(生活コスト)を減らす
- 働き方を選ぶ:「障害者雇用枠」での就職が可能になり、無理のない働き方を探せる
3種類の手帳はそれぞれ異なる根拠法令に基づいて運用されています。身体障害者手帳は「身体障害者福祉法」、精神障害者保健福祉手帳は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づいています。一方、療育手帳は法律ではなく、厚生労働省の通知をもとに各自治体が運営する制度です。
障害者手帳の歴史と制度の変遷
今でこそ当たり前になった障害者手帳ですが、その歴史を紐解くと、障害の種類によって制度化された時期に大きな「ズレ」があることが分かります。
制度のスタートは戦後すぐの1949年(昭和24年)。当初は、戦争で傷ついた人や労働災害に遭った人を救済するという意味合いが強く、まずは「身体障害者手帳」から始まりました。
一方で、知的障害の方に向けた「療育手帳」が整備されたのは1973年。さらに「精神障害者保健福祉手帳」が誕生したのは、なんと1995年(平成7年)のことです。
実は、心の病気を持つ方への公的な手帳制度は、まだ30年ほどしか経っていない「非常に新しい制度」なのです。
精神障害者保健福祉手帳は比較的新しく、1995年(平成7年)に精神保健福祉法の改正によって創設されました。療育手帳は1973年(昭和48年)に厚生省(現・厚生労働省)の通知により制度化されました。知的障害者への支援を目的としており、地域によって「愛の手帳」「みどりの手帳」など様々な名称で呼ばれています。
近年では、2016年に「障害者差別解消法」が施行され、障害を理由とする差別の禁止や合理的配慮の提供が法的に義務付けられるなど、障害者を取り巻く法制度は大きく進展しています。また、2013年に施行された「障害者総合支援法」により、障害者手帳を持つ方々への包括的な支援体制が整備されました。
近年、法律の改正(2016年の障害者差別解消法など)が相次いでいますが、これは手帳の役割が「困っている人を保護する」という古い考え方から、「障害があってもなくても、同じように社会参加する権利(合理的配慮)を保障する」という新しい考え方へ、大きくシフトしたことを意味しています。
障害者手帳制度は時代とともに変化し、障害のある方々のニーズに合わせて拡充されてきました。現在では単なる障害の証明だけではなく、障害のある方々の社会参加と自立を促進するための重要なツールとして機能しています。
障害者手帳の種類と対象者
障害者手帳は「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。それぞれ対象となる障害の種類や条件が異なり、障害の特性に応じた支援を受けるための基盤となっています。ここでは各手帳の対象となる方について解説します。
身体障害者手帳の対象となる方
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて交付される手帳で、身体の機能に永続する障害がある方が対象です。対象となる障害は大きく分けて視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害の5つに分類されます。
視覚障害の基準
視覚障害は、両眼の視力や視野の状態によって等級が判定されます。視力は矯正視力(メガネやコンタクトレンズをつけた状態での視力)で測定され、両眼の視力の和や視野の状態によって等級が決定されます。
聴覚障害の基準
聴覚障害は、聴力レベルや平衡機能の障害によって等級が判定されます。聴力は聴力検査によって測定され、両耳の聴力レベルや聴こえる音の大きさによって等級が決定されます。
内部障害の基準
内部障害は、体の内部の機能障害を指し、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫系の機能障害が対象です。これらの臓器や機能の障害によって日常生活に支障がある状態が認定の対象となります。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる方
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象としています。統合失調症、気分障害、発達障害などの精神疾患が対象となり、初診から6ヶ月以上経過していることが申請条件となります。
統合失調症の方の場合
統合失調症は、思考や感情、行動などの精神機能に障害が生じる疾患です。幻覚や妄想、思考の混乱などの症状が特徴的です。統合失調症の方が精神障害者保健福祉手帳を取得する場合、症状の重さや日常生活への影響度によって等級が判定されます。
うつ病・双極性障害の方の場合
うつ病や双極性障害(躁うつ病)などの気分障害も精神障害者保健福祉手帳の対象となります。これらの疾患では、抑うつ状態や躁状態により日常生活や社会生活に支障をきたす状態が続くことがあります。
療育手帳の対象となる方
療育手帳は、知的障害のある方を対象とした手帳です。厚生労働省の通知に基づき各自治体が独自の基準で運用しているため、名称や判定基準は地域によって異なる場合があります。東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」などと呼ばれることもあります。
「IQ70」は絶対的なライン? 判定のリアル
一般的に「IQ(知能指数)が70未満」というのが知的障害の目安とされています。しかし、これは絶対的な壁ではありません。
実際の判定現場では、ペーパーテストの点数以上に、「社会生活能力(一人で生活できるか)」が重視されるからです。
- 数値よりも「困りごと」:IQが70を超えていても、金銭管理ができない、対人トラブルが絶えないといった「適応行動」に大きな課題があれば、対象となるケースがあります。
- 境界域(グレーゾーン)の悩み:逆に数値が境界線にある場合こそ、専門家の判断が分かれるため、自己判断せずに相談することが重要です。
障害者手帳の等級と認定基準
障害者手帳には障害の種類や程度に応じて等級が設定されています。この等級は障害の重さを示すとともに、受けられる支援やサービスの内容を決める重要な基準となります。各手帳の等級制度と認定基準について解説します。
身体障害者手帳の等級(1級〜6級)
身体障害者手帳の等級は1級から6級まであり、数字が小さいほど障害の程度が重いことを示します。等級は障害の部位や機能障害の程度によって判定され、身体障害者福祉法に基づく身体障害者障害程度等級表に詳細な基準が定められています。
| 等級 | 障害の程度 | 主な例 |
|---|---|---|
| 1級 | 最重度 | 両眼の視力の和が0.01以下、両上肢の機能を全廃したもの |
| 2級 | 重度 | 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下、両耳の聴力レベルが100デシベル以上 |
| 3級 | 中度〜重度 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下、一上肢の機能を全廃したもの |
| 4級 | 中度 | 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下、両耳の聴力レベルが80デシベル以上 |
身体障害者手帳では7級という区分も存在しますが、7級単独では手帳は交付されません。ただし、7級の障害と他の7級以上の障害が重複する場合は、その組み合わせにより6級以上として認定され、手帳が交付されることがあります。
精神障害者保健福祉手帳の等級(1級〜3級)
精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級までの3段階で、身体障害者手帳と同様に数字が小さいほど障害の程度が重いことを示します。精神疾患の種類や症状の程度、生活への影響などを総合的に評価して等級が判定されます。「実際にどのくらいのサポートが必要な状態か」という生活レベルで捉えると分かりやすくなります。
| 等級 | 生活の様子のイメージ |
|---|---|
| 1級 (重度) |
「常時の援助が必要」 自発的に起きたり食べたりすることが難しく、家族やヘルパーなどの付き添いがないと、安心した生活が送れない状態です。 |
| 2級 (中度) |
「必ずしも付き添いはいらないが、リスクがある」 一人で外出などはできますが、予想外のストレスや変化に弱く、日常生活を維持するために定期的な支援や見守りが必要です。 |
| 3級 (軽度) |
「一見普通に見えるが、配慮が必要」 家事や単調な仕事はできますが、対人関係や社会生活において強い負担を感じており、フルタイム勤務などが難しい状態です。 |
この手帳には「2年」という有効期限があります。「更新のたびに等級が変わる(良くなれば下がるし、悪化すれば上がる)」という点は、固定されがちな身体障害者手帳とは異なる特徴です。
療育手帳:「A」と「B」だけではない地域差
療育手帳(知的障害)の判定は、国の統一基準がないため、実はお住まいの自治体によって運用がバラバラです。
基本的には重いほうから「A(重度)」「B(中・軽度)」と分けられますが、地域によっては「A1・A2」「B1・B2」と細分化されていたり、数字で表されたりすることもあります。
療育手帳の等級判定では、知能指数(IQ)と社会生活能力(日常生活における適応状況)の両面から総合的に判断されます。一般的には以下のような基準が用いられますが、自治体によって多少の違いがあります。
- 判定のモノサシ:単純なIQ(知能指数)の数値だけで決まるわけではありません。「着替えができるか」「危険を回避できるか」といった社会生活能力(適応行動)も加味して、総合的に判定されます。
- A判定(重度)の目安:おおむねIQ35以下、または身体障害を併せ持っているなど、手厚い介護が必要な状態。
- B判定(中・軽度)の目安:おおむねIQ70〜75以下。日常会話はできても、複雑な契約や金銭管理には支援が必要な状態。
| 等級 | 知能指数(IQ)の目安 | 日常生活の状態 |
|---|---|---|
| A(重度) | 概ね35以下 | 常に介護が必要、または問題行動があるなど |
| B(中・軽度) | 概ね36〜70程度 | 一定の支援があれば日常生活が可能な状態 |
「手帳」と「年金」の等級は連動しない
障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の制度であり、それぞれ独自の基準で判定されます。障害者手帳は現在の障害の状態に基づいて判定されるのに対し、障害年金は「働けない」または「働きにくい」状態に対して支給されます。
>手帳は「生活のしづらさ(福祉が必要か)」を見るのに対し、年金は「働く能力がどれくらい落ちているか(稼げるか)」をシビアに見ます。そのため、手帳を持っていても年金が出ないことや、逆に手帳なしでも年金が出ることもあります。「別々の審査基準がある」と割り切って、個別に申請対策をすることが大切です
障害者手帳の申請方法と流れ
障害者手帳を取得するためには、それぞれの手帳の種類によって異なる申請手続きが必要です。ここでは各手帳の申請手順や必要書類について解説します。申請は基本的にお住まいの市区町村の障害福祉窓口で行います。
>手帳の種類で違う「申請ルート」と「ゴールまでの期間」
申請から交付までは、どの手帳もおおむね1〜2ヶ月(長いと3ヶ月)かかります。「今日出して、明日もらえる」ものではないため、就職活動などで使う予定がある方は、逆算して早めに動き出すのが鉄則です。
それぞれ「誰に診断してもらうか」が異なりますので、整理しておきましょう。
| 手帳の種類 | 申請のポイント |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 「指定医」の診断が必須 かかりつけ医なら誰でも良いわけではなく、知事が指定した医師(指定医)に診断書を書いてもらう必要があります。原則、更新はありません(※状態変化の可能性がある場合を除く)。 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 「2年ごとの更新」が必須 精神科医の診断書、または障害年金証書の写しで申請します。症状が変動しやすいため、2年ごとに必ず更新手続き(再判定)があるのが最大の特徴です。 |
| 療育手帳 | 「面談」がセットになる 医師の診断書だけでなく、児童相談所(または更生相談所)での面接・判定が必要です。地域によって、数年ごとの再判定が必要な場合があります。 |
障害者手帳を取得するメリット:手帳を持つことで得られる「3つの安心」
手帳取得を迷っている方の中には、「メリットがよく分からない」という方もいます。手帳は、あなたの生活を支えるための「実用的なツール」です。大きく分けて3つの側面から生活をバックアップしてくれます。
家計を守る「経済的な防波堤」
手帳を持つと、様々な場面で「出ていくお金」を減らすことができます。
- 税金が安くなる:所得税や住民税の控除、自動車税の減免など。
- 医療費の負担減:「自立支援医療」などを使えば、通院費の自己負担が1割で済みます。
- 手当や年金:条件を満たせば、障害者手当や年金の受給対象となり、収入面でも支えになります。
社会とつながるための「割引パスポート」
「外出するのが億劫だ」という気持ちを、割引サービスが後押ししてくれます。JRやバス、タクシーなどの運賃割引に加え、映画館や美術館、携帯電話料金の割引など、日常生活のあらゆる場面で優遇を受けられます。「割引があるなら、ちょっと出かけてみようかな」というきっかけ作りになります。
自分らしく働くための「武器」
就職活動において、手帳は強力な武器になります。「障害者雇用枠」での応募が可能になるため、倍率の高い一般枠で消耗することなく、最初から「配慮のある環境」を前提とした就職活動ができます。また、就職後も「合理的配慮」を堂々と求めるための根拠になります。
障害者手帳を取得する際のデメリットや懸念点
障害者手帳の取得には多くのメリットがありますが、一方で取得をためらう理由となる懸念点も存在します。ここでは、障害者手帳を取得する際に感じるかもしれない不安や心配について取り上げます。
プライバシーや周囲の目に関する懸念
障害者手帳を持つことで、自分の障害が周囲に知られてしまうのではないかという不安があります。しかし、障害者手帳の取得情報は厳重に管理されており、本人の同意なく第三者に開示されることはありません。手帳を提示するかどうかは基本的に本人の判断によるもので、必要な場面でのみ活用することができます。また、精神障害者保健福祉手帳は表面には「障害者手帳」としか記載されておらず、プライバシーに配慮されています。
就職・転職活動への影響
障害者手帳を取得することで、就職や転職に不利になるのではないかという懸念もあります。しかし、障害者手帳を持っていても一般枠で応募することは可能で、障害について開示するかどうかは本人の選択です。また、障害者雇用枠での就職には、障害特性に合わせた業務調整や配慮が受けられるというメリットもあります。近年は多様性を重視する企業も増えており、障害者雇用に対する理解も深まってきています。
「障害者」というレッテルをどう受け止めるか
手帳を取得する際、最も大きな壁になるのは手続きの手間ではなく、「自分は障害者なんだ」と認めなければならないような、心理的な痛みかもしれません。
もし迷いがあるなら、少し視点を変えてみましょう。
障害とは、あなた個人の欠陥ではありません。「あなたの特性」と「社会の環境」が、たまたま噛み合っていない状態(ミスマッチ)を指す言葉にすぎません。
手帳は、そのズレを調整するための「道具」です。眼鏡や松葉杖と同じように、生活をスムーズにするための補助ツールとして、ドライに捉えてみてはいかがでしょうか。
取得したからといって、おでこにシールを貼られるわけではありません。誰にも言わず、机の奥にしまっておいてもいい。
あくまで「選択肢の一つ」として、あなたが主導権を持って決めていいのです。
障害者手帳がなくても利用できる支援制度
「障害者手帳がないと、何もサポートしてもらえない」と思い込んでいませんか?
実は、手帳はあくまでパスポートの一つにすぎません。手帳がまだ手元にない段階でも、あるいは取得しないという選択をした場合でも、「医師の診断書」さえあれば利用できるセーフティネットは意外と多いのです。
相談できる窓口やサポート機関
「自分がどの制度を使えるか分からない」という場合は、手帳の有無に関わらず、以下の窓口で相談に乗ってもらえます。まずは電話で「困りごとの内容」を伝えるだけでOKです。
| 悩み | おすすめの窓口 |
|---|---|
| 生活全般・制度 | 基幹相談支援センター 地域の相談窓口のまとめ役。「どこに相談すればいいか分からない」時はココ。 |
| メンタルヘルス | 精神保健福祉センター・保健所 心の健康相談だけでなく、家族からの相談も受け付けています。 |
| 発達の悩み | 発達障害者支援センター 「診断はついていないけれど、生きづらい」という段階から相談可能です。 |
「診断書」で動ける就労支援<
就労に関しても、診断書があれば利用できる支援があります。ハローワークの「障害者向け専門窓口」では、診断書があれば相談できる場合があります。障害者トライアル雇用やジョブコーチ支援も、条件を満たせば診断書のみで利用できることがあります。また、うつ病などで休職中の方向けのリワーク支援や、若者サポートステーションなども障害の有無にかかわらず利用できます。
- リワーク支援:うつ病などで休職中の方が、復職を目指すためのプログラム。手帳なしで利用できる施設が多いです。
- 若者サポートステーション:働くことに悩みを持つ若者(~49歳)なら、障害の有無に関わらず利用できます。
- ジョブコーチ支援:条件次第ですが、診断書があれば専門家のサポートを受けられる可能性があります。
お金と医療の支援は「別ルート」
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患で通院している方であれば障害者手帳がなくても申請できます。また、障害年金も障害者手帳がなくても医師の診断書などに基づいて申請可能です。そのほか、日常生活自立支援事業や各種生活相談など、障害の状態によっては手帳がなくても利用できるサービスもあります。
障害者手帳の取得を検討している段階でも、これらの支援制度を活用することで生活の質を向上させることができます。
まとめ:「障害者」という枠ではなく、「権利」として使い倒す
障害者手帳は、持っているだけで自動的に生活が良くなる魔法のアイテムではありません。自分から情報を掴みに行き、利用して初めて効果を発揮する「実用的なツール」です。
制度は複雑で、手帳・年金・医療助成など、パズルのように組み合わせて使う必要があります。
でも、それらを全て一人で勉強する必要はありません。分からないことは、役所の窓口や相談員に「私にはどんな支援が使えますか?」と丸投げしてしまってOKです。
手帳は、あなたが社会の中で自分らしく、胸を張って生きていくための「権利証」です。遠慮は無用です。
使えるサポートはすべて使い倒し、あなたの人生の可能性を広げるために役立ててください。





