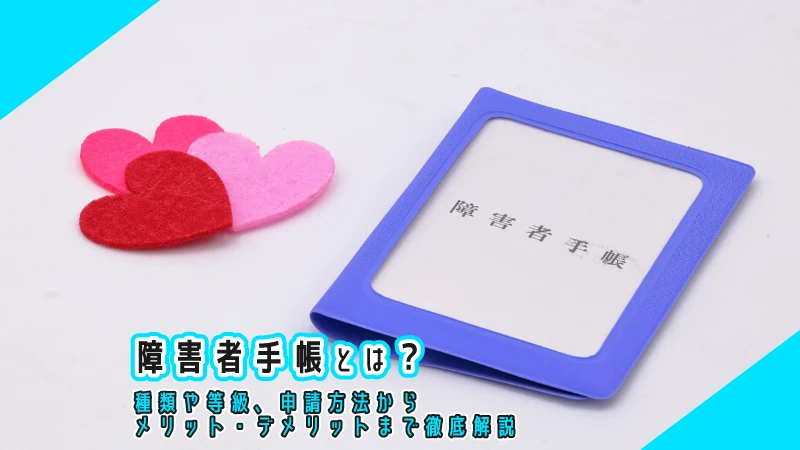- このコラムのまとめ
- 障害者雇用の基本知識から実践方法までを解説。制度の仕組みや法定雇用率、一般雇用との違い、メリット・デメリット、実例の紹介、そして企業が進めるためのステップまで網羅。障害のある方の就労支援制度や最新動向も取り上げ、多様な人材が活躍できる社会づくりに向けた障害者雇用の理解を深める内容です。
もくじ
もっと見る
障害者雇用とは?初めての方でもわかる基本知識
障害者雇用とは、障害のある人が一人ひとりの特性に合わせた働き方ができるように、企業や自治体などが設けている雇用制度です。障害のある方が安定して働き続けることを目的とし、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」によって定められています。
障害者雇用の定義とは
障害者雇用とは、心身に障害のある人が一般雇用とは別枠で企業や自治体などで働くことを指します。障害の内容や特性により、一般の方と同じ勤務条件で働くことが難しい場合があるため、障害のある人が働きやすい環境を整えた上で雇用する制度です。
障害者雇用では、採用の段階から障害について企業に伝えることで、入職後も特性に配慮した働き方ができる環境が整えられます。これにより、障害のある方も自分の能力を発揮して長く安定して働くことが可能になります。
障害者雇用の対象者について
障害者雇用の対象となるのは、原則として障害者手帳を持っている方です。障害者手帳には以下の3種類があります。
- 身体障害者手帳:身体の機能に一定以上の障害がある人に交付される手帳
- 療育手帳:知的障害の人に交付される手帳
- 精神障害者保健福祉手帳:精神障害の人に交付される手帳(発達障害のある人も含まれます)
障害者手帳を持っていれば、障害者雇用枠だけでなく一般雇用枠にも応募できます。自分の障害の種類や程度、希望する働き方に合わせて選択することが大切です。
障害者雇用促進法で定められた制度とは
障害者雇用促進法は、障害のある人の職業生活での自立と安定を実現するために、企業や行政機関に対して様々な義務や取り組みを定めた法律です。この法律の中心となる制度を紹介します。
障害者雇用率制度(法定雇用率)の概要
障害者雇用率制度とは、企業などに対して一定割合以上の障害者雇用を義務付ける制度です。この割合を「法定雇用率」と呼びます。2024年4月現在の法定雇用率は以下の通りです。
| 事業主区分 | 法定雇用率 |
|---|---|
| 民間企業 | 2.5% |
| 国・地方公共団体等 | 2.8% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% |
常用労働者が40人以上の企業は、障害者を1人以上雇用する義務があります。この法定雇用率は2026年7月には民間企業で2.7%に引き上げられる予定です。
障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成できていない企業から納付金を徴収し、達成している企業に調整金として分配する制度です。常用労働者が100人を超える企業が法定雇用率を達成できない場合、不足1人につき月額5万円の納付金を納める必要があります。
このほか、障害者雇用促進法では、職業リハビリテーションの推進や障害者に対する差別禁止、合理的配慮の提供義務なども定められています。合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に働くために必要な個別の調整や支援のことで、企業には提供義務があります。
障害者雇用は、法的義務というだけでなく、多様な人材が活躍できる職場づくりにつながる重要な取り組みです。障害のある方の雇用を通じて、企業文化や業務プロセスの見直しにもつながり、企業全体の成長に寄与します。
出典:
障害者雇用と一般雇用の違いとは
障害のある人の中には、障害のない人と同様の雇用条件である「一般雇用」で働いている人もいます。ここでは、障害者雇用と一般雇用の違いについて解説し、それぞれの特徴を比較します。
一般雇用での働き方と特徴
一般雇用とは、障害のあるなしにかかわらず、応募条件を満たしていれば誰でも応募することができる求人のことです。障害者手帳の有無に関わらず応募でき、求人の数や職種の選択肢も多いのが特徴です。
一般雇用の主な特徴は以下の通りです:
- 求人数の豊富さ:障害者雇用枠に比べて求人数が多く、幅広い職種から選べる
- 障害の開示・非開示の選択:障害があることをクローズ(非開示)にして働くことも、オープン(開示)にして働くこともできる
- 給与水準:一般的に障害者雇用よりも給与水準が高い傾向がある
- キャリアパス:昇進や異動など、キャリアアップの機会が多い場合が多い
一方で、一般雇用では障害への理解や配慮が職場で得られにくい可能性もあります。障害者職業総合センターのデータによると、一般雇用での就職後1年経過時点の職場定着率は、障害非開示の場合30.8%、障害開示の場合49.9%と、半数以上が離職している状況です。
出典:
障害者雇用での働き方と特徴
障害者雇用とは、障害者手帳を持っている人を対象とした採用枠で、法定雇用率を達成するために企業が設けている雇用形態です。「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかを持っている必要があります。
障害者雇用の主な特徴は以下の通りです:
- 障害への理解と配慮:入社時から障害について企業に伝えることで、職場環境や業務内容への配慮を受けやすい
- 勤務条件の調整:勤務時間や業務内容について、障害特性に合わせた調整が行われやすい
- 職場定着率の高さ:障害者雇用での就職後1年経過時点の職場定着率は70.4%と、一般雇用より高い
- 相談体制の充実:職場内の相談員や外部支援機関との連携など、サポート体制が整っていることが多い
一方、障害者雇用のデメリットとしては以下が挙げられます:
- 求人数の少なさ:一般雇用に比べて求人数が少なく、地域によっては選択肢が限られる
- 業務内容の制限:特定の業務に限定されることがある
- 給与水準:一般的に一般雇用よりも低い傾向がある
| 障害の種類 | 平均月額賃金(令和5年調査) |
|---|---|
| 身体障害者 | 約23万5,000円 |
| 知的障害者 | 約13万7,000円 |
| 精神障害者 | 約14万9,000円 |
| 一般雇用(参考) | 約31万8,300円 |
出典:
特例子会社での働き方という選択肢
特例子会社とは、障害のある人の雇用促進のために、親会社が設立した子会社のことです。障害者雇用率制度において、特例子会社で雇用されている障害者は親会社が雇用しているものとみなされます。
特例子会社での主な特徴は以下の通りです:
- 充実したサポート体制:障害特性に配慮した支援体制が整っていることが多い
- 雇用の安定性:親会社が大企業であることも多く、雇用が安定している傾向がある
- 障害特性に合わせた職場環境:バリアフリー環境や支援機器などが整備されていることが多い
- 仲間との協力:障害のある人同士で協力して働く環境があり、人間関係が築きやすい
特例子会社は全国で614社(令和6年6月時点)と数が限られており、地域によっては選択肢がない場合もあります。また、企業によって業務内容や待遇は大きく異なります。
一般雇用と障害者雇用、そして特例子会社という選択肢の中から、自分の障害特性や希望する働き方に合わせて選ぶことが大切です。障害者雇用では配慮が受けやすい反面、一般雇用よりも求人数や給与面で制限があることを理解し、自分に最適な働き方を選びましょう。
出典:
障害者雇用のメリットとデメリット
障害者雇用には、障害のある方本人と企業の双方にとって、さまざまなメリットとデメリットが存在します。ここでは、それぞれの立場から見た障害者雇用のメリットとデメリット、そして企業が直面する課題と解決策について解説します。
障害者本人にとってのメリット
障害者雇用で働くことは、障害のある方にとって多くのメリットがあります。自分の特性に合わせた環境で働くことで、長期的かつ安定した就労が可能になります。
主なメリットは以下の通りです:
- 障害への理解と配慮:職場に障害理解があり、特性や状況に合わせた配慮を受けやすい
- 職場定着率の高さ:障害者雇用での就職後1年経過時点の定着率は70.4%と高い
- 安定した働き方:障害特性に応じた業務内容や勤務時間の調整が可能
- キャリア形成のサポート:職場内外の支援を受けながら、スキルアップを目指せる
例えば、うつ病と自閉スペクトラム症のNさんは、職場の理解を得て自分用マニュアルを作成したり、聴覚過敏のために耳栓の使用を許可してもらったりと、落ち着いて仕事ができるように配慮を受けながら勤続6年目を迎えています。
障害者本人が感じる可能性のあるデメリット
一方で、障害者雇用には障害のある方本人にとってデメリットとなる可能性がある点も存在します。
主なデメリットとしては以下の点が挙げられます:
- 求人数の少なさ:一般雇用に比べて求人数が少なく、選択肢が限られる
- 業務内容の制限:特定の業務に限定されることが多い
- 給与水準の低さ:一般的に一般雇用よりも給与水準が低い傾向がある
- キャリアアップの機会制限:昇進やキャリアパスが限られる場合がある
これらのデメリットは企業や職場環境によって大きく異なります。応募前に企業の障害者雇用に対する姿勢や環境を確認することが重要です。
企業側から見た障害者雇用のメリット
障害者雇用は、法定雇用率の達成という法的義務だけでなく、企業にとっても多くのメリットをもたらします。
企業側のメリットとしては以下の点が挙げられます:
- 社会的責任(CSR)の実現:企業の社会的責任を果たし、企業イメージの向上につながる
- 多様性のある職場環境の構築:多様な人材が働くことで、互いを尊重する文化が醸成される
- 業務の効率化・最適化:業務の切り出しや環境整備により、全体の業務が見直され効率化される
- 税制優遇や助成金の活用:障害者雇用に関するさまざまな助成金や税制優遇を受けられる
例えば、業務を整理して障害のある人ができる仕事を切り出すことで、他の従業員がより高度な業務に集中でき、全体の生産性が向上するケースがあります。また、障害のある人の視点が加わることで、製品やサービスの改善につながることもあります。
企業側の課題と解決策
一方で、企業が障害者雇用を進める上では、いくつかの課題に直面することもあります。これらの課題を理解し、適切な解決策を実施することが重要です。
主な課題と解決策としては以下の点が挙げられます:
- 適切な業務の創出
課題:障害のある人に適した仕事がないと感じる企業が多い
解決策:業務の棚卸しと細分化、支援機関への相談
- 職場環境の整備
課題:施設・設備が対応していないことが障壁となる
解決策:バリアフリー化や支援機器の導入、助成金の活用
- 社内の理解促進
課題:障害に対する理解不足から受け入れに消極的になる
解決策:障害者雇用に関する研修の実施、全社的な理解促進
- 定着支援
課題:採用後の職場定着に課題を感じる企業が多い
解決策:定期面談や体調確認、コミュニケーション促進
これらの課題は一朝一夕に解決できるものではありませんが、社内の理解を深め、外部の支援機関と連携しながら少しずつ取り組むことが大切です。また、すでに障害者雇用に成功している企業の事例を参考にすることも有効です。
障害者雇用を義務や負担と捉えるのではなく、企業の成長や多様性推進のチャンスと捉え、前向きに取り組むことで、障害のある方と企業の双方にとって有意義な関係を築くことができるでしょう。
障害者雇用の実例と体験談
障害者雇用をより具体的に理解するために、実際に障害者雇用で働いている方々の体験談や事例を紹介します。さまざまな障害特性を持つ方々がどのように働き、どのような配慮を受けているのかを見ていきましょう。
精神障害のある方の就労事例
うつ病と自閉スペクトラム症を持つNさんは、福祉系の仕事を転々とした後、障害者雇用で事務職に就職しました。
職場での配慮:
- 業務のルーティン化:自分用のマニュアルを作成する時間を確保
- 感覚過敏への配慮:聴覚過敏のため、耳栓の使用を許可
- 定期的な面談:上司との面談時間を設け、困りごとを共有
「自分の特性を理解し、配慮してもらえる環境があることで、安心して働くことができています。現在は勤続6年目です」とNさんは話しています。
発達障害のある方の就労事例
複数の指示を受けると混乱してしまうBさんは、発達障害の診断後、障害者雇用で事務職に就職しました。
職場での配慮:
- 指示系統の一本化:指示を行う人を固定して、質問もその人に
- 業務の可視化:TODOリストを作成し、優先順位を明確化
- 作業環境の調整:集中しやすい静かな環境の確保
「今やるべきことが明確になり、ストレスなく業務を行えるようになりました。以前はミスが多くて自信をなくしていましたが、今は自分のペースで確実に仕事ができています」とBさんは語っています。
身体障害のある方の就労事例
車いすを使用するKさんは、リハビリを経て、障害者雇用で事務職として働いています。
職場での配慮:
- バリアフリー環境の整備:スロープや自動ドアの設置
- 作業環境の調整:デスクの高さを調整し、車いすでも作業しやすく
- 通勤時の配慮:フレックスタイム制導入で混雑時間を回避
「物理的な環境を整えてもらえたことで、自分の能力を発揮できる環境が整いました。特に通勤時の配慮は助かっています」とKさんは話しています。
これらの事例からわかるように、障害の種類や特性に合わせた適切な配慮を行うことで、障害のある方が自分の能力を発揮し、長く安定して働くことが可能になります。企業側も障害特性への理解を深め、必要な環境整備や支援を行うことで、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めることができるのです。
障害者雇用で働くための方法と支援制度
障害のある方が障害者雇用で働きたい場合、どのような方法で就職活動を進めればよいのでしょうか。ここでは、障害者雇用で働くための具体的な方法と、活用できる支援制度について解説します。
公共職業安定所(ハローワーク)の活用法
ハローワークは、障害のある方の就職をサポートする最も基本的な機関です。全国各地に設置されており、障害のある方専用の窓口も用意されています。
主なサービス内容:
- 専門的な職業相談:障害者職業相談員による、障害特性に応じた相談
- 求人情報の提供:障害者求人を中心とした情報提供
- 職業紹介:希望や能力に合った求人の紹介と応募サポート
- 職場適応指導:就職後の定着支援
ハローワークでは定期的に「障害者就職面接会」も開催されており、複数の企業と一度に面接できる機会もあります。利用は無料です。
地域障害者職業センターのサポート
地域障害者職業センターは、障害のある方の就職や職場適応を専門的に支援する機関で、全国47都道府県に設置されています。
主なサービス:
- 職業評価:作業検査や適性検査を通じた能力の把握
- 職業準備支援:就職に必要な基本的労働習慣の訓練
- ジョブコーチ支援:職場での適応に関する専門的支援
- リワーク支援:うつ病などによる休職からの復帰支援
特に「ジョブコーチ支援」は、職場での具体的な課題解決に効果的です。業務の進め方の工夫や環境調整など、障害特性に応じた細かな支援が受けられます。
就労移行支援事業所の利用方法
就労移行支援事業所は、一般企業への就職を希望する障害のある方に、就労に必要な訓練や就職後の支援を提供する施設です。
主なサービス:
- 職業訓練:パソコン操作やビジネスマナーなどの訓練
- 実習機会:協力企業での実践的な経験
- 就職活動支援:履歴書作成や面接対策
- 職場定着支援:就職後も継続的なサポート
利用には障害福祉サービス受給者証が必要で、最大2年間のサービスを受けられます。
障害者雇用専門の求人サイトの活用
近年はインターネット上にも障害者雇用に特化した求人サイトが多数あり、自宅から求人情報にアクセスできます。
主な求人サイト:
- 「障害者転職サポート」(パーソルチャレンジ)
- 「アットジーピー」(ゼネラルパートナーズ)
- 「LITALICO仕事ナビ」(LITALICOワークス)
- 「ハローワークインターネットサービス」(厚生労働省)
障害者雇用で働くための方法はさまざまですが、自分一人で就職活動を進めるよりも、上記のような支援機関やサービスを活用することで、より効果的に就職活動を進められます。自分の障害特性や希望に合った支援を選びながら、就職を目指しましょう。
企業が障害者雇用を進めるためのステップ
企業が障害者雇用を効果的に進めるためには、段階的にアプローチしていくことが重要です。ここでは、障害者雇用を始める前の準備段階から職場定着までの一連のステップを解説します。
社内理解の促進と受け入れ態勢の構築
障害者雇用を成功させるためには、会社全体で障害者雇用への理解を深め、受け入れる体制を整えることが第一歩です。
主な取り組み:
- 基本方針の策定:経営層が明確な方針を示し、全社で共有
- 障害理解研修の実施:障害の種類や特性、接し方についての理解促進
- 障害者職業生活相談員の選任:社内で障害のある社員をサポートする担当者の配置
- 外部支援機関との連携:ハローワークや地域障害者職業センターとの協力関係構築
業務の切り出しと職域開発
障害者雇用を進める上で重要なステップの一つが、障害のある人に適した業務の創出です。
業務切り出しのステップ:
- 業務棚卸し:各部署の業務を洗い出し、細分化
- 障害特性との適合検討:どのような障害特性と相性が良いかを検討
- 業務マニュアル作成:切り出した業務の手順を視覚的にわかりやすく整備
- 職場環境の整備:障害特性に配慮した物理的環境や支援ツールの準備
採用活動と面接のポイント
障害者雇用における採用活動は、一般の採用とは異なる配慮が必要です。
採用活動のポイント:
- 適切な求人情報発信:業務内容、勤務条件を明確に伝える
- 多様な採用チャネルの活用:ハローワーク、障害者就職面接会、支援機関を活用
- 障害特性に配慮した選考:面接方法や試験内容を柔軟に調整
- 職場実習の実施:可能であれば採用前に実習を行い、適性確認
職場定着に向けた取り組み
障害のある方を採用した後、長く安定して働いてもらうための取り組みが欠かせません。
定着支援の主な取り組み:
- 定期面談の実施:上司や相談員による定期的な面談で問題の早期発見
- 外部支援の活用:ジョブコーチ支援など専門的なサポートの利用
- 業務調整:障害特性や体調に合わせた柔軟な業務調整
- コミュニケーション支援:円滑な意思疎通のための工夫と配慮
障害者雇用は段階的に進めることが重要です。社内の理解促進から始め、適切な業務の切り出し、配慮ある採用活動、そして職場定着支援まで、計画的に取り組むことで、障害のある方と企業の双方にとって有意義な雇用を実現できます。
障害者雇用の最新動向と今後の展望
障害者雇用を取り巻く環境は、法制度の改正や働き方の多様化に伴い、常に変化しています。ここでは、最新の動向と今後の展望について解説します。
法定雇用率の変更と対象範囲の拡大
障害者雇用促進法に基づく法定雇用率は、定期的に見直しが行われています。2024年4月現在の法定雇用率と今後の予定は以下の通りです。
| 事業主区分 | 2024年4月現在 | 2026年7月以降 |
|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% | 2.7% |
| 国・地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
| 都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
この法定雇用率の引き上げにより、障害者雇用義務が発生する企業の範囲も拡大します。現在は常用労働者40人以上の企業に雇用義務がありますが、2026年7月からは37.5人以上の企業に拡大されます。
また、2024年4月からは週10時間以上20時間未満の短時間労働の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者も雇用率の算定対象(0.5人カウント)となりました。これにより、短時間からでも働きやすい環境が整備されています。
精神障害者雇用の促進政策
近年、特に注目されているのが精神障害者の雇用促進です。厚生労働省の「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、民間企業で雇用されている障害者のうち、精神障害者は約15万人で、前年比15.7%増と大きく増加しています。
主な政策としては、精神障害者雇用トータルサポーターの配置、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の実施、精神障害者等ステップアップ雇用奨励金の支給などがあります。また、週20時間以上30時間未満の短時間労働者を1カウントとする特例も当面の間延長されています。
出典:
テレワークなど多様な働き方の広がり
新型コロナウイルス感染症を契機に広がったテレワークは、障害者雇用にも大きな影響を与えています。
テレワークのメリット:
- 通勤負担の軽減:身体障害のある方や疲労が蓄積しやすい方に有効
- 自宅環境のカスタマイズ:障害特性に合わせた環境整備が可能
- 体調管理のしやすさ:体調の波がある方も柔軟に対応可能
- 地理的制約の解消:地方在住の障害者の就労機会拡大
一方で、コミュニケーション上の課題や孤立感、業務の切り分けなどの課題もあります。そのため、「ハイブリッド勤務」や「サテライトオフィス勤務」など、多様な勤務形態が模索されています。
また、ICT(情報通信技術)の発展により、音声認識技術や視線入力装置などの支援技術が進化し、これまで就労が難しかった重度の障害のある方の就労可能性も広がっています。
障害者雇用の制度や環境は今後も変化し続けるでしょう。多様な人材が活躍できる社会の実現に向けて、障害者雇用の取り組みはさらに進化していくことが期待されます。
まとめ:障害者雇用の理解を深め、共に働く社会へ
本記事では、障害者雇用の基本的な知識から実践的なノウハウまで解説してきました。障害者雇用は単なる法定雇用率達成のための手段ではなく、多様な人材が活躍できる社会を実現するための重要な取り組みです。
障害のある方は適切な配慮と環境があれば能力を発揮でき、企業側も多様性のある組織づくりや業務効率化などのメリットを得られます。障害者雇用を進める際は、社内理解の促進、適切な業務創出、採用活動の工夫、そして職場定着支援が重要です。
互いの違いを認め合い、支え合いながら共に働く社会の実現に向けて、障害者雇用への理解を深め、一人ひとりができることから取り組んでいきましょう。