公開日:2025.05.21
障害者が生活保護を利用するための完全ガイド:申請条件から併用できる制度まで
- ホーム
- コラム
- 「法律・制度」のコラム
- 障害者が生活保護を利用するための完全ガイド:申請条件から併用できる制度まで
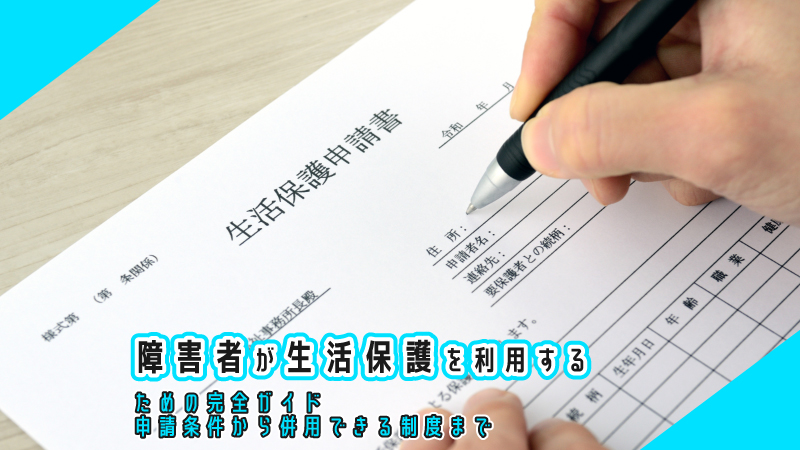
- このコラムのまとめ
- 生活保護制度は、障害者の最低限度の生活を保障する重要な支援策です。生活扶助や医療扶助、住宅扶助があり、障害者には特別な配慮があります。障害年金との併用や、就労支援施設を利用しながら生活保護を受けることができ、最終的には自立を目指す支援が行われます。生活保護を活用することで、安定した生活基盤が築けます。
もくじ
もっと見る
生活保護制度とは?障害者にとっての意義と基本原則
生活保護制度は、憲法第25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するための社会保障制度です。障害者にとって、この制度は経済的自立が難しい状況での生活を支える重要なセーフティネットとなります。
生活保護の基本的な仕組み
生活保護は、世帯の「最低生活費」と「収入」を比較し、収入が最低生活費に満たない場合にその差額を支給する制度です。
社会福祉士
障害者が生活保護を利用する際の基本的な考え方は以下の通りです。
- 障害に伴う生活上の困難に配慮した支援が受けられる
- 障害者手帳の有無にかかわらず、実際の生活困窮状態に応じて支給される
- 障害年金などの他の福祉制度と併用が可能
障害者にとっての生活保護の意義
障害者にとって生活保護制度は単なる金銭給付以上の意味を持ちます。
- 経済的自立の補完:障害により就労が制限される中でも最低限の生活が保障される
- 医療へのアクセス保障:医療扶助により医療費の心配なく必要な治療が受けられる
- 住居の確保:住宅扶助により安定した住居環境を維持できる
生活保護制度の8つの扶助
生活保護制度では、障害者の多様なニーズに対応するため、8種類の扶助が用意されています。
| 扶助の種類 | 内容 |
|---|---|
| 生活扶助 | 日常生活費(食費・被服費・光熱費等)、障害者加算あり |
| 住宅扶助 | 家賃、地代、住宅の修理費など |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 |
| 医療扶助 | 医療サービスの費用(障害関連の治療も対象) |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 |
| 出産扶助 | 出産費用 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能習得等の費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭費用 |
生活保護の4つの基本原理
障害者が生活保護を利用する際も、以下の基本原理が適用されます。
- 生存権の保障:健康で文化的な最低限度の生活が保障される
- 無差別平等:障害の有無や種類によって差別されない
- 健康で文化的な生活水準:単なる生存だけでなく社会的な生活の質も考慮
- 補足性の原理:資産や能力の活用、扶養義務者の扶養、他法他施策の活用が前提
福祉事務所ケースワーカー
障害者が受けられる生活保護の支給内容と金額
障害者が生活保護を受ける場合、障害の種類や程度に応じて様々な加算や配慮があります。このセクションでは具体的な支給内容と金額について解説します。
8種類の扶助と障害者加算について
生活保護では、必要に応じて8種類の扶助が組み合わせて支給されます。障害者の場合、特に重要なのが生活扶助における「障害者加算」です。
生活保護担当ケースワーカー
障害者加算の対象となるのは以下の条件に該当する方です。
- 障害等級表の1級か2級、または障害年金の1級に該当する方
- 障害等級表の3級、または障害年金の2級に該当する方
| 区分 | 1級・2級または障害年金1級 | 3級または障害年金2級 |
|---|---|---|
| 1級地(都市部) | 約26,810円 | 約17,870円 |
| 3級地(町村部) | 約23,060円 | 約15,380円 |
出典:
実際の受給額の目安
生活保護の支給額は、最低生活費から収入を引いた差額が支給されます。障害者の場合の最低生活費の目安は以下の通りです。
| 世帯構成 | 東京都区部 | 地方都市 |
|---|---|---|
| 障害者単身(30歳・障害等級2級) | 約13万円+家賃 | 約11万円+家賃 |
| 障害者を含む2人世帯 | 約20万円+家賃 | 約16万円+家賃 |
医療扶助と障害者の医療費
障害者にとって特に重要なのが医療扶助です。生活保護を受けている障害者は、医療機関での自己負担なく医療を受けることができます。
- 通院・入院費用が全額カバーされる
- 処方薬の費用負担がない
- リハビリテーションなどの治療も対象
住宅扶助と障害者向け配慮
障害者が生活保護を受ける場合、住宅扶助にも特別な配慮があります。
- バリアフリー住宅の場合、通常より高い家賃上限が認められることがある
- 車いす使用者など特別な住環境が必要な場合、個別に家賃上限を検討
障害者支援専門家
障害年金と生活保護の併用について
障害のある方の生活を支える制度として、障害年金と生活保護はどちらも重要です。両制度は併用できますが、いくつかの注意点があります。このセクションでは、障害年金と生活保護を効果的に組み合わせる方法を解説します。
障害年金を受給している場合の生活保護との関係
障害年金を受給している方も、その金額だけでは最低生活費に満たない場合、生活保護を申請することができます。生活保護制度では「他法他施策優先の原則」により、まず障害年金などの社会保障制度を活用した上で、それでも足りない分を生活保護で補うという考え方になっています。
社会福祉士
併用時の計算方法
障害年金と生活保護を併用する場合、生活保護費の計算は以下の式に基づいて行われます。
生活保護費 = 最低生活費 - (障害年金 + その他の収入)
| 例:30歳単身・東京都在住・障害年金2級(月額約6.5万円)の場合 |
|---|
|
最低生活費:約13万円(生活扶助約8万円+住宅扶助約5万円) 障害年金:約6.5万円 生活保護費:約6.5万円(13万円-6.5万円) |
障害基礎年金・障害厚生年金それぞれのケース
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、それぞれ生活保護との関係が少し異なります。
- 障害基礎年金のみの場合:多くのケースで金額が最低生活費を下回るため、不足分を生活保護で補うことになります。
- 障害厚生年金を受給している場合:報酬比例部分があるため、過去の給与が高かった方は金額が大きくなります。金額によっては最低生活費を上回り、生活保護を受給できない場合もあります。
障害年金の遡及払いがあった場合
障害年金は申請から受給までに時間がかかることがあり、認定されると申請時にさかのぼって支給されることがあります(遡及払い)。生活保護を受給中に障害年金の遡及払いがあった場合、生活保護を受給していた期間に対応する遡及払い分は、原則として返還の対象となります。
障害者就労支援員
就労支援施設(A型・B型・就労移行支援)と生活保護の関係
障害者の就労と自立を支援する就労支援施設と生活保護制度の関係は、多くの障害者にとって重要な関心事です。この二つの制度をどのように組み合わせられるのか、就労形態ごとに詳しく解説します。
A型事業所で働く場合の生活保護への影響
就労継続支援A型事業所は、障害者と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われる就労形態です。A型事業所で働く場合の生活保護への影響は以下の通りです。
- 雇用契約に基づく就労のため、安定した就労とみなされる可能性が高い
- 最低賃金以上の収入があるため、収入認定額が大きくなる
- フルタイム勤務の場合、生活保護が打ち切られる可能性がある
就労支援コーディネーター
B型事業所の工賃と生活保護の調整
就労継続支援B型事業所は、雇用契約を結ばず、作業量や作業内容に応じて工賃が支払われる福祉的就労の場です。B型事業所の工賃と生活保護の関係について重要なポイントは以下の通りです。
- B型事業所での工賃は収入として認定されるが、月額15,000円以下であれば全額控除の対象となる場合がある
- 15,000円を超える場合は、超過分が収入認定される
- B型事業所の通所により生活保護が打ち切られることは基本的にない
就労移行支援を利用しながら生活保護を受ける方法
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す障害者に対して、就労に必要なスキルの習得や就職活動のサポートを行う福祉サービスです。利用期間は原則2年間で、その間に就職を目指します。
| 就労形態 | 収入の特徴 | 生活保護との調整 |
|---|---|---|
| A型事業所 | 最低賃金以上の給与 (月8〜12万円程度) |
収入が多いため減額幅大きい |
| B型事業所 | 工賃 (月1〜3万円程度) |
15,000円以下なら全額控除 |
| 就労移行支援 | 訓練期間中は収入なし | 訓練中は生活保護に影響なし |
就労移行支援事業所スタッフ
障害者が生活保護から自立するためのステップ

生活保護は、困窮状態にある障害者の生活を支える重要なセーフティネットですが、可能であれば自立を目指すことも大切です。ここでは、障害者が生活保護から段階的に自立していくための現実的なステップを解説します。
障害福祉サービスの活用方法
障害者が生活保護から自立するためには、障害者総合支援法に基づく様々な障害福祉サービスを効果的に活用することが鍵となります。
相談支援専門員
障害福祉サービスの中でも、特に自立に向けて効果的なサービスには以下のようなものがあります。
- 相談支援:サービス等利用計画の作成と定期的なモニタリング
- 就労移行支援:一般就労に向けた訓練と職場定着支援
- 就労定着支援:就職後の職場定着をサポート
- 居宅介護:自宅での生活をサポート
就労支援プログラムへの参加
障害者が就労を通じて自立を目指す場合、様々な就労支援プログラムを活用することで、段階的に就労能力を高めていくことができます。
- ハローワークの専門支援窓口:障害者向け求人情報の提供や職業相談
- 障害者就業・生活支援センター:就業面と生活面の一体的な支援
- 地域障害者職業センター:職業評価や職業準備支援、ジョブコーチ支援
自立に向けた計画と支援体制
障害者が生活保護から自立するためには、明確な目標設定と段階的な計画が重要です。また、その計画を支える支援体制も欠かせません。
| 支援者・サービス | 役割 |
|---|---|
| ケースワーカー | 生活保護制度に関する支援 |
| 相談支援専門員 | 障害福祉サービスの調整 |
| 就労支援員 | 就労に関する支援 |
| 医療関係者 | 健康管理と医療的サポート |
就労と収入増加に伴う生活保護からの卒業プロセス
障害者が就労によって収入を増やし、生活保護から卒業するプロセスは、一般的に以下のようなステップで進みます。
- 就労準備期:障害福祉サービスを利用した基礎的な就労スキルの習得
- 就労開始期:短時間勤務からスタートし、勤労控除を活用
- 収入増加期:勤務時間や業務範囲の拡大による収入増加
- 自立移行期:収入が最低生活費に近づき、生活保護からの卒業準備
- 自立生活期:生活保護から完全に卒業し、安定した就労と生活の維持
障害者就労支援機関スタッフ
障害者が生活保護を受けるための申請条件と対象者
障害者が生活保護を申請する際には、一般的な生活保護の条件に加えて、障害特性に応じた判断が行われます。このセクションでは、障害者が生活保護を受けるための具体的な申請条件と対象者について詳しく解説します。
障害があっても資産・能力の活用が求められる
生活保護制度は「補足性の原理」に基づいており、障害者であっても基本的には自分の資産や能力を活用することが前提となります。ただし、障害の特性や程度に応じた合理的な配慮がなされます。
福祉事務所職員
障害者が保有できる可能性のある資産の例
- 障害者が通院・通所に使用する自動車
- 障害に対応した住宅
- 障害に必要な福祉用具・補装具
扶養照会について知っておくべきこと
生活保護の申請時には、原則として扶養義務者(親、子、きょうだいなど)への扶養照会が行われます。しかし、障害者の場合、特に配慮が必要なケースがあります。
扶養照会が緩和されるケース
- DV・虐待などの事情がある場合
- 扶養義務者が生活保護を受給している場合
- 長期間(10年程度)音信不通の場合
- 扶養義務者が高齢(70歳以上)の場合
世帯分離の可能性と方法
生活保護は原則として世帯単位で適用されますが、障害者がいる世帯では「世帯分離」が認められる場合があります。
| 世帯分離が認められる主なケース | 内容 |
|---|---|
| 障害者と介護する親の同居 | 親の収入が一定以上あるが、障害者本人に収入がない場合 |
| 障害者が就労している世帯員と同居 | 障害者本人は就労が困難だが、同居家族は就労している場合 |
| 施設等に入所している障害者 | 障害者支援施設やグループホームに入所している場合 |
障害者支援相談員
障害者が生活保護を申請する際の流れと必要書類
障害のある方が生活保護を申請する際には、一般的な申請手続きに加えて、障害の状況に応じた準備や配慮が必要となります。このセクションでは、スムーズな申請のための具体的な流れと必要書類について解説します。
申請前の相談ステップ
生活保護の申請を検討している障害者の方は、まず申請前の相談から始めることをお勧めします。この段階で適切な準備をすることで、申請手続きがスムーズに進みます。
福祉事務所職員
申請前の相談ステップは以下の通りです。
- お住まいの地域を管轄する福祉事務所を確認する
- 福祉事務所の生活保護担当に電話で状況を簡単に説明
- 相談支援専門員やケースワーカーなどに同行を依頼
- 必要書類の事前準備
必要書類の準備と申請手続き
申請に必要な基本的な書類は以下の通りです。
| 書類の種類 | 内容・取得方法 |
|---|---|
| 生活保護申請書 | 福祉事務所で入手・記入 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 収入関係書類 | 給与明細、年金証書、各種手当の証明書など |
| 資産関係書類 | 預貯金通帳、保険証券など |
障害者が特に準備すべき書類
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 障害年金関係書類(年金証書、振込通知書など)
- 医師の診断書(障害の状況や就労困難を示すもの)
- 自立支援医療受給者証(持っている場合)
支援者・専門家に同席してもらうメリット
障害のある方が生活保護を申請する際、支援者や専門家に同席してもらうことで、様々なメリットがあります。特にコミュニケーションの補助や、障害の状況を客観的に説明してもらえる点が大きな利点です。同席を依頼できる人としては、相談支援専門員、医療ソーシャルワーカー、障害者支援団体のスタッフなどがあります。
障害者特有の「水際作戦」対策と権利擁護
生活保護の申請段階で不当に申請を阻止されてしまう「水際作戦」は、特に障害のある方に対して行われやすいことが指摘されています。このセクションでは、障害者特有の水際作戦の実態と、それに対抗するための具体的な方法について解説します。
申請を断られたときの対処法
生活保護の申請は、憲法第25条で保障された権利に基づくものです。しかし、実際の窓口では様々な理由をつけて申請自体を受け付けないケースが報告されています。
生活保護申請支援弁護士
障害者によく見られる水際作戦の例と対処法
| よくある水際作戦の例 | 効果的な対処法 |
|---|---|
| 「障害者手帳がないと申請できない」 | 「手帳の有無にかかわらず、生活に困窮していれば申請できる権利があります」と伝える |
| 「障害年金を先に申請してからにしてください」 | 「他の制度の申請と並行して生活保護の申請をすることは可能です」と伝える |
| 「車を持っている人は申請できません」 | 「障害のため通院や日常生活に車が必要です」と伝える |
障害特性に配慮した面談の依頼方法
生活保護の申請時や申請後の面談では、障害特性に応じた配慮を求めることが重要です。適切な配慮があれば、コミュニケーションの障壁が減り、正確な情報伝達が可能になります。
- 静かな部屋での面談
- 支援者の同席
- 面談時間の短縮や分割
- 視覚的な資料や説明の提供
相談・支援機関の活用法
生活保護の申請や受給に関して困ったときは、様々な相談・支援機関を活用することができます。特に障害のある方は、障害福祉と生活保護の両面からサポートを受けられる機関を知っておくことが重要です。
- 無料の法律相談:法テラス、弁護士会の無料法律相談など
- 障害者支援機関:基幹相談支援センター、障害者生活支援センターなど
- 権利擁護機関:地域の権利擁護センター、障害者110番など
生活保護を受給中の障害者の権利と義務
生活保護を受給している障害者の方は、一般的な受給者としての権利と義務に加えて、障害特性に応じた配慮や特別なルールが適用される場合があります。このセクションでは、スムーズな受給生活を送るために知っておくべき権利と義務について解説します。
定期的な収入申告と生活状況報告
生活保護を受給している方には、定期的に収入状況や生活状況を報告する義務があります。障害のある方にとって、この手続きは負担になる場合もありますが、適切に対応するためのポイントを押さえておきましょう。
生活保護担当ケースワーカー
申告・報告を適切に行うためのポイント
- 障害特性に応じた申告方法の相談(口頭での報告など)
- リマインドシステムの活用(スマートフォンのリマインダー機能など)
- 収入証明書類の保管システムの確立
医療扶助の利用方法と注意点
医療扶助は、障害のある方にとって特に重要な扶助の一つです。適切に医療サービスを受けるための利用方法と注意点を理解しておきましょう。
- 医療券・調剤券の受け取りと管理
- 医療機関での受診方法(受診時に医療券を窓口に提示)
- 自立支援医療との併用方法の確認
就労や障害福祉サービス利用時の報告義務
生活保護受給中に就労を始めたり、障害福祉サービスを利用したりする場合には、適切な報告が必要です。特に障害のある方は、就労条件や福祉サービスの利用状況に配慮した対応が求められます。
| 報告が必要な事項 | 報告のタイミング |
|---|---|
| 就労開始・収入の変化 | 就労開始前の相談と開始後の速やかな報告 |
| 障害福祉サービスの利用 | 利用開始前の事前相談と開始後の報告 |
| 入院・施設入所 | 入院・入所前または直後の速やかな報告 |
まとめ:障害者が安心して生活保護を利用するためのポイント
障害のある方が生活保護を利用する際のポイントを総括します。生活保護は「恥ずかしいもの」ではなく、憲法で保障された権利です。特に障害がある方にとっては、必要な医療や生活基盤を確保し、自立への道筋をつけるための重要な制度です。
障害者支援専門家
申請の際は支援者や専門家の同席を依頼し、障害特性に応じた配慮を求めることで、スムーズな手続きが可能になります。また、障害福祉サービスと生活保護を併用することで、より充実した支援を受けられます。






