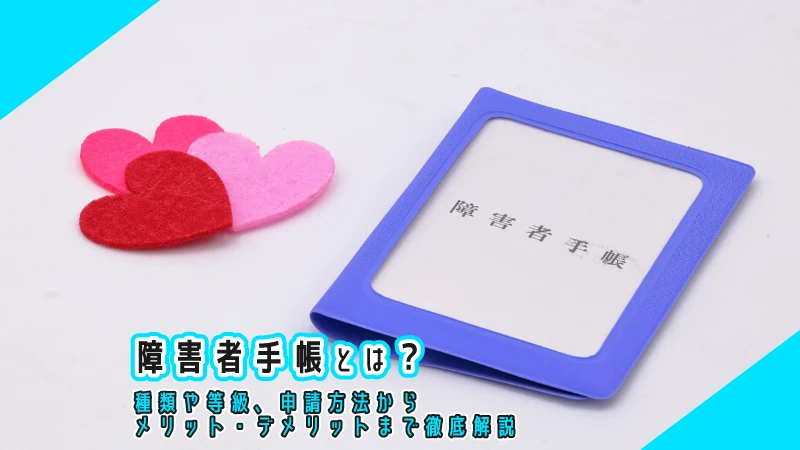- このコラムのまとめ
- 身体障害者手帳は障害のある方が様々な支援サービスを受けるための証明書です。この記事では、手帳の基本知識から申請方法、等級制度、受けられるメリットやサービス、更新・再認定の情報まで徹底解説。障害のある方の生活をサポートする重要なツールとして、手帳の有効活用方法を紹介しています。
もくじ
もっと見る
身体障害者手帳の基本知識
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が様々な福祉サービスを受けるために必要な「証明書」です。この手帳を取得することで、医療費の助成や税金の軽減、公共料金の割引など、生活の質を向上させるための支援を受けることができます。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、都道府県知事、政令指定都市の市長、中核市の市長などが身体に障害のある方に交付する公的な証明書です。この手帳は「身体障害者福祉法」に基づき、障害のある方の自立と社会参加を促進することを目的としています。
福祉相談員
対象となる障害の種類
身体障害者手帳の交付対象となる障害には、以下のような種類があります。
- 視覚障害
- 聴覚または平衡機能の障害
- 音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害)
ただし、障害の程度によって交付の対象外となる場合もあります。身体障害者手帳は、障害が永続することを前提とした制度です。そのため、一時的な障害や回復が見込まれる状態では認定されないことがあります。
手帳取得の重要性
身体障害者手帳を取得することには、以下のような重要性があります。
- 様々な福祉サービスを受けるための「パスポート」として機能する
- 障害者雇用枠での就職や転職活動が可能になる
- 経済的負担を軽減するための各種割引や控除を受けられる
障害があると医療費がかかるだけでなく、生活面でも様々な費用がかさむことがあります。身体障害者手帳は、そうした経済的な負担を感じている方にとって、利用価値の高い手帳といえるでしょう。
就労支援専門家
手帳の取得は任意ですので、必要だと感じたときに申請を検討すればよいでしょう。また、取得しても利用するかどうかは個人の自由です。まずは自分にとってどのようなメリットがあるのか、理解することが大切です。
身体障害者手帳取得の5つのメリット
身体障害者手帳を取得することで、日常生活や社会参加をサポートするさまざまな支援やサービスを受けることができます。ここでは、特に重要な5つのメリットについて説明します。
1.医療費、補装具、リフォーム費用の助成
身体障害のある方にとって、医療費の助成は大きなメリットです。国の公費負担医療制度である自立支援医療(更生医療)を利用すると、障害の軽減や進行予防に効果のある治療を受けた場合、医療費の自己負担が原則1割で済みます。
また、補装具(車いす、補聴器、義肢など)の購入・修理費用の助成や、住宅のバリアフリー化のためのリフォーム費用の助成も受けられます。これらは障害の種類や等級によって内容が異なります。
2.所得税・住民税・自動車税などの軽減
身体障害者手帳があると、税金の控除や減免を受けることができます。所得税・住民税では「障害者控除」が適用され、障害の程度により控除額が異なります。
税理士
3.さまざまな公共料金の割引サービス
身体障害者手帳を提示することで、多くの公共料金や施設利用料の割引を受けることができます。JRや私鉄、バスなどの交通機関では運賃が半額になることが多く、介護者も割引対象になる場合があります。
その他、NHK放送受信料の減免、携帯電話料金の割引、公共施設(美術館、博物館など)の入場料割引なども利用できます。
4.障害者雇用での就職・転職活動ができる
企業は一定数の障害者を雇用する法的義務があります。身体障害者手帳を持っていると、障害者雇用枠での就職活動が可能になり、就職の選択肢が広がります。
- 一般採用に加え、障害者雇用枠での応募ができる
- 職場での合理的配慮を受けやすくなる
- 障害者就労支援サービスが利用できる
5.公営住宅の優先入居や住宅設備改善の支援
身体障害者手帳を持っていると、公営住宅への入居申し込みの際に優遇措置を受けられることがあります。また、住宅のバリアフリー化などの改修費用の助成も受けられます。
住環境の改善は、自立した生活を送るための重要な要素です。手すりの設置や段差の解消、トイレや浴室の改修など、障害の状況に合わせた住環境整備の支援を受けることができます。
これらの5つのメリットは、身体障害者手帳を取得することで得られる主な利点です。ただし、サービスの内容や条件は地域や障害の等級によって異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体の障害福祉課などにお問い合わせください。
身体障害者手帳で受けられる具体的なサービス一覧

身体障害者手帳を取得すると、様々な公的サービスや民間企業の割引制度を利用することができます。ここでは、障害の種類や等級によって受けられる具体的なサービスを分野別に紹介します。
医療・福祉サービス
身体障害者手帳を持っていると、医療費の負担軽減や福祉用具の支給など、医療や福祉に関する様々なサポートを受けることができます。
- 自立支援医療(更生医療):医療費の自己負担が原則1割に
- 補装具費支給:義肢、車いす、補聴器などの購入・修理費の補助
- 日常生活用具給付:特殊寝台、入浴補助用具などの給付
- ホームヘルプ、ショートステイなどの障害福祉サービス
税金・公共料金の軽減
経済的な負担を軽減するため、税金や公共料金に関する様々な優遇措置があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 障害者控除、特別障害者控除の適用 |
| 自動車関連税 | 自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免 |
| NHK放送受信料 | 全額免除または半額免除 |
| 携帯電話料金 | 基本使用料等の割引 |
交通機関の運賃割引
身体障害者手帳を提示することで、様々な交通機関の運賃が割引になります。
交通アドバイザー
また、タクシーの割引(1〜2割)や航空運賃の障害者割引も利用できます。
公共施設・民間施設の利用料割引
多くの公共施設や民間施設では、身体障害者手帳を提示することで入場料や利用料の割引が受けられます。
- 博物館、美術館、動物園:入場料無料または割引
- 映画館、テーマパーク:割引料金の適用
就労支援サービス
身体障害者手帳を持っていると、就労に関する様々な支援サービスを利用することができます。
- ハローワークの専門窓口での職業相談・紹介
- 障害者就業・生活支援センターでの総合的支援
- 就労移行支援、就労継続支援などの障害福祉サービス
身体障害者手帳で受けられるサービスは非常に多岐にわたります。自分の障害の種類や等級、生活状況に合わせて、必要なサービスを選んで活用することが大切です。手帳を取得したら、まずはお住まいの地域の障害福祉窓口で受けられるサービスの詳細を確認してみましょう。
身体障害者手帳の申請方法と流れ
身体障害者手帳を取得するためには、一定の手続きが必要となります。ここでは、申請から交付までの流れや必要書類、申請時の注意点について解説します。
申請に必要な書類の準備
身体障害者手帳の申請には、以下の書類が必要です。事前に準備しておくとスムーズに手続きが進められます。
| 必要書類 | 説明 |
|---|---|
| 交付申請書 | 市区町村の障害福祉窓口で入手できます |
| 身体障害者診断書・意見書 | 指定医師が作成したもの(発行から原則3ヶ月以内のもの) |
| 写真 | 縦4cm×横3cmの顔写真(脱帽・上半身) |
| 印鑑 | 認印で構いません |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードや運転免許証など |
指定医師による診断書の取得
身体障害者診断書・意見書は、「指定医」が作成する必要があります。かかりつけ医が指定医でない場合は、指定医の紹介を受けるか、障害福祉窓口で紹介してもらいましょう。診断書作成には料金がかかります(5,000円〜10,000円程度)。
福祉窓口担当者
申請から交付までの流れ
- 必要書類を住んでいる市区町村の障害福祉窓口に提出
- 自治体から都道府県の審査会へ書類が送られ、障害等級の判定が行われる
- 審査結果に基づき障害等級が決定される
- 手帳の交付決定通知が届く
- 市区町村の窓口で身体障害者手帳を受け取る
申請から交付までにかかる期間は、自治体や審査の状況によって異なりますが、一般的には1ヶ月〜3ヶ月程度です。
申請時の注意点
身体障害者手帳の申請をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。
- 診断書は最新の状態を反映したものを用意する
- 申請前に自治体のウェブサイトや窓口で必要書類や手続きを確認する
- 障害が永続することを前提とした制度のため、一時的な障害は対象外
- 15歳未満の子どもの場合は、保護者が申請手続きを行う
身体障害者手帳の申請手続きは少し複雑に感じるかもしれませんが、一度取得すれば様々な支援やサービスを受けることができます。わからないことがあれば、お住まいの自治体の障害福祉窓口に気軽に相談してみてください。
身体障害者手帳の等級制度
身体障害者手帳の等級は、障害の種類や程度によって1級から6級まで分けられており、1級が最も重度、6級が最も軽度とされています。この等級によって、受けられる福祉サービスや税控除などの内容が異なります。
1級から6級までの障害等級の詳細
身体障害者手帳の等級は、障害の種類と程度により6段階に区分されています。等級が上位(数字が小さい)になるほど、障害の程度が重く、受けられるサービスも手厚くなります。
| 等級 | 障害の程度 | 基本的な考え方 |
|---|---|---|
| 1級 | 極めて重度 | 日常生活に常時介護が必要な状態 |
| 2級 | 重度 | 日常生活に著しい制限を受ける状態 |
| 3〜4級 | 中度 | 日常生活に相当な制限を受ける状態 |
| 5〜6級 | 軽度 | 日常生活に制限を受ける状態 |
障害福祉カウンセラー
障害種別ごとの等級判定基準
身体障害は大きく5つの種類に分けられ、それぞれの障害種別によって等級の判定基準が異なります。
主な障害種別の判定例
- 視覚障害:視力や視野の状態により判定(例:良い方の眼の視力が0.01以下は1級)
- 聴覚障害:聴力レベル(デシベル)により判定(例:両耳の聴力レベルが100デシベル以上は2級)
- 肢体不自由:上肢・下肢・体幹の機能障害の程度により判定
- 内部障害:日常生活活動の制限度合いにより判定
等級によるサービス内容の違い
障害等級によって、受けられる福祉サービスの内容や範囲が異なります。
- 1・2級(重度):特別障害者手当、重度障害者医療費助成、NHK放送受信料の全額免除、所得税の特別障害者控除などが適用されることが多い
- 3・4級(中度):公共交通機関の運賃割引、自動車税の減免、障害者控除などが適用されることが多い
- 5・6級(軽度):基本的な税控除や一部の割引サービスは受けられるが、重度障害者向けの特別サービスは適用されないことが多い
身体障害者手帳の等級制度は複雑ですが、自分の障害がどの等級に該当するかを知ることで、受けられる支援の内容を把握し、より効果的に活用することができます。
身体障害者手帳の更新と再認定
身体障害者手帳は、基本的に更新の必要がない永続的な手帳ですが、一部のケースでは再認定や更新が必要となることがあります。ここでは、身体障害者手帳の更新と再認定に関する重要な情報を解説します。
更新が必要なケースと不要なケース
身体障害者手帳は、基本的には一度交付されると有効期限がなく、生涯使用できるものです。しかし、以下のようなケースでは更新や再認定が必要になることがあります。
| 更新が必要なケース | 更新が不要なケース |
|---|---|
| ・障害の程度に変化が予想される場合 ・手帳に再認定期日や有効期限が記載されている場合 ・18歳未満で交付を受けた場合(一部の障害) |
・手帳に有効期限の記載がない場合 ・障害の状態が固定していると判断された場合 |
障害福祉担当者
再認定の対象となる主な障害
特に以下のような障害がある場合、再認定の対象となることが多いです。
- 人工透析を始めたばかりの腎臓機能障害
- 手術後間もない心臓機能障害
- 成長期にある小児の障害(肢体不自由など)
- 治療により改善が見込まれる視覚障害や聴覚障害
等級変更の可能性と再認定の流れ
再認定によって障害の程度が変化していると判断された場合、等級が変更されることがあります。等級が変わると受けられるサービスの内容も変わってくるため、注意が必要です。
再認定の手続きの流れ
- 再認定期日が近づくと、自治体から通知が届く
- 指定医師に診断書・意見書の作成を依頼する
- 必要書類を揃えて市区町村の障害福祉窓口に提出する
- 審査結果を待ち、新しい手帳を受け取る
住所変更や氏名変更の手続き
住所や氏名が変わった場合には届け出が必要です。これは更新ではなく、記載事項の変更手続きになります。市区町村内での引っ越しや、市区町村をまたぐ転居の場合も手続きが必要です。
身体障害者手帳は、障害のある方の生活を支える重要な証明書です。有効期限や再認定の期日をしっかり確認し、適切な時期に必要な手続きを行うことで、継続して各種サービスを利用できるようにしましょう。
身体障害者手帳に関するよくある疑問
身体障害者手帳に関して、初めて取得を検討する方や既に持っている方から、様々な疑問が寄せられています。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
取得によるデメリットはあるのか
障害者相談支援員
手帳を取得すること自体にはほとんどデメリットはなく、利用するかどうかは個人の判断に委ねられています。就職・転職に不利になるという懸念もありますが、むしろ障害者雇用枠での応募が可能になるなど、選択肢が広がることが多いです。
他の障害者手帳との違い
障害者手帳には、身体障害者手帳の他に「精神障害者保健福祉手帳」と「療育手帳」があります。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 特徴 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害など | 等級は1〜6級、基本的に更新不要 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、発達障害など | 等級は1〜3級、2年ごとの更新が必要 |
| 療育手帳 | 知的障害、発達障害(知的障害を伴うもの) | 等級はA(重度)とB(中軽度)、地域により異なる |
複数の障害がある場合の手続き
複数の身体障害がある場合は、それぞれの障害について診断書を作成し、申請時に提出します。審査では「総合等級」が決定され、1つの身体障害者手帳に複数の障害名と等級が記載されます。
また、身体障害と精神障害や知的障害が重複している場合は、それぞれの障害に対応する手帳を別々に申請し、取得することができます。
一時的な障害でも申請できるのか
身体障害者手帳は、障害が永続することを前提とした制度です。そのため、疾病の発病直後や、怪我による一時的な機能障害、手術後の一時的な機能低下などは、原則として対象外となります。
ただし、「障害が固定した」と医師が判断した場合は申請が可能です。障害の固定とは、治療による機能回復がこれ以上見込めない状態を指します。
身体障害者手帳に関する疑問は多岐にわたりますが、わからないことがあれば市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談してみましょう。
まとめ:身体障害者手帳の活用ポイント
身体障害者手帳は、障害のある方が社会生活をより豊かに、自立して送るための大切なツールです。この手帳を持つことで、医療費の助成や税金の控除、公共交通機関の割引など、様々な支援を受けることができます。
障害者支援団体代表
手帳の取得を検討されている方は、まずお住まいの自治体の窓口に相談してみましょう。すでに持っている方は、定期的に最新の制度やサービスをチェックし、自分に合った支援を積極的に活用することが大切です。