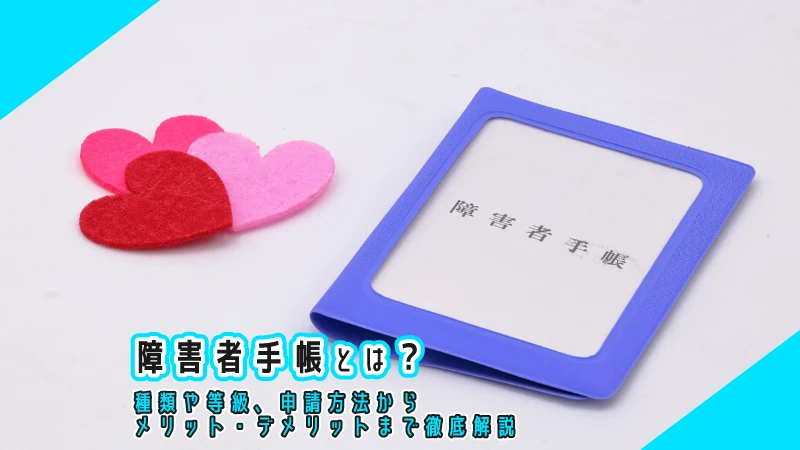- このコラムのまとめ
- 療育手帳は、知的障害のある方の生活と就労を支える大切な権利証です。等級判定や更新などのルールに加え、税制優遇や障害者枠での就職といった「実生活を楽にするメリット」を詳しく解説しました。制度は複雑ですが、知っているだけで選択肢は広がります。利用できる支援を最大限に活かし、生活の基盤を固めるヒントにしてください。
もくじ
もっと見る
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障害のある方が取得できる障害者手帳です。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と並び、障害者手帳の一つに数えられています。この手帳を所持することで、障害者総合支援法に基づくさまざまな支援やサービスを受けることができます。
| 障害者手帳の種類 | 対象となる方 |
|---|---|
| 療育手帳 | 知的障害のある方 |
| 身体障害者手帳 | 視覚、聴覚、肢体などの身体的な障害のある方 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、発達障害などの精神障害のある方 |
療育手帳制度の特徴
療育手帳は、厚生労働省からの通知に基づき、各自治体において定められた要綱のもとで運営されています。そのため、自治体によって名称や詳細が異なる点が特徴です。
福祉担当者
地域による名称の違い
療育手帳は地域によって呼び名が異なることがあります。主な名称は以下のとおりです。
- 「愛の手帳」(東京都・横浜市)
- 「愛護手帳」(青森県・名古屋市)
- 「みどりの手帳」(さいたま市)
名称は異なっても、いずれも療育手帳に分類されるため、受けられるサービスの基本的な内容に大きな違いはありません。
療育手帳に記載される内容
療育手帳には、主に以下の情報が記載されます。
- 本人の氏名、住所、生年月日、性別
- 障害の程度(等級)
- 保護者の氏名、住所、本人との続柄
- 指導・相談に関する記録
- 次回判定年月日(更新時期)
療育手帳は子どものうちに取得するケースが多いですが、成人後に知的障害の診断を受けて取得する人もいます。発達障害や身体障害と診断されている人でも、知的障害があると認められれば取得が可能です。
療育手帳取得のメリット
療育手帳を取得すると、様々な支援や優遇措置を受けることができます。主なメリットを紹介します。
経済的支援
療育手帳を持っていると、税金の控除や手当の支給など経済的な支援を受けられます。
- 税金の控除:所得税・住民税の障害者控除(A判定は特別障害者控除)
- 手当の支給:特別児童扶養手当など
- 心身障害者扶養共済:保護者が掛金を納めると、保護者死亡後も年金を受給できる
| 控除の種類 | 障害者 | 特別障害者 |
|---|---|---|
| 所得税の障害者控除 | 27万円 | 40万円 |
| 住民税の障害者控除 | 26万円 | 30万円 |
出典:
公共料金・施設利用の割引
療育手帳を提示することで、様々な公共料金や施設利用料が割引になります。
- 公共料金:NHK受信料、水道料金、携帯電話料金など
- 公営住宅:優先入居の対象となる
- 公共施設:美術館、博物館、映画館などの入場料割引
福祉支援員
交通機関の割引
各種交通機関も療育手帳所持者に対して運賃割引を実施しています。
- 鉄道:JRや私鉄各社で5割引(条件あり)
- バス・タクシー:路線バスは5割引、タクシーは1割引が一般的
- 航空運賃:国内線の運賃割引
- 高速道路:重度障害者が同乗する車両は5割引(介護者が運転する場合)
障害福祉サービスの利用
療育手帳があると、障害者総合支援法に基づく各種福祉サービスをスムーズに利用できます。
- ホームヘルプサービス
- ショートステイ(短期入所)
- 移動支援
- 日中活動系サービス
療育手帳は様々な支援やサービスを受けるための「パスポート」のような役割を果たします。サービスの詳細や対象条件は自治体によって異なる場合がありますので、お住まいの市区町村窓口で確認することをおすすめします。
就労に関するサポート

療育手帳を所持していると、就労に関する様々な支援やサービスを受けることができます。知的障害のある方の就労をサポートする制度や仕組みについて解説します。
障害者雇用枠での就職
療育手帳を所持していると、企業の「障害者雇用枠」での就職が可能になります。企業は従業員数に応じて、一定の人数(民間企業の場合2.5%)の障害者を雇用することが法律で義務付けられています。
就労支援専門家
就労支援サービスの種類
障害者総合支援法に基づく就労支援サービスには、主に以下の種類があります。
就労移行支援
一般企業への就職を目指す方に対して、就職に必要なスキルの習得や就職活動のサポートを行います。通常2年間の利用期間で、職場実習や面接対策なども行います。
就労継続支援A型・B型
一般企業での就労が難しい方が働く場所を提供するサービスです。
| サービス | 特徴 |
|---|---|
| A型(雇用型) | ・雇用契約を結ぶ ・最低賃金が保証される |
| B型(非雇用型) | ・雇用契約を結ばない ・作業に応じた工賃が支払われる |
就労定着支援
就職後、職場に定着できるよう支援するサービスです。就職後最長3年間、職場訪問や面談などを通じて働き続けるためのサポートを行います。
関連記事
就職活動は「チーム戦」。3つの機関を使い分ける
療育手帳を持っていると、一般の窓口ではなく、専門知識を持ったスタッフがいる「専門窓口」を利用できます。これは単なる相談場所ではなく、あなたの特性を企業に翻訳して伝えてくれる「エージェント」のような存在です。それぞれの得意分野を知って、賢く使い分けましょう。
- ハローワーク(障害者専門窓口):
求人の紹介元。「自分にできる仕事があるか不安」という段階でも、担当者が個別につき、時間をかけて希望を聞き取ってくれます。障害者枠の求人はここに集約されているため、情報収集の拠点になります。 - 地域障害者職業センター:
ここは「準備とリハビリ」の場所です。「職業評価」で得意・不得意を分析してもらったり、ジョブコーチ(職場適応援助者)を派遣してもらったりと、より専門的で技術的なサポートが受けられます。 - 障害者就業・生活支援センター(通称:ナカポツ):
仕事の悩みだけでなく、「金銭管理が不安」「生活リズムが整わない」といった生活面の困りごとまでセットで相談できるのが特徴です。就職した後も長く伴走してくれる、心強い存在です。
手帳は、これらの支援をスムーズに受けるための「パスポート」です。一人で求人サイトを眺めるよりも、こうした支援機関に「自分に合う働き方」を一緒に探してもらう方が、ミスマッチの少ない職場に出会える確率はぐっと高まります。
療育手帳の等級と判定基準
療育手帳は、障害の程度に応じて等級が分かれています。等級によって受けられるサービスの内容や範囲が異なるため、判定基準を理解しておくことが重要です。
A判定(重度)の基準
療育手帳のA判定は、重度の知的障害がある方に対して交付されます。厚生労働省のガイドラインでは、以下のいずれかに該当する場合にA判定となります。
- 知能指数がおおむね35以下で、日常生活の介助が必要または問題行動を有する
- 知能指数がおおむね50以下で、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する
B判定(中軽度)の基準
B判定は、A判定に該当しない知的障害のある方に対して交付されます。自治体によってはB1(中度)・B2(軽度)などにさらに細分化されていることがあります。
| 区分 | IQ(知能指数)の目安 | 日常生活の状況 |
|---|---|---|
| B1(中度) | IQ36~50程度 | 日常生活がおおむね一人でできるが、指示が必要 |
| B2(軽度) | IQ51~75程度 | 日常生活は一人でできる |
地域による等級区分の違い
療育手帳の等級区分は自治体によって異なります。主な等級区分の例をいくつか紹介します。
- 東京都(愛の手帳):1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)の4区分
- 神奈川県:A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4区分
- 兵庫県:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の3区分
福祉専門家
判定は「IQ」と「生活能力」の2軸で決まる
療育手帳の判定というと、「知能検査(IQテスト)の点数だけでバッサリ決められてしまう」というイメージをお持ちかもしれません。
しかし実際には、IQの数値はあくまで判断材料の一つです。最も重視されるのは「日常生活を送る上で、どれくらい手助け(福祉のサポート)が必要か」という点です。
そのため、判定の場ではご本人へのテストだけでなく、ご家族や支援者へのヒアリング(聞き取り)が丁寧に行われます。「一人で着替えができるか」「金銭管理はできるか」「トラブルが起きた時に助けを呼べるか」といった、生活に密着したエピソードも等級を決める重要な要素になります。
年齢によって「判定場所」が変わります
判定を受ける機関は、申請する時の年齢によって窓口が異なります。
- 18歳未満の方:「児童相談所」が担当します。
- 18歳以上の方:「知的障害者更生相談所」が担当します。
療育手帳の対象者
療育手帳は、知的障害のある方を対象とした障害者手帳です。ここでは、療育手帳の交付対象となる条件や、発達障害との関係について解説します。
知的障害のある方
療育手帳の主な対象者は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された方です。知的障害は、以下の特徴を持つ状態を指します。
- 知的機能(学習、推論、問題解決など)に制約がある
- 日常生活における適応機能に制約がある
- 発達期(おおむね18歳未満)に発症している
知的障害の判断には、主に知能指数(IQ)が用いられます。一般的に、IQ70以下(自治体によっては75以下)であり、かつ日常生活や社会生活に支障がある場合に、知的障害として判定されることが多いです。
大人になってからの申請には「18歳の壁」がある
療育手帳は「知的障害(発達期に現れた障害)」を対象としているため、大人になってから初めて取得しようとすると、少しハードルが上がります。「18歳未満の時点で知的障害があったこと」を証明する資料が必要になるからです。
| 申請時の年齢 | 判定の場所と難易度 |
|---|---|
| 18歳未満 (児童) |
児童相談所 学校や健診の記録がリアルタイムで残っているため、比較的スムーズに取得できます。 |
| 18歳以上 (成人) |
知的障害者更生相談所 「昔から障害があった」という証拠(通知表や過去の診断書など)を掘り起こす必要があり、準備に手間がかかるケースがあります。 |
発達障害(ADHD・ASD)でも取得できる?
「発達障害の診断だけ」では、原則として療育手帳は取得できません。分かれ道になるのは、「知的な遅れ(IQの低さ)を伴っているかどうか」です。
- 知的障害がある場合:「療育手帳」の対象になります。
- 知的障害がない場合:「精神障害者保健福祉手帳」の対象になります。
発達支援専門家
ただし、これらは「どちらか片方しか持てない」わけではありません。知的障害と精神障害(発達障害含む)の両方の要件を満たす場合は、手帳を「2冊持ち」することも可能です。使えるサービスの幅が広がるため、両方の取得を検討する価値は十分にあります。
また、一度取得したら終わり、と思われがちですが、療育手帳には「有効期限」があります。特に成長期のお子さんの場合、発達によって状態が変化しやすいため、数年ごとの「再判定(更新)」が必須となります。
療育手帳の有効期限と更新
療育手帳には有効期限が設けられており、期限が来ると更新手続きが必要になります。ここでは、有効期限の考え方と更新方法について解説します。
年齢別の有効期限
療育手帳の有効期限は原則として2年間ですが、年齢や自治体によって異なる場合があります。一般的な有効期限の設定例は以下のとおりです。
| 年齢区分 | 有効期限(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 乳幼児期 | 1~2年 | 発達の変化が大きい時期 |
| 学童期 | 2~3年 | 成長に応じて判定が変わる可能性あり |
| 青年期 | 2~4年 | 18歳時点での再判定が重要 |
| 成人期 | 2~5年、または期限なし | 自治体によって長期間の有効期限も |
18歳を境にして判定機関が児童相談所から知的障害者更生相談所に変わるため、18歳前後での更新は必ず行うようにしましょう。
更新手続きの方法
療育手帳の更新手続きは、以下の流れで行います。
- 有効期限の2~3ヵ月前から市区町村の窓口で申請
- 判定機関での再判定の予約
- 再判定の実施(知能検査や面接など)
- 新しい療育手帳の交付
更新申請の際に必要な書類は主に以下のとおりです。
- 療育手帳更新申請書
- 現在使用している療育手帳
- 本人の顔写真(縦4cm×横3cm程度)
- 印鑑
福祉事務所職員
更新以外の手続きが必要なケース
療育手帳の更新以外にも、以下のような場合には手続きが必要です。
- 住所や氏名が変わった場合
- 手帳を紛失・破損した場合
- 障害の状態が大きく変化した場合
これらの手続きは市区町村の障害福祉窓口で行います。特に住所変更の場合、自治体を越えての引っ越しでは、転出前と転入後の両方の自治体での手続きが必要になることがあります。
療育手帳の申請方法
療育手帳を取得するには、一定の手続きが必要です。ここでは、申請から交付までの流れや必要書類について解説します。
申請の準備:写真は「スマホ」でもOK?
申請に必要なものはシンプルですが、意外とつまづきやすいポイントがあります。役所の窓口に行く前に、以下のリストをチェックしてみてください。
- 申請書:窓口でもらってその場で書けばOKです。
- 顔写真:縦4cm×横3cm。写真館で撮る必要はありません。無背景ならスマホで撮影し、コンビニで「証明写真プリント」をしたもので十分通用する自治体がほとんどです(※念のため窓口に確認を)。
- 身分証と印鑑:マイナンバーカードや保険証、認印を持参しましょう。
- 【最重要】過去の記録(※18歳以上の場合):大人になってからの申請では、「18歳より前から障害があったこと」の証明を求められます。母子手帳、小学校の通知表、当時の診断書など、実家を捜索してでもかき集める必要があります。
判定の流れと内容
療育手帳の申請が受理されると、判定機関での判定を受けることになります。
- 市区町村の障害福祉窓口に必要書類を提出
- 判定日の予約(18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所)
- 判定機関で各種検査や面接を受ける
- 判定結果の連絡
- 市区町村窓口で療育手帳を受け取る
判定当日は「ぶっつけ本番」にしない
書類を出した後は、判定機関での「面談(検査)」が待っています。ここで多くの人が失敗するのが、「緊張して普段の様子が伝わらない(または、よそ行きで頑張りすぎてしまう)」ことです。
正しい等級をもらうためには、事前の準備がモノを言います。
| 判定の内容 | 攻略のポイント |
|---|---|
| 知能検査 | IQを測るテスト(田中ビネーなど)を行います。ここはありのまま受けるしかありません。 |
| 聞き取り調査 (面接) |
ここが勝負です。「着替えはできるか」「パニックになるか」などを聞かれますが、緊張すると普段の困りごとをド忘れしがちです。 |
相談支援専門員
手帳交付までの期間
申請から手帳が届くまでは、地域によりますが1〜2ヶ月かかるのが一般的です。「就職面接に間に合わない!」とならないよう、使う予定があるなら早めに動くのが鉄則です。
療育手帳の申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉課です。申請方法や必要書類について不明点がある場合は、窓口に相談するとよいでしょう。
療育手帳取得の注意点
申請から手帳が届くまでは、地域によりますが1〜2ヶ月かかるのが一般的です。「就職面接に間に合わない!」とならないよう、使う予定があるなら早めに動くのが鉄則です。
メリット・デメリットの考え方
療育手帳を取得するかどうかを考える際は、メリットとデメリットを総合的に判断することが大切です。
| メリット | 懸念点 |
|---|---|
| ・各種福祉サービスの利用 ・税金の控除 ・料金割引 ・障害者雇用枠での就労 |
・「障害者」というラベルへの抵抗感 ・更新手続きの負担 ・進路や就職への影響を懸念 |
療育手帳の取得に明確なデメリットはありませんが、上記のような懸念から取得を躊躇される方もいます。手帳の所持は外部に公表する必要はなく、必要な場面でのみ活用できます。
プライバシーへの配慮
療育手帳を持っていることを周囲に知られることを心配する方もいますが、プライバシーは守られています。
- 療育手帳の所持を他者に伝えるかどうかは本人や家族の判断です
- 自治体の職員には守秘義務があり、個人情報が勝手に外部に漏れることはありません
- 学校や職場に手帳の情報を伝えるかどうかも選択できます
福祉相談員
「障害者」というレッテル貼りが怖い?
手帳を取るかどうか迷う最大の理由は、制度上のデメリットではなく、「障害者として生きることへの心理的な抵抗感」ではないでしょうか。
しかし、療育手帳はあくまで「福祉サービスを利用するためのパスポート」に過ぎません。持っているからといって、誰かに言いふらす義務はないのです。
- 使うも使わないも自由:取得しても、普段はタンスの奥にしまっておいて構いません。
- 会社に言う必要はない:障害者枠で働く時以外は、会社に報告する義務はありません。一般枠で働くなら、隠したままでもOKです。
- プライバシーは守られる:役所の職員や学校の先生には守秘義務があります。近所の人に勝手に知られることはありません。
手帳は「レッテル」ではなく、生きるための「お守り」や「切り札」だと考えてみてください。普段は持っていることを忘れていて、税金を払う時や、就職活動をする時だけこっそり使う。そんな「いいとこ取り」な使い方ができる便利な道具なんですよ。
よくある質問
療育手帳に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。申請を検討されている方やすでに取得されている方の疑問解消にお役立てください。
大人になってからでも手帳は取れますか?
取得可能です。ただし、子どもの頃の記録を発掘する「証拠探し」が必要になります。
療育手帳は、法律上の定義で「発達期(おおむね18歳まで)」に現れた障害を対象としています。そのため、大人になってから申請する場合、「これは大人になってからの病気や認知症ではなく、子供の頃からあったものです」と証明しなければなりません。
具体的には、以下のような「過去の証拠」が審査の鍵になります。実家に眠っていないか確認してみましょう。
- 母子手帳:発語の遅れや検診時の記録などが残っているもの
- 通知表:「学習に遅れがある」「集団行動が苦手」といった先生のコメント
- 過去の検査結果:小中学校時代に受けた知能検査(WISCなど)の記録
もし手元に資料がない場合でも、ご両親や兄弟からの聞き取り(ヒアリング)で審査が進められるケースもあります。あきらめる前に、一度お住まいの自治体窓口や支援センターに「手持ちの資料がないのですが」と相談してみてください。
精神科医
療育手帳と運転免許の関係は?
療育手帳を持っていることだけで運転免許の取得が制限されることはありません。運転免許は、知識や技能の試験に合格し、運転に支障をきたす可能性のある特定の病気や障害がないと判断されれば取得できます。知的障害の程度によっては、学科試験の内容理解や実技試験での技能習得に困難が生じる場合があります。
療育手帳と障害者手帳の違いは?
「障害者手帳」は総称であり、療育手帳はその一種です。日本の障害者手帳制度には主に3種類あります。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など |
| 療育手帳 | 知的障害(知的発達症) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、気分障害、発達障害など |
療育手帳と障害年金の関係は?
療育手帳と障害年金は別の制度であり、一方を持っていても自動的に他方が受給できるわけではありません。療育手帳を持っていると、障害年金の申請において参考資料となる場合がありますが、障害年金の申請には医師の診断書など別途必要書類があります。
まとめ:手帳は、あなたと家族を守る「権利のパスポート」
療育手帳を取得するにあたり、「障害者という枠組みに入ること」に抵抗を感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この手帳はレッテルを貼るためのものではなく、社会の中で安心して生きていくための「権利証」です。
税金の控除も、公共料金の割引も、就労支援も。これらはすべて、ハンディキャップのある方が当たり前に受け取っていい「権利」です。遠慮する必要は一切ありません。ライフステージごとに変わる必要な支援を、手帳というパスポートを使って最大限に引き出してください。
障害者支援専門家