公開日:2025.08.11
障害年金の更新手続き完全ガイド:手続きの流れから支給停止対策まで
- ホーム
- コラム
- 「法律・制度」のコラム
- 障害年金の更新手続き完全ガイド:手続きの流れから支給停止対策まで
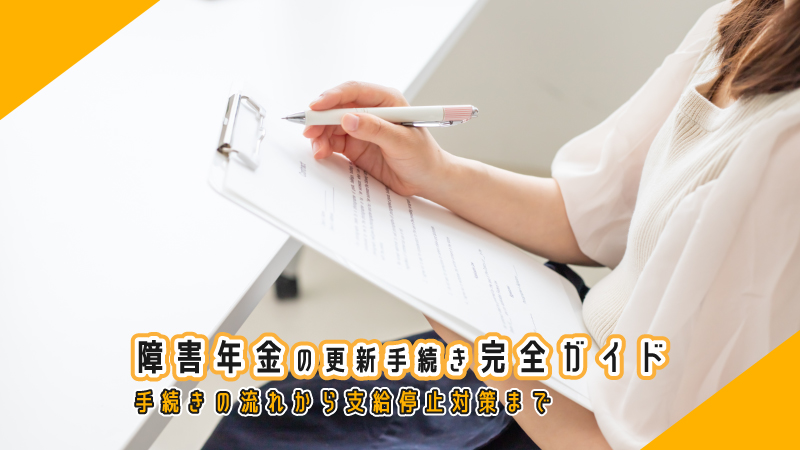
- このコラムのまとめ
- 障害年金の更新手続きを詳しく解説。有期認定と永久認定の違い、更新の流れ、支給停止・減額になる原因から対処法まで網羅。診断書作成のポイントや医師への症状の伝え方など、スムーズな更新のためのコツも紹介。統計によれば約98%の方が継続受給できているので、正しい知識で不安なく手続きを進めましょう。
もくじ
もっと見る
障害年金の更新とは
障害年金は一度支給が決まっても、自動的に継続されるわけではありません。ここでは更新制度の基本を解説します。
有期認定と永久認定の違い
障害年金の認定には「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。有期認定は1〜5年ごとに更新が必要で、精神障害や内部疾患など症状が変化する可能性がある障害に適用されます。永久認定は更新不要で、四肢の切断や失明など回復見込みのない障害が対象です。
更新時期の確認方法
更新時期は年金証書の「次回診断書提出年月」欄で確認できます。具体的な月日が記載されている場合は有期認定で更新が必要です。「**年**月」と記載されている場合は永久認定です。
社会保険労務士
障害年金の更新手続きの流れ
障害年金の有期認定を受けている方は、定期的に更新手続きを行う必要があります。ここでは更新手続きの流れを解説します。
STEP1:障害状態確認届が届く
更新時期が近づくと、日本年金機構から「障害状態確認届」が誕生月の3ヶ月前の月末に届きます。
STEP2:医師に診断書を作成してもらう
障害状態確認届を受け取ったら、速やかに医師に診断書の作成を依頼します。診断書作成には通常2〜3週間かかり、5,000〜10,000円程度の費用がかかります。
STEP3:診断書の内容を確認する
診断書を受け取ったら、傷病名や日付の誤り、記入漏れがないか内容を確認しましょう。特に前回と違う医師が作成した場合は注意が必要です。
STEP4:必要書類を提出する
誕生月の末日までに診断書を提出します。郵送か年金事務所などの窓口で直接提出できます。
STEP5:審査結果を待つ
提出後、約3ヶ月で審査結果が届きます。等級に変更がなければハガキが、変更があれば通知書が届きます。
STEP6:審査結果の反映
等級が上がれば誕生月の翌月分から、下がれば誕生月の4ヶ月目から反映されます。統計によると、約96%の方が継続して受給できています。
社会保険労務士
更新審査で支給停止・減額になる原因
障害年金の更新で最も不安なのが支給停止や減額です。どのような場合にそうなるのかを解説します。
障害の状態が軽減したと判断された場合
治療効果で症状が改善した、投薬量や通院頻度が減少したなどの理由で、障害の状態が軽減したと判断されると、等級の引き下げや支給停止になることがあります。
就労状況など生活環境の変化
特に精神疾患で2級を受給している場合、一般就労を始めると「労働能力が回復した」と判断されることがあります。ただし、障害者雇用枠での就労や短時間勤務、特別な配慮を受けている場合は、その実態を診断書に記載してもらうことが重要です。
社会保険労務士
出典:
更新審査を有利に進めるポイント
障害年金の更新審査を有利に進めるための重要なポイントを紹介します。
医師への症状の正確な伝え方
診断書の内容は審査結果を左右する重要な要素です。障害が日常生活や仕事にどう影響しているかを具体的に伝えましょう。メモを準備したり、家族に同席してもらうのも効果的です。
日常生活状況の記載のコツ
精神疾患の場合は家事や外出の状況、対人関係の困難さを具体的に説明しましょう。身体障害の場合は移動制限や日常動作の困難さを伝えることが大切です。
就労している場合は、職場での配慮や支援の状況も必ず説明しましょう。
診断書の記載内容を確認する重要性
診断書が作成されたら、提出前に必ず内容を確認しましょう。特に前回と異なる医師が作成する場合は、前回の診断書を参考にしてもらうとよいでしょう。
社会保険労務士
更新で問題が発生した場合の対処法
障害年金の更新審査で支給停止や減額となった場合の対処法を解説します。
支給停止になった場合の再申請方法
障害が再び重くなった場合は「老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届」を提出することで年金の支給再開を求められます。診断書と共に年金事務所などに提出しましょう。
減額された場合の対応策
症状が悪化したら「障害給付額改定請求書」で等級の引き上げを求められます。前回の審査から原則1年経過後に申請可能です。症状悪化を客観的に示す資料があると有利です。
不服申立ての手続き
審査結果に納得できない場合は不服申立てができます。処分を知った日から3ヶ月以内に地方厚生局の社会保険審査官に審査請求を行います。その結果にも納得できなければ2ヶ月以内に再審査請求も可能です。
社会保険労務士
よくある質問と回答
障害年金の更新に関してよく寄せられる質問にお答えします。
更新期限に間に合わない場合はどうすればいい?
期限に間に合わないと一時的に支給が差し止められますが、後日提出して認定されれば遡って支給されます。まずは年金事務所に連絡し、状況を説明しましょう。
通院していない場合の診断書はどうする?
定期的に通院していなくても、診断書は必要です。以前かかっていた医療機関に連絡し、診断書作成のための受診を相談しましょう。
仕事をしていても更新は可能?
就労していても更新は可能です。障害者雇用枠での就労か、特別な配慮を受けているかなど、就労状況を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらうことが重要です。
社会保険労務士
専門家に相談するメリット
障害年金の更新手続きは専門的な知識が必要です。ここでは専門家に相談するメリットと選び方を解説します。
社会保険労務士などの専門家の役割
社会保険労務士(社労士)に依頼することで、診断書のチェック、医師への伝え方のアドバイス、書類作成の負担軽減など様々なサポートが受けられます。
特に精神疾患の場合は、症状を客観的に説明することが難しいため、専門家の支援が効果的です。
相談先の選び方
障害年金に詳しい社労士を選ぶことがポイントです。障害年金の実績があるか、自分の障害に関する知識があるか、費用体系はどうかなどを確認しましょう。支給停止後の不服申立てなど法的対応が必要な場合は弁護士への相談も検討します。
社会保険労務士
まとめ:スムーズな更新手続きのために
障害年金の更新手続きを円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、年金証書で更新時期を確認し、忘れないようカレンダーなどにメモしておきましょう。障害状態確認届が届いたら、速やかに医師に診断書の作成を依頼します。その際、症状や日常生活の状況を正確に伝えることが大切です。診断書が完成したら内容をしっかり確認し、提出期限である誕生月の末日までに忘れずに提出しましょう。
社会保険労務士





