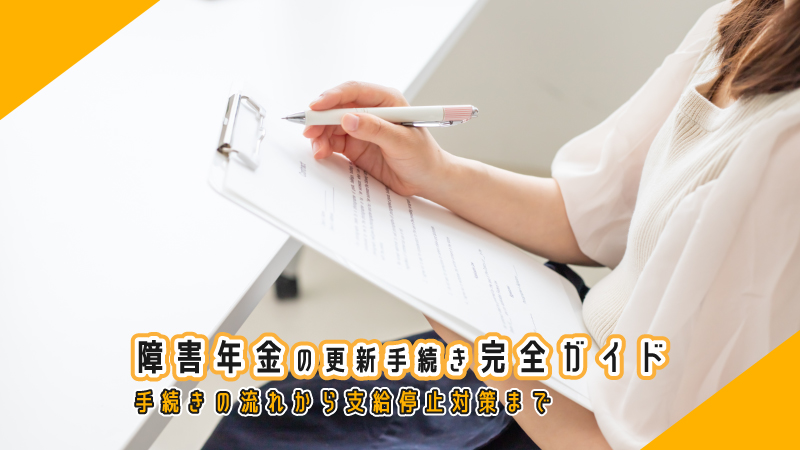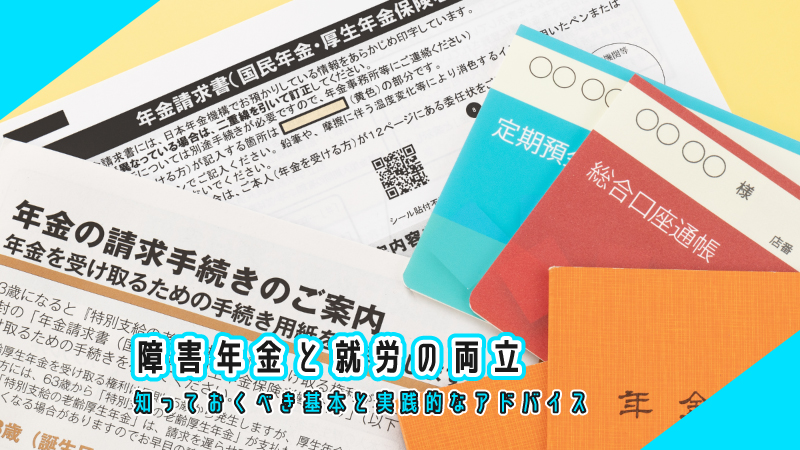
- このコラムのまとめ
- 障害年金と就労は両立可能です。受給者の約3分の1が何らかの形で働いています。本記事では、障害年金と就労の基本的関係、受給継続に影響する要素、両立のための実践ポイント、障害種別ごとの事例、働き方の選択肢、よくある質問について解説します。正しい知識と適切な準備で、障害があっても自分らしい生活を送りましょう。
もくじ
もっと見る
障害年金と就労の関係性:基本的な知識
障害年金を受給している方や、これから申請を考えている方の多くが「働くと年金が止まってしまうのではないか」と不安を抱えています。しかし実際には、障害年金と就労は両立可能なのです。
障害年金制度の基本
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に受け取れる公的年金制度です。受給条件には就労の有無は含まれておらず、障害の程度によって支給されます。
社会保険労務士
障害年金には主に以下の種類があります。
- 障害基礎年金:国民年金加入者や20歳前の傷病が対象
- 障害厚生年金:厚生年金加入中の傷病が対象
障害年金受給者の就労実態
厚生労働省の統計によると、障害年金受給者の約3人に1人が何らかの形で就労しています。障害の種類別に見ると、就労率は身体障害で48%、知的障害で58.6%、精神障害で34.8%となっています。このデータからも分かるように、障害年金を受給しながら働くことは決して珍しくありません。
出典:
障害等級別の就労への影響と注意点
障害年金の等級によって、就労に関する考え方や影響は異なります。等級ごとの特徴を理解しておきましょう。
- 1級:日常生活でも常時介助が必要な重度の状態。原則として就労は困難とされますが、特別な配慮や環境があれば可能なケースもあります。
- 2級:日常生活に著しい制限がある状態。短時間勤務や軽作業、特別な配慮がある環境での就労なら可能な場合が多いです。
- 3級(厚生年金のみ):就労を前提とした障害等級。通常の業務に配慮が必要であれば該当する可能性があります。
重要なのは、障害年金の受給条件に「就労していないこと」は含まれていないという点です。障害年金は、障害によって生活や仕事などが制限される場合に受給できる制度であり、就労の有無そのものが直接の判断基準ではありません。
ただし、障害年金の受給を継続するためには、障害の状態と就労の実態に矛盾がないことが重要です。次のセクションでは、受給継続に影響する具体的な要素について詳しく見ていきましょう。
障害年金の受給継続に影響する要素
障害年金を受給しながら働く場合、年金の継続受給に影響する要素を理解しておくことが重要です。ここでは、主な影響要素を解説します。
就労状況が審査に影響する傷病の種類
障害の種類によって、就労の有無が審査に与える影響は異なります。
- 就労の影響を受けにくい傷病:視覚・聴覚障害、肢体不自由、人工臓器使用など
- 就労実態が審査に影響する傷病:精神疾患(うつ病、統合失調症など)、内臓疾患(がん、心臓病など)
障害年金専門家
受給停止になるケース
障害年金の受給が停止になる主なケースには、以下のようなものがあります。
- 障害が軽くなったと判断された場合
- 20歳前傷病による障害基礎年金で所得制限を超えた場合
(前年度所得が472.1万円を超えると全額停止、370.4万円を超えると半額停止) - 更新時の診断書の内容が不十分な場合
出典:
有期認定と継続的な審査の仕組み
障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。有期認定は1〜5年ごとに更新審査があり、この時点で障害の状態が改善したと判断されると、等級の引き下げや支給停止になる可能性があります。
更新時には医師との連携を密にし、就労状況と配慮の実態を具体的に説明することが重要です。
障害年金と就労を両立するための実践ポイント
障害年金と就労を上手に両立するには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは実践的なアドバイスを紹介し、年金受給を継続しながら働くための具体的な方法を解説します。
医師とのコミュニケーションと診断書の確認
障害年金の認定や更新において、医師が作成する診断書は極めて重要です。就労状況を医師に正確に伝え、診断書に適切に反映してもらいましょう。
社会保険労務士
就労状況の適切な申告と記録方法
職場での配慮や支援内容、症状による制限などを具体的に記録しておくことが重要です。特に以下の点に注意しましょう。
- 就労内容と障害の状態に矛盾がないか確認する
- シフトや支援記録などを保管する
- 症状による制限や体調の波を記録する
収入管理と所得制限への対応
障害年金には基本的に所得制限はありませんが、20歳前傷病による障害基礎年金のみ例外的に所得制限があります。
- 20歳前傷病の場合、前年の所得が472.1万円を超えると全額支給停止になります
- 収入額よりも「就労の実態」が重視されることを理解しましょう
- 障害年金は非課税所得ですが、給与所得には通常通り課税されます
就労と障害年金の両立には、事前の準備と継続的な記録が重要です。特に更新時期が近づいてきたら、早めに準備を始め、就労の影響が診断内容に適切に反映されるよう医師との連携を取りましょう。
障害種別ごとの就労と年金受給の両立事例
障害の種類によって、就労と障害年金の両立のしやすさや注意点は異なります。ここでは主な障害種別ごとに、実際に障害年金を受給しながら働いている方々の事例を紹介します。
精神障害で障害年金を受給しながら働くケース
精神障害の場合、外見からは障害が分かりにくく、「働けているなら障害は軽い」と誤解されやすい特徴があります。
| 事例 | 障害内容 | 年金種類・等級 | 就労形態 |
|---|---|---|---|
| 30代女性 | てんかん | 障害基礎年金2級 | パート勤務(月15日程度) |
| 30代男性 | 高次脳機能障害 | 障害厚生年金3級 | アルバイト(データ入力) |
社会保険労務士
身体障害で障害年金を受給しながら働くケース
身体障害は目に見える障害が多く、客観的な診断基準があるため、就労の有無が障害年金の審査に与える影響は比較的小さいことが特徴です。
- 左大腿骨頚部骨折(人工関節置換)の50代男性:障害厚生年金3級を受給しながらフルタイム勤務
- 両眼の視力低下の40代女性:障害基礎年金2級を受給しながら在宅でデータ入力の仕事
内部障害で障害年金を受給しながら働くケース
内部障害は外見からは分かりにくく、日によって症状が変動することも多いため、理解されにくい面があります。
- 慢性腎不全の40代男性:障害厚生年金2級を受給しながら、透析日の早退許可を得てフルタイム勤務
- 大動脈解離の40代男性:障害厚生年金3級を受給しながら、担当顧客数を減らして短時間勤務
障害年金受給者の働き方の選択肢
障害年金を受給しながら働く場合、自分の障害特性や体調に合った働き方を選ぶことが重要です。適切な就労形態を選択することで、障害年金の受給を継続しながら、無理なく安定した生活を送ることができます。
障害に合わせた就労形態の選び方
障害の種類や程度によって、適した就労形態は異なります。自分の特性や体調に合った働き方を選ぶことが大切です。
| 就労形態 | 特徴 | 向いている障害特性 |
|---|---|---|
| 短時間勤務 | 1日の勤務時間を短くする | 疲れやすい、集中力に制限がある |
| 在宅勤務 | 自宅で仕事をする | 移動困難、環境変化に弱い |
| 障害者雇用 | 法定雇用率に基づく雇用 | 配慮や支援が必要な場合 |
障害年金を活用した経済的自立の方法
障害年金は「収入の一部」として考え、就労収入と組み合わせることで経済的な自立を目指せます。
就労支援専門家
就労支援サービスの活用法
障害のある方の就労を支援するサービスを活用することで、障害年金との両立がしやすくなります。
- 就労移行支援:一般企業への就職を目指す支援サービス
- 就労継続支援A型:雇用契約を結んで働く福祉的就労の場
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばない福祉的就労の場
障害年金受給者の働き方は一人ひとり異なります。自分の体調や障害特性に合った無理のない働き方を選び、必要に応じて支援サービスを活用することで、長期的に安定した生活を送ることができます。
障害年金と就労に関するよくある質問
障害年金を受給しながら働くことについて、多くの方が抱える疑問や不安にお答えします。
障害年金の受給は会社に知られる?
障害年金の受給状況は基本的に会社に知られることはありません。障害年金は非課税所得であり、社会保険料にも関係しないため、ご自身から申告しない限り会社側が知ることはできません。
社会保険労務士
収入が増えたら障害年金はどうなる?
障害厚生年金と20歳以後の傷病による障害基礎年金には所得制限はありません。ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、前年の所得が一定額を超えると減額または停止します。
障害年金が停止になった場合の対処法
万が一、就労を理由に障害年金の支給が停止になった場合、以下の対処法があります。
- 審査請求:不支給決定から3ヶ月以内に審査請求が可能
- 事後重症請求:症状が悪化した場合、再度申請可能
- 専門家に相談:社会保険労務士などの専門家にアドバイスを求める
パートや在宅ワークも障害年金に影響する?
短時間勤務や在宅ワークも就労の一形態ですが、「障害のために通常の勤務が困難で、配慮された働き方をしている」という説明ができれば、むしろ障害の状態を裏付ける材料になることもあります。
まとめ:障害年金と就労の両立で豊かな生活を目指すために
障害年金と就労の両立は十分に可能です。厚生労働省の統計によれば、障害年金受給者の約3分の1が何らかの形で就労しています。
社会保険労務士
両立を成功させるためには、正しい知識と情報、適切な記録と準備、そして専門家や支援者との連携が重要です。
自分の障害特性に合った働き方を選び、無理のないペースで進めることで、障害年金を受給しながらも充実した就労生活を送ることができるでしょう。