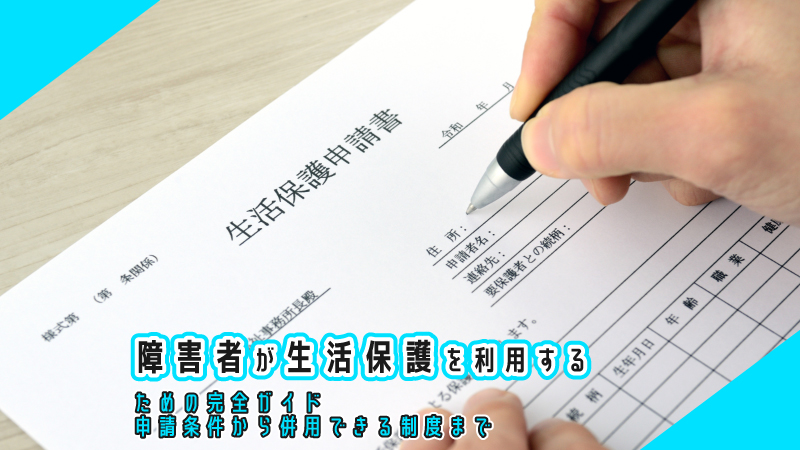公開日:2025.08.15
生活保護受給中でも利用できる就労支援制度の完全ガイド – 併用のメリットと注意点
- ホーム
- コラム
- 「法律・制度」のコラム
- 生活保護受給中でも利用できる就労支援制度の完全ガイド – 併用のメリットと注意点
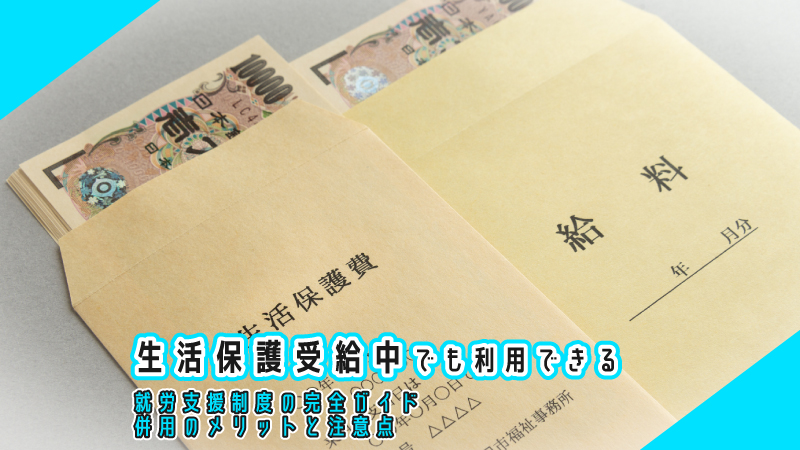
- このコラムのまとめ
- 生活保護を受給中でも就労移行支援などの就労支援制度を併用できます。利用料無料で就労スキルを身につけられる大きなメリットがあり、段階的な自立への道筋を作れます。申請手続きの流れ、収入の取り扱い、実際の成功事例など、両制度を上手に活用して経済的自立を目指すための完全ガイドです。
もくじ
もっと見る
生活保護と就労支援制度の併用は可能なのか?
「生活保護を受けながら就労支援を利用できるのだろうか」と心配している方も多いでしょう。結論から言うと、生活保護受給中でも就労移行支援などの就労支援制度を併用することは可能です。
就労支援制度の種類と特徴
主な就労支援制度には以下のようなものがあります。
- 就労移行支援:一般就労を目指す障害や難病のある方向けの通所型サービス
- 就労継続支援A型:最低賃金以上の給料を得ながら働く福祉サービス
- 就労継続支援B型:雇用契約を結ばず、自分のペースで働ける福祉サービス
併用が認められる理由
生活保護制度は最低限度の生活保障と自立支援を目的としています。就労支援制度の利用は「自立」という目標に向けた積極的な一歩と位置づけられるため、併用が認められています。
福祉事務所職員
生活保護受給中の利用料
生活保護受給世帯では、就労移行支援などの障害福祉サービスの利用料が無料になります。ただし、交通費や昼食代などの実費は自己負担となる点に注意が必要です。
就労支援制度を利用するための条件
就労支援制度を利用するには、以下のような条件を満たす必要があります。
- 原則として18歳以上65歳未満であること
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがあること
- 一般企業での就労を希望していること(就労移行支援の場合)
両制度の併用は、経済的な安定を確保しながら就労スキルを高め、将来的な自立を目指すための効果的な方法です。
自立への第一歩として、積極的に検討してみることをお勧めします。
生活保護受給中に就労支援制度を利用するメリット
生活保護を受給しながら就労支援制度を利用することには、多くのメリットがあります。ここでは主な利点を紹介します。
経済的な負担が少なく就労スキルが身につく
生活保護受給中は就労支援サービスの利用料が無料となります。経済的な不安を抱えることなく、就労に必要なスキルを身につけられるのが最大のメリットです。
- 利用料が無料:生活保護受給世帯は障害福祉サービスの利用料が無料です
- 生活基盤の確保:生活の心配をせずに就労訓練に集中できます
段階的な自立への道筋が作れる
就労支援制度を利用することで、一足飛びではなく段階的に自立への道筋を作ることができます。
- 生活リズムの改善から始まり、職業スキルの習得へと進みます
- 実習・体験就労を経て、自信を培いながら就職を目指せます
就労自立給付金を受け取れる
就職によって生活保護から脱却する際には、「就労自立給付金」を受け取ることができます。これは新生活のスタートを支える大切な資金となります。
生活保護担当ケースワーカー
このように、生活保護と就労支援制度を併用することで、経済的・精神的な安定を保ちながら、着実に自立への歩みを進めることができるのです。
実際の利用者事例と成功への道のり
生活保護と就労支援制度を併用して自立を果たした方々の実例をご紹介します。
うつ病から回復し事務職へ ― 50代男性Aさんの場合
Aさん(50代男性)は職場の人間関係でうつ病を発症し、働けなくなったため生活保護を受給。回復後、就労移行支援事業所の利用を開始しました。
Aさん
約1年間の訓練を経て、Aさんは障害者雇用枠で労務関係の事務職に就職。就労自立給付金を受けながら生活保護から脱却しました。
発達障害の特性を活かしてIT企業へ ― 30代女性Bさんの場合
Bさん(30代女性)は発達障害(ASD)の診断後、就職活動がうまくいかず生活保護を申請。就労継続支援B型からスタートし、その後就労移行支援に移行しました。
就労移行支援では自己理解を深め、特性を強みに変える訓練を受けました。データ分析や論理的思考などの強みを活かし、IT企業のデータ入力・分析部門への就職に成功。職場での合理的配慮も得られ、安定して働けるようになりました。
成功事例から学ぶポイント
- 段階的な回復と訓練:小さなステップから始めること
- 自己理解の深化:強みと弱みを理解し、適職を見つけること
- 継続的な支援の活用:就職後も定着支援を利用すること
併用する際の申請手続きと流れ
生活保護と就労支援制度を併用するためには、それぞれの制度で定められた申請手続きが必要です。ここでは基本的な流れを解説します。
福祉事務所への相談と申請方法
生活保護の申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います。
- 相談予約:福祉事務所に電話で予約
- 初回面談:現在の状況を説明し申請意思を伝える
- 申請書類の提出:必要書類を提出
- 調査:家庭訪問や資産調査などが行われる
- 決定通知:原則14日以内に結果が通知される
障害福祉サービス受給者証の取得手順
就労支援サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
相談支援専門員
就労支援事業所の選び方
事業所選びでは以下のポイントを考慮しましょう。
- 通いやすさ:自宅からのアクセス
- 特性への対応:自分の障害特性に合ったプログラム
- 費用面:交通費補助や食事提供の有無
可能であれば複数の事業所を見学し、自分に合った場所を選ぶことをお勧めします。
併用利用時の注意点と収入の取り扱い
生活保護と就労支援制度を併用する際には、特に収入の取り扱いについて正確に理解しておく必要があります。
収入申告の義務と扶助費調整の仕組み
生活保護受給者には、あらゆる収入を福祉事務所に申告する義務があります。就労支援で得た収入も例外ではありません。
- 収入申告:「収入申告書」に記入して提出
- 扶助費調整:申告された収入に基づき生活保護費が調整される
ケースワーカー
交通費・食費などの実費負担について
就労支援事業所に通所する際の交通費や昼食代は基本的に自己負担です。ただし、事業所によっては交通費補助や食事提供を行っているところもあります。
障害年金など他の給付金との関係
障害年金や失業給付などの社会保障給付も「収入」として認定され、基本的に生活保護費から差し引かれます。ただし、障害者加算が適用される場合もあります。
就労によって自立する際には「就労自立給付金」が支給されるため、この制度も活用しましょう。
よくある質問(FAQ)
生活保護と就労支援制度の併用について、よくある質問にお答えします。
就労支援を利用して就職したら生活保護はすぐ打ち切られる?
ケースワーカー
障害者手帳がなくても利用できる?
障害者手帳がなくても、医師の診断書などで障害や難病の状況が確認できれば、就労支援サービスを利用できる場合があります。
生活保護と障害年金は両方もらえる?
生活保護と障害年金は同時に受給可能ですが、障害年金は「収入」として認定され、その分生活保護費が減額されます。
通所交通費の負担軽減方法はある?
- 交通費補助のある事業所を選ぶ
- 障害者割引の活用
- 送迎サービスのある事業所を選ぶ
就労支援を受けても就職できなかった場合はどうなる?
就労支援の利用期間が終了しても就職に至らなかった場合、就労継続支援A型・B型への移行や、別の就労移行支援事業所の利用などが選択肢となります。
まとめ:生活保護から自立へのステップアップ
生活保護と就労支援制度の併用は、自立への効果的な道筋となります。経済的な安定を保ちながら、就労に必要なスキルを段階的に身につけていくことができるのです。
就労支援利用経験者
自立への道のりは決して平坦ではありませんが、小さな成功体験を積み重ねることで自信をつけていくことができます。
支援者とのパートナーシップを大切にしながら、自分のペースで着実に前進していきましょう。