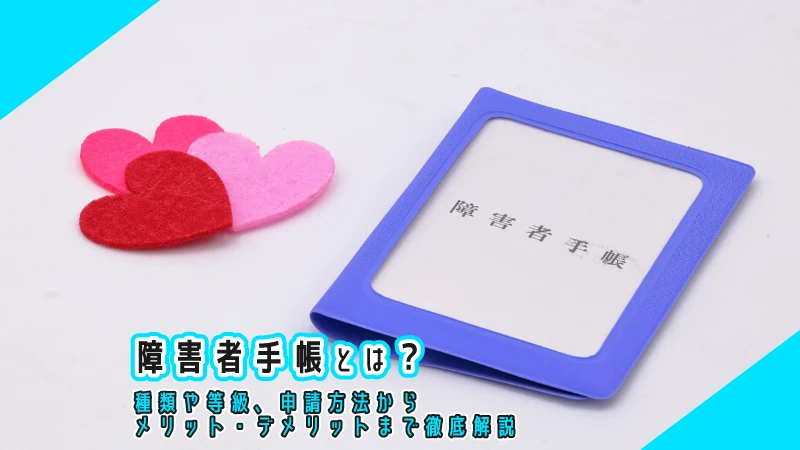公開日:2025.08.20
精神障害者保健福祉手帳の等級とは?1級・2級・3級の違いとメリット・デメリットを徹底解説
- ホーム
- コラム
- 「法律・制度」のコラム
- 精神障害者保健福祉手帳の等級とは?1級・2級・3級の違いとメリット・デメリットを徹底解説
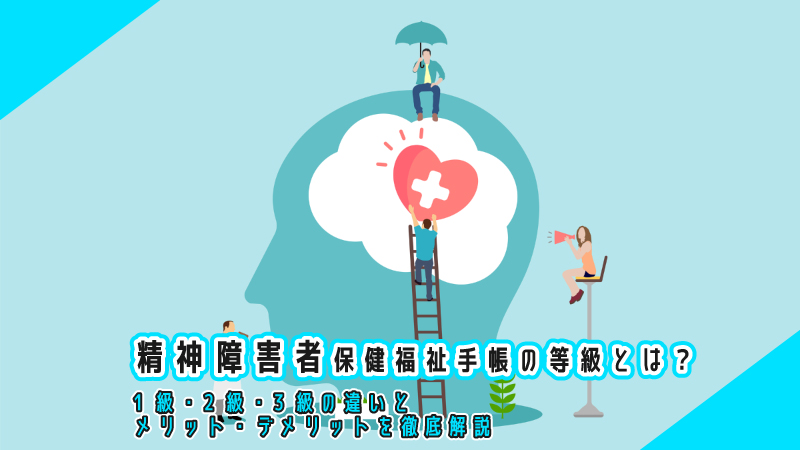
- このコラムのまとめ
- 精神障害者保健福祉手帳の等級(1級〜3級)の違いと判定基準、各等級で受けられる税金控除や公共料金割引などの経済的メリット、就労支援などのサービス内容を解説。申請方法や更新手続き、取得の際の懸念点も紹介し、精神疾患のある方の社会参加と自立を支援するための制度について詳しく説明しています。
もくじ
もっと見る
精神障害者保健福祉手帳の等級判定基準
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象に交付される手帳です。障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設定されており、それぞれの等級によって受けられるサービスや支援内容が異なります。
精神障害者手帳の等級判定の仕組み
精神障害者手帳の等級は、次の観点から総合的に判断されます。
- 精神疾患の存在の確認
- 精神疾患(機能障害)の状態の確認
- 能力障害(活動制限)の状態の確認
- 精神障害の程度の総合判定
精神疾患の種類だけでなく、その症状によって日常生活や社会生活にどの程度の支障をきたすかが重要な判断基準となります。
1級:日常生活のすべてに「誰かの手」が必要な状態
ベッドから起き上がって着替える、食事を摂る。そういった当たり前の行動が億劫でたまらず、一日中横になって過ごしてしまう……。誰かの声掛けや介助がないと、生活が破綻してしまうレベル、と考えていただくとイメージに近いでしょう。
精神保健福祉士
具体的には、以下のような状態が継続している場合が該当します。
- 外出:通院が必要でも、家族などの付き添いがないと家から出ることができない
- 食事・衛生:食欲がわかず食事を抜いたり、お風呂に入ることができず清潔を保てなかったりする
- 安全管理:火の不始末のリスクがあったり、金銭感覚が極端になって管理できなかったりする
- 対人関係:家族以外との意思疎通がほとんど成立せず、自分の殻に閉じこもっている
2級:一人暮らしには「見守り」が必要なレベル
2級は、必ずしも24時間の付き添いは必要ありませんが、完全に一人で生活を回すには危うさが残る状態です。「調子が良い時はできるけれど、何かトラブルがあると途端に崩れてしまう」ため、定期的な福祉サービスの介入が必要です。
2級に該当する方の特徴は以下の通りです。
- 想定外への弱さ:いつものコンビニなら行けるが、電車遅延などの「ハプニング」が起きるとパニックになり、一人で対処できない
- 衛生面の波:「お風呂に入らなきゃ」と分かっていても体が動かず、身だしなみが整えられない日が多い
- 対人トラブル:その場の空気に合わない発言をしてしまったり、相手の意図を誤解してトラブルになったりしやすい
3級:一見普通に見えるけれど、「配慮」が必要なレベル
3級は、日常生活や家事はある程度自力でこなせるため、周囲からは「単なる甘えでは?」「怠けているだけでは?」と誤解されやすい辛さがあります。しかし実際には、ストレス耐性が低く、環境の変化によってガクンと調子を崩しやすいため、就労には「短時間勤務」や「障害者枠」などのセーフティネットを必要とします。
3級に該当する方の特徴は以下の通りです。
- 応用力の課題:ルーチンワークは得意だが、マニュアルにない指示をされるとフリーズしてしまう
- 人間関係の消耗:表面上の会話はできるが、長時間の交流は精神的に著しく消耗し、翌日寝込んでしまう
- 環境変化への弱さ:平穏な環境なら問題ないが、部署異動や引っ越しなどの「変化」が起きると、適応できずに症状が悪化する
「診断書」で医師が見ているポイント
等級判定で重視されるのは、病名よりも「今の生活で、具体的に何ができなくて困っているか」という事実です。審査の際は、主に以下の「自立度」がチェックポイントになります。
| 判定の視点 | チェックされる具体的な能力 |
|---|---|
| 自分の身の回りのこと | 「お風呂に入りましょう」と言われなくても自分で入浴できるか? 部屋の掃除や食事の準備を、誰の手も借りずに継続できるか? |
| >社会との関わり | 一人でバスや電車に乗って目的地まで行けるか? 役所での手続きや買い物を、店員や窓口の人とトラブルなく行えるか? |
| 働く力・持続力 | 仕事に就いたとして、毎日決まった時間に通えるか? 職場のルールを守り、同僚と協力して業務を行える安定性があるか? |
等級は固定されたものではなく、症状の変化に応じて更新時に見直されることがあります。病状が改善した場合は等級が下がることもありますし、悪化した場合は上がることもあります。
精神科医
精神障害者手帳の等級判定は、都道府県や政令指定都市の精神保健福祉センターが行っています。
診断書の内容をもとに総合的に判断されるため、同じ診断名でも症状や生活状況によって等級が異なることがあります。
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、精神疾患を持つ方の社会復帰と自立、社会参加の促進を図ることを目的として、一定の精神障害があると認められた方に交付される手帳です。「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(精神保健福祉法)に基づいて1995年に創設されました。
精神障害者手帳の対象となる精神疾患
精神障害者手帳の対象となるのは、「精神疾患を有する者であって、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者」とされています。具体的には、以下のような精神疾患が対象となります。
- 統合失調症
- うつ病・双極性障害などの気分障害
- てんかん
- 発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如多動症など)
- 高次脳機能障害
- ストレス関連障害(適応障害、PTSDなど)
精神保健福祉士
障害者手帳の種類
日本の障害者手帳制度には、主に以下の3種類があります。障害の種類によって申請する手帳が異なります。
| 手帳の種類 | 対象となる障害 | 等級区分 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害など | 1級〜6級 |
| 療育手帳 | 知的障害 | 重度(A)、その他(B)など(自治体により異なる) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 統合失調症、うつ病、発達障害など | 1級〜3級 |
手帳と障害年金の違い
よくある誤解ですが、精神障害者手帳を持っているからといって、自動的に障害年金(お金)がもらえるわけではありません。この2つは運営元も目的も異なる、まったく別の制度だからです。ざっくりと以下のように使い分けるとイメージしやすいでしょう。
- 精神障害者手帳(パスポート):税金が安くなったり、バス代が割引になったりと、「出ていくお金を減らす」ためのサービスを利用する権利証。また、障害者枠で就職するためのチケット。
- 障害年金(給与保障):病気や障害によって働くことが難しくなり、収入が途絶えてしまった場合に、「入ってくるお金を保障する」ための制度。
そのため、「手帳は2級だけど、年金は不支給だった(あるいは3級だった)」というケースは珍しくありません。手帳は「生活のしづらさ」を広く見ますが、年金は「稼ぐ能力がどれくらい落ちているか(労働能力の喪失)」をシビアに判定するためです。
手帳を持つ本当のメリットとは
手帳を取得することを「障害者というレッテルを貼られる」とネガティブに捉えてしまう方もいらっしゃいます。しかし、就労支援の現場では、手帳を「生きやすくなるためのツール」として捉えることをお勧めしています。
- 社会参加の促進:映画館や美術館の割引などが受けられます。「家に引きこもりがちだけど、割引があるならちょっと出かけてみようかな」という、外出のきっかけ作りになります。
- 経済的負担の軽減:所得税や住民税の控除、公共交通機関の割引などにより、固定費や生活コストを下げることができます。収入が不安定になりがちな時期の心強い支えです。
- 就労機会の拡大:一般枠では隠さなければならなかった「苦手なこと」を、障害者雇用枠では堂々と伝えられます。手帳は、配慮を受けながら働くための「通行手形」のようなものです。
精神科医
精神障害者手帳の取得は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づいて申請するものです。自分の状況や必要性に応じて、メリットとデメリットを検討した上で取得を決めることが大切です。
精神障害者保健福祉手帳の等級別メリット
精神障害者手帳のメリットは、等級が重くなるほど手厚くなるのが基本ですが、実は「2級と3級で税金の控除額は変わらない」といった意外なポイントもあります。ご自身の等級でどのような経済的サポートが受けられるのか、生活防衛の視点から見ていきましょう。
1級:最も手厚い「特別障害者」としての支援
1級は、常に手厚い介護や見守りを必要とする状態の方が対象となるため、税法上も「特別障害者」として扱われ、控除額が跳ね上がります。家計への負担を極力減らすためのセーフティネットが最も強力に働く区分です。
- 所得税の負担減:40万円(特別障害者控除)
- 住民税の負担減:30万円(特別障害者控除)
- 家計の固定費削減:NHK受信料(半額または全額※世帯要件あり)や、自動車税の減免などが受けられるケースが多い
ファイナンシャルプランナー
出典:
2級:1級に次ぐサポート範囲
2級は「日常生活に著しい制限がある」状態です。1級の「特別障害者」枠からは外れますが、それでも一般の方に比べれば十分な節税効果があります。また、福祉サービスの「境界線」になりやすいのがこの2級です。
- 所得税の控除:27万円(障害者控除)が所得から差し引かれる
- 住民税の控除:26万円の控除が適用される
- 資産形成の優遇:「新マル優制度」を使えば、350万円までの預貯金の利子が非課税になる
地域によっては、バスや電車などの交通費助成や医療費助成が「2級まで」と線引きされていることがあります。「2級だと利用できるサービス」を取りこぼさないよう、自治体のパンフレットを隅々までチェックすることをお勧めします。
3級:税金メリットは2級と同じ
3級は「軽度」とされますが、決してメリットが薄いわけではありません。実は、所得税や住民税の控除額に関しては、2級と全く同額です。「3級だから取っても意味がない」ということはなく、しっかりと家計の助けになります。
- 税金メリットは2級と同等:所得税27万円、住民税26万円の控除が受けられる
- 雇用のチャンス:「障害者雇用枠」での就職活動が可能になり、働き方の選択肢が増える
- 企業の割引:映画館や携帯電話料金など、民間企業の障害者割引は3級でも使えることが多い
精神保健福祉士
等級に関係なく受けられる共通のサービス
精神障害者手帳の等級に関わらず、手帳を持っていることで受けられる共通のサービスも多くあります。主な共通サービスは以下の通りです。
- 障害者雇用枠での就職機会:障害者手帳があれば、等級に関わらず障害者雇用枠での就職活動が可能
- 公共施設の利用料割引:美術館、博物館、動物園などの入場料割引
- 航空運賃の割引:国内線の航空運賃が3〜5割引(航空会社による)
- 携帯電話料金の割引:各社の障害者向け割引サービス
| 地域による支援の例 | 内容 | 対象等級 |
|---|---|---|
| 都営交通無料乗車券 | 都営地下鉄・バス等が無料で利用可能(東京都) | 全等級 |
| タクシー料金助成 | タクシー券の交付や料金の一部助成 | 主に1級・2級(自治体による) |
手帳を取得することは、「障害者」というレッテルを貼られることではありません。むしろ、生きづらさを抱えるあなたを守るための強力な「パスポート」を手に入れることです。等級や金額の多寡にかかわらず、利用できるサービスは遠慮なく活用してください。
それらがもたらす経済的なゆとりや周囲の配慮は、あなたがあなたらしく、心穏やかに暮らすための大切な土台になってくれるはずです。
精神障害者保健福祉手帳の経済的メリット
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)を取得することで、様々な経済的メリットを受けることができます。これらの経済的支援は、精神疾患を抱える方の生活を経済面から支えるための重要な制度です。ここでは、税金控除や公共料金の割引など、具体的な経済的メリットについて解説します。
税金控除(所得税・住民税)
精神障害者手帳をお持ちの方は、所得税と住民税において障害者控除を受けることができます。この控除により、納税額を軽減できるため、手取り収入が増加します。
| 区分 | 所得税控除額 | 住民税控除額 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 | 精神障害者手帳1級 |
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 | 精神障害者手帳2級・3級 |
税理士
毎月の「固定費」を確実に減らす
精神障害者手帳のメリットを最も実感しやすいのが、毎月必ず出ていくお金(固定費)の削減です。一つひとつは小さく見えても、年間で計算すると数万円単位の節約になるため、家計防衛の第一歩として手続きをお勧めします。
- NHK受信料:世帯構成などの条件を満たせば、受信料が半額、あるいは全額免除になります。手続き一つで毎月の支払いが軽くなる代表的なメリットです。。
- スマホ料金:ドコモ、au、ソフトバンクなどの大手キャリアでは、基本料金の割引や事務手数料の無料化を行っています。「格安SIM並み」の料金で手厚いサポートを受けられる選択肢として有効です。
「移動」のハードルを下げる
通院や気晴らしの外出など、移動にかかるコストも手帳があるだけで大きく変わります。「交通費がかかるから出かけたくない」という心理的なブレーキを外してくれる嬉しい制度です。
- バス・地下鉄:多くの自治体で、市営バスや地下鉄の運賃が割引(または無料パス発行)になります。特に定期的な通院がある方には大きな支えです。
- タクシー:乗車時に手帳を提示するだけで、運賃が1割引になる会社がほとんどです。体調が悪く電車に乗れない時の「緊急手段」として安く使えるのは安心感につながります。
- 飛行機:意外と知られていませんが、国内線であればJALやANAなどで大幅な割引(3〜5割程度)が受けられます。帰省や旅行のハードルが一気に下がります。
休日の「楽しみ」も割安に
社会参加のリハビリとして、外に出るきっかけを作ってくれるのも手帳の役割です。ご本人だけでなく、「付き添いの1名」も同額の割引になる施設が多いため、家族や友人を誘いやすくなるのも隠れたメリットです。
- 映画館:いつでも1,000円程度で鑑賞できます。レディースデーなどを気にせず、見たい時に安く見られるのは嬉しいポイントです。
- レジャー施設:動物園や水族館、ディズニーランドやUSJなどのテーマパークでも割引制度があります。人混みが苦手でも、「安く入れるなら空いている夕方から行ってみようかな」という選択もしやすくなります。
「医療費」の不安を解消する
精神障害者手帳をお持ちの方は、医療費の助成を受けられる場合があります。特に精神疾患の治療は長期にわたることが多いため、医療費の負担軽減は大きな経済的メリットとなります。
- 自立支援医療(精神通院医療):通常3割の窓口負担が「原則1割」になります。さらに世帯所得に応じて月額上限(2,500円〜など)が設定されるため、安心して治療を続けられます。
- 心身障害者医療費助成(マル障など):自治体によっては、自立支援医療を使った残りの自己負担分まで助成してくれる制度があります。地域によって名称や内容が異なるため、役所の窓口で「私の地域ではどうですか?」と確認してみましょう。。
このように、手帳は単なる証明書ではなく、生活のあらゆる場面であなたを支える「パスポート」のようなものです。遠慮なく活用して、浮いたお金やエネルギーを、ご自身の楽しみや回復のために使ってください。
精神障害者保健福祉手帳の就労支援
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)を持つことで、就労に関する様々な支援やサービスを受けることができます。これらの支援は、精神障害のある方が自分らしく働き、社会参加を実現するための重要な制度です。この章では、精神障害者手帳を活用した就労支援の内容や制度について解説します。
障害者雇用枠での就職
精神障害者手帳を持っていると、障害者雇用枠で就職することができます。これは「障害者雇用促進法」に基づく制度で、一定規模以上の企業に障害者雇用を義務付けているものです。
| 企業区分 | 法定雇用率(2025年現在) |
|---|---|
| 民間企業(従業員43.5人以上) | 2.5% |
| 国、地方公共団体 | 2.8% |
障害者雇用枠での就職の主なメリットは以下の通りです。
- 合理的配慮を受けやすい:障害の特性に応じて、労働時間の調整や業務内容の調整、通院のための休暇取得などの配慮を受けやすくなります。
- 採用選考で有利になる可能性:企業が法定雇用率達成のために障害者採用を積極的に行っているため、一般枠よりも採用される可能性が高まる場合があります。
就労支援カウンセラー
出典:
就労支援サービスの利用
精神障害者手帳を持っていると、障害者総合支援法に基づく様々な就労支援サービスを利用することができます。主な就労支援サービスには以下のようなものがあります。
- 就労移行支援:一般企業への就職を目指す障害のある方に、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練や、就職活動のサポート、就職後の職場定着支援などを提供します。
- 就労継続支援A型(雇用型):一般企業での就労が困難な方に、雇用契約を結んで働く場を提供します。
- 就労継続支援B型(非雇用型):一般企業での就労が困難な方に、雇用契約を結ばずに働く場を提供します。
関連記事

就労移行支援とは?対象者・支援内容から利用の流れまで徹底解説
就労移行支援は、障害者が一般企業で働くためのサポートを提供するサービスです。対象は18歳から65歳未満で、スキル習得や就職活動の支援が行われます。最大2年間の利用が可能で、個別の支援が提供されます。サービスは施設内での訓練や実習を通じて行われます。

就労継続支援A型とB型の違いを徹底解説|対象者・仕事内容・給与面の比較
就労継続支援A型は雇用契約を結び、最低賃金が保証される安定した働き方を提供します。一方、B型は契約なしで柔軟な支援を受けられますが、給与は低めです。どちらを選ぶかは、障害の特性や働く環境に応じて慎重に決めることが重要です。自分に合った支援を受けるために、各型の特徴をよく理解しましょう。
「合理的配慮」で、オーダーメイドの働き方を
障害者雇用枠の最大の強みは、企業に対して「合理的配慮」を求められる点です。これは単なる特別扱いではなく、あなたが本来の力を発揮するために必要な環境調整です。例えば、以下のような調整を堂々と相談できます
- 時間の融通:「満員電車を避けて1時間遅く出社する」「通院日は半休を取る」など、体調に合わせたスケジュール調整。
- 業務の取捨選択:「電話対応だけは免除してもらう」「マルチタスクを避け、一つずつ指示をもらう」など、苦手な作業の切り出し。
- 感覚過敏への対策:「パーテーションで視線を遮る」「ノイズキャンセリングイヤホンの使用を認めてもらう」など、安心できる物理環境の確保。
ハローワークなどの公的支援機関の活用
精神障害者手帳を持っていると、ハローワークなどの公的就労支援機関の専門的なサービスを受けることができます。
- ハローワーク:障害者専門の窓口があり、障害者向けの求人紹介や職業相談、職業紹介などのサービスを提供しています。
- 地域障害者職業センター:障害者職業カウンセラーによる専門的な職業相談、職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援などのサービスを提供しています。
- 障害者就業・生活支援センター:就業面と生活面の両方から一体的な支援を行っています。
精神障害者手帳を活用した就労支援は、就職前の準備から就職後の定着まで、幅広くサポートしてくれます。自分の状況や希望に合わせて、これらの支援制度を積極的に活用することで、より充実した職業生活を送ることができるでしょう。
精神障害者保健福祉手帳取得のデメリット
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)の取得には多くのメリットがある一方で、一部のデメリットや懸念点も存在します。手帳取得を検討される際には、これらの点も理解した上で判断することが大切です。ここでは、精神障害者手帳取得に関して考えられるデメリットや懸念点について解説します。
プライバシーの懸念
精神障害者手帳の取得に関して最も多く挙げられる懸念は、プライバシーに関するものです。精神疾患に対する社会的なスティグマ(偏見)が依然として存在する中、手帳の取得によって精神障害があることが周囲に知られることを心配する方は少なくありません。
- 職場での開示の問題:障害者雇用枠で就職する場合や、職場で合理的配慮を求める場合には、手帳の存在を会社に伝える必要があります。
- 周囲の人の反応への不安:家族や友人、同僚などに精神障害者手帳を持っていることが知られた場合の反応を懸念する方もいます。
精神保健福祉士
関連記事

オープン就労とは?メリット・デメリットと適性がある人の特徴
オープン就労は障害を開示して働く形態で、特性に合わせた配慮を受けながら働くことができます。障害者雇用枠での応募が一般的で、精神的負担の軽減や職場定着率の向上等のメリットがあります。デメリットとしては給与水準が低めで、職種選択肢が限られることが挙げられます。自分の障害特性や希望する働き方に合わせて選択することが重要です。

クローズ就労の徹底ガイド:メリット・デメリットと成功するためのポイント
クローズ就労は、自分の障害を企業に開示せず、一般雇用枠で働く方法です。これにより給与水準が高く、職種の選択肢が広がる反面、障害への配慮が受けられない、体調管理が難しくなるなどのデメリットもあります。成功するためには、適切な就職先選びや自己管理が重要です。自分の特性に合った働き方を選ぶことが長期的な活躍につながります。
2年ごとの更新は、正直「面倒」なイベント
手帳の最大のデメリットと言えるのが、2年ごとの更新手続きです。ただでさえ体調の波がある中で、期限を管理し、手続きを行うのは骨が折れる作業です。あらかじめコストと手間を把握しておきましょう。
- 診断書取得の負担:更新には医師の診断書が必要で、5,000円〜1万円程度の文書料がかかります。「高い」と感じるかもしれませんが、税金の控除や交通費の割引などで、年間トータルで見れば「元が取れる」ケースがほとんどです。
- 手役所へ行く手間:更新のためには、市区町村の窓口に出向いて申請書を提出する必要があります。
- うっかり失効のリスク:通知は来ますが、忙しいとつい後回しにしがちです。更新期間(有効期限の3ヶ月前から)に入ったら、スマホのカレンダーにアラートを入れるなど、自衛策が必要です。
心理的な抵抗感
精神障害者手帳の取得にあたっては、心理的な抵抗感を持つ方も少なくありません。これは社会的なスティグマだけでなく、自己認識に関わる問題でもあります。
- 自己認識の問題:「障害者」というラベルを自分に付けることへの抵抗感があります。
- 症状の一時性と手帳の必要性:特にうつ病や適応障害など、回復が見込まれる疾患の場合、「いずれ良くなるのに手帳が必要なのか」という疑問を持つことがあります。
精神科医
手帳を返還したい場合
精神障害者手帳を取得した後、症状が改善したり、ライフスタイルが変わったりして、手帳が不要になった場合は返還することが可能です。手帳の返還は比較的簡単な手続きで行うことができます。市区町村の窓口に手帳を持参し、返還の意思を伝えれば手続きが完了します。
デメリットや手間についてお伝えしましたが、手帳を取ったからといって、必ずしもそれを使わなければならない義務はありません。 取得だけしておき、普段は机の引き出しにしまっておく。そして本当に辛くなった時だけ、そっと取り出して助けを求める。そんな「お守り」のような持ち方も立派な活用法です。正解はありません。今のあなたの心が「これがあれば少し楽になりそうだな」と感じたタイミングが、申請のベストタイミングなのかもしれません。
最終的には、精神障害者手帳は自分らしく生きるための「ツール」の一つであり、取得するかどうかは個人の自由な選択に委ねられています。
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)の申請は、比較的シンプルな手続きですが、必要書類の準備や申請先の確認など、いくつかのステップが必要です。ここでは、申請に必要な書類や手続きの流れについて解説します。
申請に必要な書類
精神障害者手帳を申請する際には、以下の書類が必要となります。事前に準備しておくと、申請手続きがスムーズに進みます。
- 申請書:市区町村の窓口で入手するか、自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合があります。
- 診断書:精神保健指定医または精神障害の診断・治療に従事する医師が作成したものが必要です。初診日から6ヶ月以上経過していることが条件です。
- 本人の写真:縦4cm×横3cmの顔写真(原則として申請前6ヶ月以内に撮影したもの)が必要です。
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの身分証明書が必要です。
なお、精神障害を支給事由とする障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給している方は、診断書の代わりに「年金証書の写し」と「直近の年金振込通知書の写し」を提出することで申請が可能です。
医療ソーシャルワーカー
医師に「生活のしんどさ」をどう伝えるか
診断書は、手帳の等級(1〜3級)を決める最も重要な資料です。しかし、主治医は診察室でのあなたしか知りません。「家ではお風呂に入れない」「買い物ができない」といった生活の裏側にある具体的な困りごとは、自分から伝えない限り診断書には反映されません。
口頭で伝えるのが苦手な場合は、「生活の困りごとメモ」を事前に書いて渡し、「これを参考に診断書を書いてください」とお願いするのが確実です。これが等級判定の精度を大きく左右します。
申請から受け取りまでの「待ち時間」
書類を出してから手帳が手元に届くまでには、かなりのタイムラグがあります。「出したから明日から使える」わけではないので注意が必要です。
- 準備:診断書依頼から受け取りまで(約2週間〜1ヶ月)
- 申請:役所の障害福祉課などの窓口へ提出(郵送対応の自治体もあり)
- 審査:提出された書類は都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターに送られ、審査が行われます。
- 交付:「できましたよ」という通知が届き、窓口で受け取り
トータルで申請から2〜3ヶ月かかるケースも珍しくありません。就職活動や引っ越しなどで手帳を使いたい時期が決まっている場合は、逆算して早めに動き出しましょう。
精神障害者手帳の申請は、必要な書類を揃えれば比較的シンプルな手続きです。申請に不安がある場合は、主治医や医療機関のソーシャルワーカー、自治体の窓口などに相談しながら進めることをお勧めします。
精神障害者保健福祉手帳の更新と等級変更
精神障害者手帳は、一度取得すれば永続するものではありません。病状の変化を確認するため、原則として「2年ごと」に更新手続きが必要です(※有効期限は手帳に記載されています)。
また、「取得時よりも症状が重くなり、生活が苦しくなった」という場合は、更新時期を待たずに「等級変更」の申請を行い、今の状態に見合った等級(支援)を求めることも可能です。
更新手続きの方法と時期
精神障害者手帳の有効期限は、交付日から2年間です。継続して手帳を利用するためには、期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。手帳の更新申請は、有効期限の「3ヶ月前」から受け付けています。
ここで注意が必要なのは、「申請してから新しい手帳が届くまでのタイムラグ」です。診断書の作成に数週間、役所の審査に1〜2ヶ月かかることはザラにあります。「期限ギリギリでいいや」と後回しにしていると、新しい手帳が間に合わず、一時的に手元に有効な手帳がない「空白期間」ができてしまうリスクがあります。
精神保健福祉士
更新手続きに必要な書類は、初回申請とほぼ同じです。主な必要書類は以下の通りです。
- 更新申請書:市区町村の窓口で入手するか、自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合があります。
- 診断書:精神保健指定医または精神障害の診断・治療に従事する医師が作成したものが必要です。
- 本人の写真:縦4cm×横3cmの顔写真(申請前6ヶ月以内に撮影したもの)が必要です。
- 現在使用している手帳:更新時には現在の手帳を持参します。
更新時にも等級の審査が行われるため、症状の変化によって等級が変わる可能性があります。
症状が改善している場合は等級が下がることもありますし、悪化している場合は上がることもあります。
等級変更の申請方法
「症状が重くなり、今の等級では支援が足りない」と感じる場合は、更新時期を待たずに「等級変更」を申請できます。必要な書類セットは、通常の更新手続きとほぼ同じです。
等級変更の申請方法は、基本的に更新手続きと同じです。以下の書類が必要となります。
- 申請書:役所の障害福祉課などの窓口に置いてあります。「等級を変えたい」と伝えれば、その場で書き方を教えてもらえます(自治体サイトからダウンロードできる場合も多いです)。
- 「現状」を伝えた診断書:ここが最重要です。単に診断書を依頼するのではなく、「以前より生活のここが困難になったから、等級を見直したい」と医師に明確に伝え、その実情を反映してもらう必要があります。
- 顔写真(縦4cm×横3cm):新しい手帳を作るために必要です。最近は高価な証明写真機でなくても、スマホで撮影してコンビニ等でプリントした写真でOKとしてくれる自治体が増えています。
- いま持っている手帳:新しい手帳ができあがったタイミングで、窓口にて交換します(※申請中も、手元にある手帳はそのまま使えますのでご安心ください)。
精神科医
手帳を返還したい場合
精神障害者手帳は、症状が改善した場合や、何らかの理由で手帳が不要になった場合には、自主的に返還することができます。手帳の返還は義務ではなく、本人の意思に基づいて行うものです。
手帳を返還したい場合は、市区町村の障害福祉課窓口に、手帳を返還したい旨を伝え、現在所持している手帳を提出します。窓口で返還届などの書類に記入すれば手続きは完了です。
手帳を返還すると、手帳によって受けていた各種サービスや支援が受けられなくなります。将来的に再度手帳が必要になる可能性がある場合は、有効期限が切れるのを待って更新しないという選択肢もあります。
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)に関して、多くの方が抱える疑問や不安について、よくある質問とその回答をまとめました。手帳の取得を検討されている方や、すでに取得されている方の参考になれば幸いです。
手帳を取得すると給料が下がる?
精神障害者手帳を取得しても、それだけを理由に給料が下がることはありません。「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」により、障害を理由とした不当な差別的取扱いは禁止されています。給与や昇給に関して障害のない人と不当な差をつけることは、法律違反となります。
社会保険労務士
会社に手帳のことを隠していても問題ありませんか?
精神障害者手帳を取得したことを職場に伝える法的な義務はありません。手帳の取得や開示は個人の自由です。特に一般枠(クローズ就労)で働く場合、業務に支障がなければ、あえて伝える必要はないのです。ご自身にとって「伝えないほうが働きやすい」と判断したなら、その選択は守られます。
ただし、以下のような場合は開示を検討する価値があります。
- 障害者雇用枠で応募する場合:障害者雇用枠で応募する場合
- 「合理的配慮」を交渉したい場合:「通院で休みたい」「電話対応を外してほしい」といった配慮を会社に求める際、手帳があることが強力な根拠(証明書)になります。
障害年金と手帳、どちらか片方だけでもいいのですか?
はい、全く問題ありません。この2つは「運営元」も「審査基準」も違う別々の制度ですので、切り離して考えてください。
実際、「手帳は持っているけれど、年金は申請していない」という方は非常に多いです。それぞれの制度を使う目的が異なるため、ご自身の状況に合わせてチョイスして構いません。
3級でも障害者雇用枠で就職できる?
はい、精神障害者手帳3級をお持ちの方でも、障害者雇用枠での就職が可能です。障害者雇用促進法では、手帳の等級に関わらず、精神障害者手帳を持つすべての方を障害者雇用率の算定対象としています。
就労支援カウンセラー
手帳の診断書はどの医師に書いてもらえばいい?
精神障害者手帳の診断書は、原則として精神保健指定医または精神障害の診断・治療に従事する医師(精神科医や心療内科医など)に作成してもらう必要があります。疾患の種類によっては、てんかんは神経内科医、発達障害は小児科医、高次脳機能障害は脳神経外科医など、専門の医師が作成することも可能です。
精神障害者手帳に関するその他のご質問は、お住まいの市区町村の障害福祉課窓口、精神保健福祉センター、または主治医・医療機関のソーシャルワーカーなどに相談することをお勧めします。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を持つ方の社会参加と自立を支援するための重要なツールです。等級(1級~3級)に応じて様々な支援やサービスを受けることができ、税金控除や公共料金割引などの経済的メリット、障害者雇用枠での就職機会など多くのメリットがあります。
手帳の取得・更新には診断書などの書類が必要で、2年ごとの更新手続きが必要です。プライバシーの懸念などのデメリットもありますが、自分の状況に合わせて活用することで、精神疾患があっても充実した生活を送る助けとなるでしょう。
精神保健福祉士