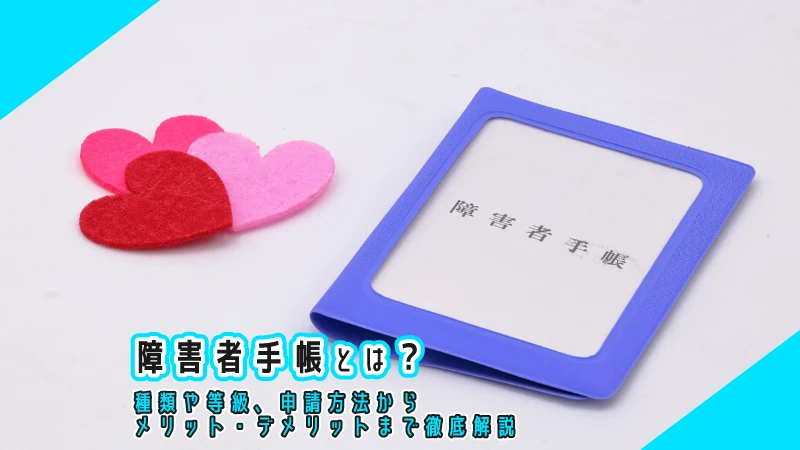- このコラムのまとめ
- 就労移行支援は、障害者が一般企業で働くためのサポートを提供するサービスです。対象は18歳から65歳未満で、スキル習得や就職活動の支援が行われます。最大2年間の利用が可能で、個別の支援が提供されます。サービスは施設内での訓練や実習を通じて行われます。
もくじ
もっと見る
就労移行支援の基本情報
就労移行支援とは、一般企業などへの就職を目指す障害のある方に向けて、就労に必要なスキルの習得から就職活動のサポート、就職後の定着支援まで一貫して支援する福祉サービスです。
就労移行支援とは何か
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づいて実施される障害福祉サービスの一つです。障害や難病のある方が就労するために必要な知識やスキルを身につけ、一般企業への就職を目指す場所として機能しています。
就労支援専門家
全国には約3,300か所の就労移行支援事業所があり、それぞれが特色あるプログラムを提供しています。
対象となる人の条件
就労移行支援を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。
- 原則18歳から65歳未満の方
- 一般企業などへの就職または仕事での独立を希望している方
- 精神障害、発達障害、身体障害、知的障害、難病などがある方
対象となる障害や疾患には、うつ病や双極性障害などの精神障害、ADHD・ASDなどの発達障害、肢体不自由などの身体障害、知的障害、難病などが含まれます。
障害者手帳がなくても利用できる場合がある点も特徴です。障害の確定診断があれば、手帳がなくても利用できるケースがあります。
利用できる期間と時間
就労移行支援の利用期間は原則として最長24か月(2年間)となっています。ただし、状況に応じて市区町村の判断により、最大12か月(1年間)の延長が認められる場合もあります。
利用時間については、事業所によって異なりますが、一般的には平日の日中に実施されており、多くの事業所が1日5〜6時間程度のプログラムを提供しています。利用開始時は週2〜3日から始め、徐々に週5日の利用に移行していくケースが一般的です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利用期間 | 原則24か月(最大36か月まで延長可能な場合あり) |
| 利用時間 | 事業所により異なる(一般的に1日5〜6時間程度) |
| 利用頻度 | 個人の状況に応じて調整(週2〜5日) |
就労移行支援は、就職準備から定着支援まで一貫したサポートを受けられる福祉サービスです。次章では、具体的にどのような支援が受けられるのかを詳しく見ていきます。
就労移行支援で受けられる6つのサポート
就労移行支援事業所では、障害のある方が一般企業に就職し、長く働き続けられるようさまざまな角度からサポートを行っています。ここでは代表的な6つのサポート内容を解説します。
①職業能力評価とアセスメント
就労移行支援の利用を始める際に、まず利用者一人ひとりの強みや課題、希望する働き方などを総合的に評価します。このアセスメントをもとに個別支援計画が作成され、以降の支援が進められます。
②社会人基礎スキルの習得
一般企業で働くために必要な基本的なスキルを身につけるプログラムが提供されます。
- ビジネスマナー(挨拶、身だしなみ、言葉遣いなど)
- コミュニケーションスキル
- 基本的なパソコンスキル
- 時間管理能力
③専門的な職業訓練
事業所によって、特定の職種や業界に特化した専門的な職業訓練を実施しています。IT・デジタル系、事務・経理系、クリエイティブ系など、自分の興味や適性に合わせたスキルを身につけることができます。
④就職活動のサポート
就職活動においては、履歴書・職務経歴書の作成から面接対策まで、就職活動のあらゆる場面でサポートを受けることができます。
キャリアカウンセラー
⑤職場体験・インターンシップの機会提供
多くの事業所では、実際の職場での就業体験やインターンシップの機会を提供しています。これにより、実際の仕事の流れや職場の雰囲気を事前に体験することができます。職場体験を経験することで、実際の就労をよりイメージしやすくなり、具体的な自信につながります。
⑥就職後の定着支援
就労移行支援の大きな特徴の一つが、就職後も継続的にサポートを受けられる点です。就職してからの6か月間は、就労移行支援事業所が定期的に職場を訪問したり、面談を実施したりして、職場定着をサポートします。
さらに、6か月経過後も最大3年間は「就労定着支援」というサービスを利用することができます。長期にわたって支援が受けられるため、職場での不安や悩みがあっても安心して相談することができます。
就労移行支援を利用するメリット
就労移行支援を利用することで、障害のある方が一般企業に就職するための様々なメリットがあります。単に就職先を紹介してもらうだけでなく、働き続けるための総合的なサポートを受けられる点が大きな特徴です。
自分のペースで就職準備ができる
就労移行支援の最大の特徴は、一人ひとりの状況や体調に合わせて、無理のないペースで就職準備ができることです。体調や障害特性に配慮した個別支援計画が作成され、最長2年間という期間で、焦らずに準備を進められます。
就労移行支援利用者(30代・女性)
専門スタッフによる手厚いサポート
就労移行支援事業所には、障害者の就労支援に精通した専門スタッフが在籍しています。就労支援員、職業指導員、生活支援員など、それぞれの専門分野から多角的なサポートを受けることができます。
同じ悩みを持つ仲間との交流
就労移行支援事業所では、同じように就労を目指す仲間と交流する機会が得られます。障害や病気があるために就職に不安を抱える人同士で、悩みを共有したり励まし合ったりすることで、精神的な支えになります。
就職後も継続的な支援が受けられる
就労移行支援の大きなメリットの一つが、就職後も継続的なサポートを受けられる点です。就職後6か月間は定着支援が受けられ、その後も「就労定着支援」を利用すれば最大3年間のサポートが受けられます。
適切な職場とのマッチングが実現しやすい
就労移行支援事業所では、利用者の特性や希望を把握した上で、適切な職場とのマッチングを図ります。自分に合った職場で働くことができれば、能力を発揮しやすく、職場定着率も高まります。
自己理解が深まり自信につながる
就労移行支援の利用を通じて、自分の障害特性や強み・弱みについての理解が深まります。これは単に就職するためだけでなく、その後の人生においても大きな財産となります。
自己理解と対処法の獲得が、就労の場面だけでなく、生活全般における自信につながっていきます。
就労移行支援における支援スタッフの役割
就労移行支援事業所では、さまざまな専門性を持ったスタッフが連携して利用者の就労をサポートしています。それぞれのスタッフが担う役割を理解することで、どのような支援が受けられるかをより具体的にイメージできるでしょう。
サービス管理責任者
サービス管理責任者(通称:サビ管)は、就労移行支援事業所における支援の要となる存在です。利用者一人ひとりの状況に合わせた個別支援計画の作成や、サービス全体の質の管理を担当しています。
サービス管理責任者
職業指導員
職業指導員は、就労に必要な知識や技能を習得するための直接的な指導を行うスタッフです。ビジネスマナーや基本的なPC操作から、専門的な職業スキルまで、様々なプログラムや訓練を実施します。
生活支援員
生活支援員は、利用者の日常生活や健康管理、メンタル面のサポートを主に担当するスタッフです。就労を目指すためには、安定した生活基盤が欠かせません。生活リズムの調整や体調管理、ストレス対処法など、生活面の相談に応じています。
就労支援員
就労支援員は、実際の就職活動や就職後の定着支援を中心に担当するスタッフです。企業とのパイプ役となり、利用者と企業の橋渡しをする重要な役割を担っています。履歴書や職務経歴書の作成支援、面接対策、求人情報の収集と紹介などを行います。
その他の専門スタッフ
事業所によっては、以下のような専門スタッフが在籍していることもあります。
- 精神保健福祉士:精神障害のある方の支援に専門的な知識を持つ資格者
- 社会福祉士:福祉全般に関する専門知識を持つ資格者
- 臨床心理士・公認心理師:心理面のサポートを専門とする資格者
- キャリアカウンセラー:就職・キャリア形成に関する専門的な相談員
就労移行支援では、これらの専門スタッフがチームとなって多角的な支援を提供しています。スタッフとの良好な関係を築き、積極的にコミュニケーションを取ることで、より効果的な支援を受けることができるでしょう。
利用者の体験談と成功事例

就労移行支援を利用して実際に就職を果たした方々の体験談は、これから利用を検討している方にとって大きな参考になります。ここでは、さまざまな障害特性を持つ方々の就労成功事例を紹介します。
精神障害から一般企業へ就職した例
Kさん(40代・男性)双極性障害
Kさんは約1年間の利用を経て、障害者雇用枠で大手企業のバックオフィス部門に就職しました。自己理解プログラムで調子の波を客観的に把握できるようになり、服薬管理と睡眠の重要性を実感し、生活リズムを整える習慣が身についたことが成功の鍵でした。
発達障害の特性を活かした就職例
Mさん(20代・女性)は、大学卒業後に発達障害(ASD・ADHD)と診断されました。就労移行支援で約1年半過ごし、その間に自分の特性と向き合いながら、強みを活かせる仕事を探していきました。
細部への注意力と集中力という特性を活かし、出版社のデジタルコンテンツ部門で校正・チェック業務を担当する仕事に就くことができました。「特性を直す」のではなく「特性を活かせる場所を見つける」という考え方に出会えたことが大きな転機となりました。
職場定着に成功した利用者の声
Tさん(30代・男性)統合失調症
Tさんは就労移行支援での1年間の利用を経て事務職に就職し、現在は2年以上安定して勤務を続けています。ストレスのサインに早く気づく方法を学び、症状が出始めたときの対処法を身につけたこと、そして就職後も就労定着支援を利用して定期的な面談で不安を解消できたことが長期間働き続けられている理由です。
就労移行支援利用者の成功事例から学ぶポイント
- 自己理解を深める:自分の障害特性や体調の波を客観的に把握し、対処法を身につけることが大切です。
- 強みを活かせる仕事を探す:障害による制限だけでなく、特性を強みとして活かせる職場や職種を見つけることが成功のカギです。
- 継続的な支援の活用:就職後も就労定着支援などを利用し、困ったときに相談できる環境を維持することが職場定着につながります。
就労移行支援を利用するまでの流れ
就労移行支援の利用を検討している方にとって、「どのような手続きが必要なのか」「どのくらいの期間がかかるのか」といった疑問は大きな関心事でしょう。ここでは、就労移行支援を利用し始めるまでの一般的な流れを解説します。
福祉相談支援員
STEP1:医療機関の受診と診断
就労移行支援は障害福祉サービスの一つであるため、利用するためにはまず医療機関を受診し、障害や疾患についての診断を受ける必要があります。すでに通院中の方は、主治医に就労移行支援の利用を検討していることを伝え、必要な診断書や意見書の作成を依頼しましょう。
STEP2:事業所の見学と体験利用
医療機関での受診と並行して、実際に利用する就労移行支援事業所を探しましょう。事業所選びは重要なポイントですので、複数の事業所を見学・比較することをお勧めします。多くの事業所では見学に加えて、1日から数日間の体験利用も受け付けています。
STEP3:障害福祉サービス受給者証の申請
就労移行支援を利用するためには、お住まいの市区町村から「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。申請書を提出すると、後日、自治体の職員による訪問調査が行われます。受給者証の交付までは地域によって差がありますが、一般的には申請から1~2か月程度かかります。
STEP4:利用契約と個別支援計画の作成
受給者証が交付されたら、利用を希望する就労移行支援事業所と正式に利用契約を結びます。契約後、事業所のサービス管理責任者が中心となって「個別支援計画」を作成します。これはあなたの障害特性や希望、課題などを踏まえた上で、どのような支援を行っていくかを具体的に記した計画書です。
STEP5:通所開始と職業訓練
すべての手続きが完了すると、いよいよ就労移行支援事業所への通所が始まります。
通所初日には、オリエンテーションがあり、その後、個別支援計画に基づいた訓練プログラムへの参加が始まります。
通所開始時は週2~3日程度の通所から始め、徐々に日数や時間を増やしていくケースが一般的です。
就労移行支援事業所の選び方
就労移行支援事業所は全国に約3,300か所あり、それぞれが特色を持ったプログラムやサポート内容を提供しています。自分に合った事業所を選ぶことは、就労成功への重要なステップです。ここでは、事業所選びのポイントを解説します。
事業所選びで押さえるべきポイント
就労移行支援事業所を選ぶ際には、以下のポイントを総合的に考慮することが大切です。自分にとって特に重要な条件から優先順位をつけて検討しましょう。
- 通いやすさ(立地・アクセス)
- プログラム内容(基本スキル・専門スキル)
- 事業所の雰囲気やスタッフの対応
- 就職実績や定着率
- 障害特性への理解度や対応力
就労支援コンサルタント
特色で選ぶ(得意分野・訓練内容)
就労移行支援事業所は、提供するプログラムや得意とする支援分野に特色があります。IT・プログラミング、オフィスワーク、クリエイティブ分野、接客・販売、軽作業・製造など、自分の興味や目指したい職種に合わせた事業所を選ぶことが効果的です。
また、発達障害特化型、精神障害特化型など、特定の障害に特化したプログラムやサポート体制を持つ事業所もあります。自分の障害特性に合った環境を選ぶことも重要です。
地域で選ぶ(通いやすさ・アクセス)
通いやすさは事業所選びの重要なポイントです。長期間(最長2年間)通うことを考えると、通所にかかる時間や交通費、アクセスの便利さを十分に考慮する必要があります。
通所の負担が大きすぎると、それだけで疲れてしまい、訓練に集中できなくなる可能性があります。
実績で選ぶ(就職率・定着率)
事業所の就職実績や定着率は、支援の質を判断する重要な指標です。就職率が全国平均(約50〜55%)を大きく下回っていないか、就職後の定着率はどうか、希望する業界への就職実績はあるかなどを確認しましょう。
他の就労支援サービスとの違い
障害のある方の就労を支援するサービスには、就労移行支援のほかにもいくつかの種類があります。それぞれのサービスには目的や対象者、支援内容に違いがあるため、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。
就労継続支援A型・B型との違い
就労系障害福祉サービスの中で、特によく混同されるのが「就労移行支援」と「就労継続支援」です。名称が似ていますが、目的や対象者、サービス内容には大きな違いがあります。
| 比較項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 一般企業への就職 | 雇用契約に基づく継続的な就労機会の提供 | 雇用契約なしでの就労機会の提供 |
| 対象者 | 一般就労を希望し、訓練により就職が見込める人 | 一般企業での就労が困難だが、雇用契約を結んで働ける人 | 一般企業での就労が困難で、雇用契約を結ぶことも難しい人 |
| 利用期間 | 原則2年以内 | 制限なし | 制限なし |
障害福祉サービス相談員
就労定着支援との違い
就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般企業に就職した障害のある方が、長く働き続けられるようサポートする障害福祉サービスです。2018年に創設された比較的新しいサービスで、職場定着に重点を置いています。
就労移行支援が就職前の支援であるのに対し、就労定着支援は就職後の支援です。両者は連続性のあるサービスとして、一貫したサポートを提供しています。
ハローワークや職業訓練との違い
ハローワークは求人情報の提供や職業紹介、職業訓練(ハロートレーニング)は特定の技術や資格の取得に特化したプログラムを提供しています。就労移行支援はこれらと比べて、障害特性に配慮したきめ細かな支援や、生活面も含めた総合的なサポートが特徴です。
就労移行支援の利用料金
就労移行支援は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つであり、利用料金の仕組みは他の障害福祉サービスと共通しています。ここでは、就労移行支援の利用にかかる費用について詳しく解説します。
基本利用料の仕組み
就労移行支援の基本利用料は、原則として利用したサービスの1割を自己負担する仕組みになっています。しかし、利用者の経済的負担を軽減するため、所得に応じた月額の負担上限額が設定されており、多くの方が無料または少額の負担で利用できるようになっています。
| 区分 | 世帯の状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満) |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
この仕組みにより、実際には約9割の利用者が無料(0円)で就労移行支援を利用しているという調査結果もあります。
就労移行支援事業所スタッフ
出典:
その他かかる費用(交通費・食費など)
就労移行支援の基本利用料以外にも、実際の利用にあたっては以下のような費用がかかる場合があります。
- 交通費:自宅から事業所までの交通費(自治体によっては助成制度あり)
- 食費:事業所での昼食代(1食300〜500円程度が一般的)
- 教材費・活動費:プログラムによっては教材費などが別途必要な場合あり
これらの費用は事業所や自治体によって取り扱いが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
就労移行支援に関するよくある質問
就労移行支援の利用を検討する際には、様々な疑問や不安が浮かぶものです。ここでは、よく寄せられる質問とその回答を紹介します。
Q1. 障害者手帳がなくても利用できる?
就労移行支援は、障害者手帳の有無にかかわらず利用できる可能性があります。医師の診断書や意見書があれば、利用が認められるケースが多いです。詳細はお住まいの市区町村の障害福祉課に相談してみるのが確実です。
就労移行支援利用者(20代・女性)
Q2. 利用中の工賃はもらえる?
就労移行支援は基本的に職業訓練の場であり、給与のような形での賃金は発生しません。ただし、事業所によっては企業から請け負った作業の対価として工賃が発生する場合があります。金額は事業所や作業内容によって異なりますが、一般的には月額数千円程度であることが多いです。
Q3. 仕事や学校と併用できる?
就労移行支援の利用条件として、一般的には「失業状態であること」が前提となっているため、原則として就労しながらの利用はできません。ただし、短時間のアルバイトや休職中の場合など、例外的に併用が認められることがあります。
Q4. 期間内に就職できなかった場合は?
就労移行支援の利用期間は原則として2年間までですが、期間内に就職できなかった場合にも、以下のような選択肢があります。
- 市区町村の判断により、最大1年間の延長が認められる場合がある
- 就労継続支援A型・B型などの他の障害福祉サービスへの移行を検討する
- 一定期間経過後に再度就労移行支援を利用できる可能性がある
Q5. 就職後もサポートを受けられる?
就職後も6か月間は就労移行支援事業所による定着支援を受けることができます。その後も「就労定着支援」というサービスを利用すれば、最長3年間のサポートが受けられます。
まとめ:自分に合った就労移行支援を見つけよう
就労移行支援は、障害や難病のある方が一般企業で働くための「橋渡し」となる重要なサービスです。自分のペースで準備を進められる環境、専門スタッフによるサポート、就職後の継続的な支援など、多くのメリットがあります。
成功のカギは、自分に合った事業所選びにあります。通いやすさ、障害特性への理解、プログラム内容、雰囲気などを総合的に判断し、複数の事業所を見学・体験した上で選ぶことをお勧めします。
就労支援専門家