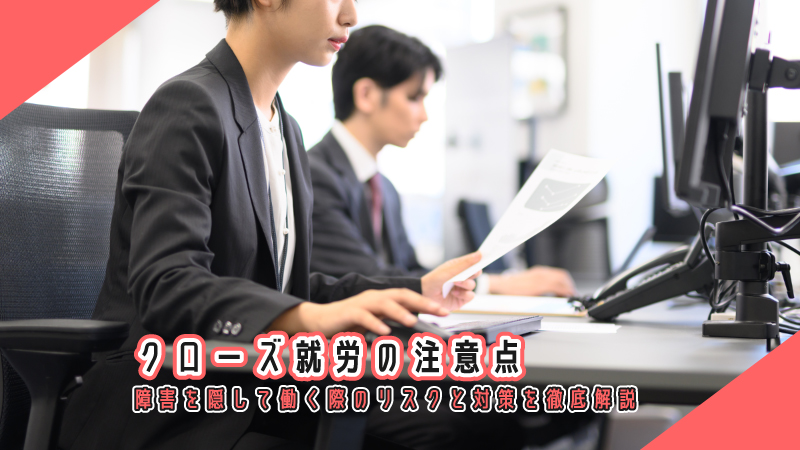
- このコラムのまとめ
- クローズ就労とは障害を隠して一般枠で働く方法です。法的には問題ありませんが、配慮が受けられない、体調管理が難しい、バレるリスクなど様々な注意点があります。この記事では、クローズ就労の定義から成功させるための準備、セミクローズなどの中間的選択肢、具体的なリスクと対策まで徹底解説します。
もくじ
もっと見る
クローズ就労とは?基本的な概念を理解しよう
障害のある方が就職を考える際、「オープン就労」と「クローズ就労」という2つの選択肢があります。クローズ就労とは、企業に障害を開示せずに一般枠で働く方法です。障害について隠したまま一般の従業員と同じ条件で仕事をするという働き方です。
クローズ就労の定義と一般就労との違い
クローズ就労について正しく理解するために、基本的な概念を確認しておきましょう。
- クローズ就労:障害を企業に開示せず、一般枠で就職すること
- オープン就労:障害を企業に開示して就職すること(障害者雇用枠だけでなく、一般枠でも障害を開示する場合を含む)
就労支援専門家
クローズ就労を選ぶ際は、自分の障害の特性と業務内容が適合するかどうかを慎重に検討する必要があります。障害を隠して働くということは、特別な配慮や支援を受けずに仕事をこなさなければならないということです。
クローズ就労をする人の割合と実態
2017年の厚生労働省の調査によると、障害を持ちながら就職した方のうち、約18%(5〜6人に1人)が障害を隠して一般企業に就職しています。一般求人の方が種類が多く、障害を開示する法的義務がないことから、クローズ就労を選ぶ方は少なくありません。
| 就労タイプ | 3ヶ月後の定着率 | 1年後の定着率 |
|---|---|---|
| 障害者雇用枠(オープン) | 約85% | 約70% |
| 一般企業(クローズ) | 約50% | 約30% |
出典:
注目すべきは、クローズ就労を選んだ方の職場定着率です。上記のデータを見ると、クローズ就労での定着率は3ヶ月後には約50%、1年後には約30%にまで下がってしまいます。オープン就労と比較して継続率が大幅に低いことがわかります。
このことからもわかるように、クローズ就労はメリットがある一方で、長期的に働き続けるためには様々な課題があります。自分の特性をよく理解し、適切な準備をすることが重要です。
クローズ就労を成功させるための準備と対策
クローズ就労は定着率が低い傾向がありますが、適切な準備と対策を行うことで成功の可能性を高めることができます。ここでは、障害を隠して就労する際に必要な具体的な準備と対策を紹介します。
自己理解を深め、自分の限界を知る
クローズ就労を成功させる第一歩は、自分自身の障害特性を正確に理解することです。自分の強みと弱みを客観的に把握しておくことで、無理なく働き続けられる職場環境を選ぶことができます。
- 自分の障害がどのような場面で影響するかを具体的にリストアップする
- 過去の経験から、どのような環境・業務で調子を崩したかを振り返る
- 自分の体調のサインを把握し、無理をする前に対処できるようにする
無理のない職場環境と業務内容を選ぶ
自己理解ができたら、次は自分の特性に合った職場環境と業務内容を慎重に選ぶことが重要です。就職前に以下のポイントをチェックしましょう。
- 業務内容が自分の強みを活かせるものか
- 苦手な業務が主な仕事ではないか
- 勤務時間や通勤時間が自分の体力的に無理のない範囲か
- 福利厚生が充実し、有給休暇が取りやすい環境か
就労支援カウンセラー
ストレス管理と健康維持の方法
クローズ就労では、障害を隠しながら働くこと自体が大きなストレスになります。長期的に働き続けるためには、効果的なストレス管理と健康維持の方法を確立しておくことが不可欠です。
- 定期的な通院と服薬管理を徹底する
- 休日や勤務後の効果的なリラックス方法を見つける
- 睡眠、食事、運動など基本的な健康管理を怠らない
クローズ就労を成功させるためには、周到な準備と日々の自己管理が欠かせません。自分の特性を理解し、それに合った職場選びと対策を行うことで、長期的に安定して働ける可能性が高まります。ただし、状況が厳しくなった場合は、オープン就労への切り替えも一つの選択肢として考えておくことも大切です。
クローズとオープン、中間的な選択肢も考える
障害のある方の就労は「完全にクローズ」か「完全にオープン」かの二択だけではありません。実際には、その中間にも様々な選択肢があります。ここでは、より柔軟な働き方の選択肢を紹介します。
セミクローズという選択肢
「セミクローズ」とは、完全にクローズでも完全にオープンでもない、中間的な開示方法です。例えば、人事部や直属の上司だけに障害を開示し、同僚には開示しないという方法があります。
- 人事部と直属の上司のみに開示する
- 上司だけに開示し、人事部にも他の同僚にも開示しない
- 特定の信頼できる同僚にのみ開示する
- 障害名は開示せず、必要な配慮のみを伝える
セミクローズの利点は、必要な配慮を受けつつも、障害に対する不必要な偏見を避けられる点です。
特に発達障害やうつ病など、外見からは分かりにくい障害の場合、必要な人にだけ伝えることで、より自然な職場関係を築ける可能性があります。
状況に応じた開示のタイミング
障害の開示は、就職前に一度決めたら変更できないものではありません。状況に応じて開示の範囲やタイミングを柔軟に考えることも重要です。
| 開示のタイミング | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 入社前・面接時 | 最初から必要な配慮を受けられる | 採用に不利に働く可能性がある |
| 内定後・入社前 | 採用は決まっているため安心 | 内定取り消しのリスク(まれ) |
| 入社後・試用期間中 | 職場環境を確認してから判断できる | 「隠していた」という印象を与える |
上司だけに伝えるという方法
セミクローズの中でも、特に「上司だけに伝える」という方法は多くの方が選ぶ選択肢です。直属の上司は業務調整の権限を持っているため、実質的な配慮を受けやすいというメリットがあります。
キャリアカウンセラー
クローズでもオープンでもない中間的な選択肢を検討することで、自分に最適な働き方を見つけられる可能性が広がります。完全なクローズ就労に不安がある場合は、これらの選択肢も視野に入れてみましょう。
関連記事

オープン就労とは?メリット・デメリットと適性がある人の特徴
オープン就労は障害を開示して働く形態で、特性に合わせた配慮を受けながら働くことができます。障害者雇用枠での応募が一般的で、精神的負担の軽減や職場定着率の向上等のメリットがあります。デメリットとしては給与水準が低めで、職種選択肢が限られることが挙げられます。自分の障害特性や希望する働き方に合わせて選択することが重要です。

クローズ就労の徹底ガイド:メリット・デメリットと成功するためのポイント
クローズ就労は、自分の障害を企業に開示せず、一般雇用枠で働く方法です。これにより給与水準が高く、職種の選択肢が広がる反面、障害への配慮が受けられない、体調管理が難しくなるなどのデメリットもあります。成功するためには、適切な就職先選びや自己管理が重要です。自分の特性に合った働き方を選ぶことが長期的な活躍につながります。
クローズ就労は違法なのか?法的な観点から検証
障害を隠して就職することに対して、「違法ではないか」「虚偽申告にならないか」と不安を感じる方は少なくありません。このセクションでは、クローズ就労の法的位置づけについて解説します。
障害を隠して就職することの法的位置づけ
結論から言えば、障害を隠して就職すること自体は違法ではありません。障害の有無を会社に申告することを義務づける法律はないからです。
- 障害者雇用促進法は、企業に対して障害者の雇用を義務づけるものであり、障害者個人に対して障害の開示を義務づけるものではない
- 労働契約法や労働基準法においても、求職者に障害の開示義務を定めた条文はない
- 障害者差別解消法は、むしろ障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁止している
労働問題専門弁護士
虚偽申告との境界線
クローズ就労と虚偽申告の境界線は、どこにあるのでしょうか。この点を明確にしておくことは重要です。
| 状況 | 法的リスク | 対応方法 |
|---|---|---|
| 障害について直接質問された | 虚偽申告のリスクあり | 誠実に回答するか、答えたくない旨を伝える |
| 質問されていない | リスク低い | 自分から申告する義務はない |
| 就業規則に虚偽申告の禁止がある | 後にトラブルとなるリスクあり | 就業規則を事前に確認する |
重要なのは、企業には「安全配慮義務」があり、労働者には「自己保健義務」があるという点です。障害の影響で体調管理がうまくできず欠勤が多かったり、顧客や会社に悪影響を及ぼすと判断された場合、解雇される可能性もあります。
クローズ就労を選択する場合は、自分の障害が業務に与える影響を客観的に評価し、業務を適切に遂行できると判断できる場合に限るべきでしょう。
クローズ就労の最大の注意点:7つのリスクと対策
クローズ就労は一般枠での就職というメリットがある一方で、いくつかの重要なリスクも伴います。ここでは、クローズ就労における主要なリスクとその対策について解説します。
注意点①:必要な配慮が受けられない
クローズ就労の最大の注意点は、障害に対する必要な配慮が受けられないことです。企業側は障害の存在を知らないため、特別な対応や業務調整を期待することはできません。
対策:自分の特性を踏まえて、特別な配慮がなくても対応できる職場環境と業務内容を事前に見極めることが重要です。
注意点②:体調不良時や通院に理解が得られにくい
障害を開示していない場合、通院や体調管理のための配慮を求めることが難しくなります。
産業保健師
注意点③:外部支援機関のサポートが受けられない
クローズ就労では、就労支援機関やジョブコーチなどの外部支援を活用しにくくなります。
対策:職場外で支援機関と定期的に連絡を取り、状況報告や助言を受ける関係を維持しましょう。
注意点④:税金関連で障害がバレるリスク
年末調整での障害者控除申告や障害年金の受給が、障害を知られるきっかけになることがあります。
注意点⑤:健康診断や診断書でバレる可能性
企業の健康診断や休職・病欠時の診断書提出が、障害を知られるきっかけになることがあります。
注意点⑥:突発的な体調悪化への対応が難しい
障害を隠している状態で突発的な体調悪化が起きた場合、適切な対応を受けにくいという問題があります。
注意点⑦:精神的ストレスの増加
障害を隠し続けること自体が大きな精神的ストレスとなり、それが体調悪化を招くという悪循環に陥るリスクがあります。
対策:プライベートな時間で十分にリラックスする機会を設け、ストレスを解消する方法を見つけましょう。
どんな状況で障害がバレやすい?具体的なケース
クローズ就労を選択した場合でも、様々な状況で障害が職場に知られてしまう可能性があります。ここでは、実際に障害がバレやすい具体的なケースについて解説します。
自己申告が必要になる場面
会社生活の中で、自己申告が必要となる場面は思いのほか多く、そのような機会に障害が明らかになることがあります。
- 入社時の健康保険加入手続きでの既往歴記入
- 社内アンケートでの障害者雇用状況確認
- 健康診断前の問診票への記入
- 社内イベント参加時の健康状態確認
対処法:自己申告が必要な場面では、業務に直接影響する範囲に限定して回答することを検討しましょう。
同僚との交流や業務遂行の中でのサイン
日常の業務や同僚との交流の中で、無意識のうちに障害の特性が表れることがあります。
| 特性が表れやすい場面 | バレるリスク |
|---|---|
| チームでの作業 | コミュニケーションの取り方の違いが目立つ |
| 飲み会・社内イベント | 疲労やストレスが表れやすい、薬の服用が難しい |
| 緊急対応・急な変更 | 混乱やパニックが生じやすい |
就労支援専門家
医療機関への受診と会社への報告
定期的な通院や急な体調不良による受診が、障害を知られるきっかけになることがあります。
- 定期的な通院のための休暇取得パターンが目立つ
- 病欠が続き、診断書の提出を求められる
- 傷病手当金の申請で診断名が会社に伝わる
- 急な体調不良で救急搬送され、会社に連絡が行く
対処法:可能であれば通院は勤務時間外や休日に設定する、診断書の内容を業務に影響する範囲に限定してもらうよう医師に相談するなどの工夫をしましょう。
まとめ:クローズ就労を検討している方へのアドバイス
クローズ就労は一つの選択肢であり、自分の状況や価値観に合わせて慎重に判断することが大切です。最後に重要なポイントをまとめます。
就労支援専門家
自分の障害特性をよく理解し、無理なく働ける環境を選ぶこと。そして必要に応じて専門家や支援機関に相談することで、より良い就労生活を送れるでしょう。あなたの就労が実り多く、充実したものになることを願っています。



