公開日:2025.09.19
精神障害者が長く働き続けるための環境づくり~企業の取り組みと支援制度
- ホーム
- コラム
- 「就労支援」のコラム
- 精神障害者が長く働き続けるための環境づくり~企業の取り組みと支援制度
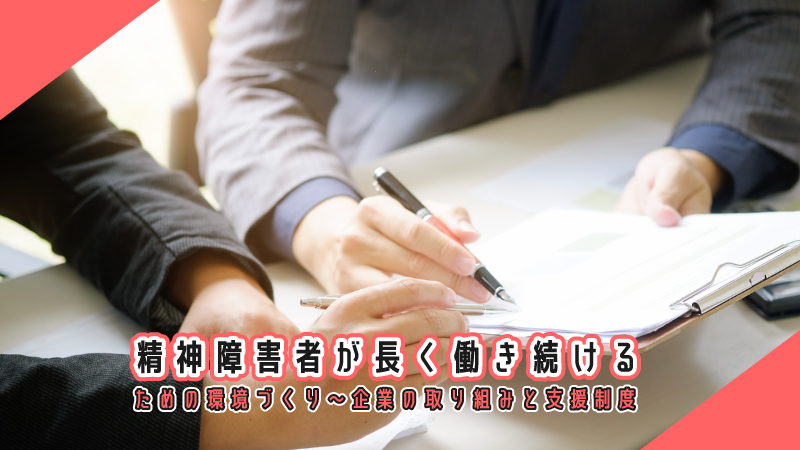
- このコラムのまとめ
- 精神障害者が職場で長く働き続けるために必要な環境づくりを解説。障害特性の理解と適切な配慮、柔軟な勤務体制、社内の理解促進、外部機関との連携など、企業の取り組みと、当事者自身の自己管理スキルを紹介。企業と精神障害者双方がWin-Winとなる雇用関係を構築するためのポイントを網羅しています。
精神障害者雇用の現状と課題
精神障害者の雇用を取り巻く環境は、近年大きく変化しています。法定雇用率の算定対象に精神障害者が加わったことで雇用数は増加傾向にありますが、一方で職場定着率の低さなど、様々な課題も顕在化しています。ここでは、精神障害者雇用の現状と主な課題について解説します。
精神障害者の雇用数と定着率の実態
厚生労働省の「障害者雇用状況の集計結果」によれば、民間企業における精神障害者の雇用数は年々増加しています。令和5年の調査では、精神障害者の雇用者数は約13万人に達し、平成30年の障害者雇用促進法改正前と比較して約2.6倍に増加しています。
一方で、精神障害者の職場定着率は他の障害種別と比較して低い状況にあります。障害者職業総合センターの調査によれば、就職後1年経過時点での職場定着率は以下のような結果となっています。
- 身体障害者:60.8%
- 知的障害者:68.0%
- 精神障害者:49.3%
- 発達障害者:71.5%
このデータから、精神障害者は就職後1年以内に約半数が離職していることがわかります。
障害者雇用コンサルタント
出典:
法定雇用率の引き上げと企業に求められる対応
厚生労働省は、企業に義務付けられている障害者の法定雇用率を2026年(令和8年)に向けて段階的に引き上げる方針を発表しています。
| 時期 | 法定雇用率 | 対象となる事業主の範囲 |
|---|---|---|
| 令和5年度まで | 2.3% | 従業員43.5人以上の企業 |
| 令和6年4月〜 | 2.5% | 従業員40人以上の企業 |
| 令和8年7月〜 | 2.7% | 従業員37.5人以上の企業 |
出典:
令和6年4月からは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者も、障害者雇用率の算定対象(0.5人としてカウント)となります。精神障害者は体調管理の観点から短時間勤務を希望するケースが多いため、この制度変更は精神障害者の雇用促進に大きく寄与すると考えられます。
精神障害の特性と就労における困難さ
精神障害者が就労上で直面する主な困難さには、以下のようなものがあります。
- 体調や状態に波があり、勤怠や成果が不安定になりやすい
- 疲れやすく、長時間の勤務や連続勤務が難しい場合がある
- ストレスに弱く、環境変化や人間関係の変化に敏感
- 周囲からは障害が見えにくく、理解されにくい
これらの困難さは障害特性に由来するため、完全に克服することは難しいものです。しかし、適切な配慮や環境調整によって、その影響を最小限に抑えることは可能です。企業側の理解と配慮、そして本人の自己管理能力の向上が、安定した就労の鍵となります。
精神障害者雇用の現状と課題を正しく理解することは、効果的な支援体制を構築するための第一歩です。次章では、精神障害者が長く働くための具体的な職場環境づくりについて詳しく見ていきます。
精神障害者が長く働くための職場環境づくり
精神障害者が職場で長く働き続けるためには、その特性を理解した上で適切な環境を整備することが不可欠です。企業側の配慮と工夫により、精神障害者の職場定着率を向上させることが可能になります。
障害特性の理解と適切な配慮の提供
精神障害者が安定して働くためには、まず企業側がその障害特性を正しく理解することが基本となります。精神障害には様々な種類があり、それぞれ異なる特性と必要な配慮があります。
障害者雇用コンサルタント
これらの特性を理解した上で、合理的配慮を提供することが重要です。令和6年4月からは、障害者を雇用する全ての事業主に合理的配慮の提供が義務付けられています。
業務内容・勤務時間の柔軟な調整
精神障害者が長く働き続けるためには、業務内容や勤務時間を柔軟に調整することが効果的です。特に、体調の波がある精神障害者にとって、働き方の柔軟性は職場定着の大きな鍵となります。
- 短時間勤務からスタートし、徐々に時間を延ばす
- 体調に合わせてテレワークを併用する
- 定期的な通院のための休暇取得を認める
- 本人の強みを活かした業務を割り当てる
実際に、多くの企業では法改正に対応して週10時間以上20時間未満の短時間勤務制度を導入し始めています。令和6年4月からは、この時間帯で働く障害者も雇用率の算定対象となるため、精神障害者の雇用機会が広がることが期待されます。
コミュニケーション体制の構築
精神障害者が職場で安心して働くためには、適切なコミュニケーション体制の構築が欠かせません。精神障害の特性により、コミュニケーションに困難を抱えることがあるため、企業側の工夫が求められます。
- 定期的な面談の実施:週1回など定期的に面談の時間を設け、業務の進捗や体調の変化を確認する
- 複数の報告手段の用意:口頭だけでなく、メールやチャットなど本人が使いやすい方法を認める
- 明確で具体的な指示:抽象的な表現を避け、具体的な手順や期限を示す
特に重要なのは、本人が体調の変化や困りごとを「言いやすい雰囲気」を作ることです。問題が大きくなる前に早期対応できるよう、オープンなコミュニケーション環境を整えましょう。
ストレスマネジメントと体調管理のサポート
精神障害者にとって、ストレスの管理と体調の維持は長く働き続けるための重要な要素です。企業側からの適切なサポートにより、安定した就労が可能になります。
- ストレスのサインを早期に発見するための観察と声かけ
- 疲労が蓄積する前に休憩を取れる仕組みづくり
- 静かに休める場所の確保
ある企業では、精神障害者の体調管理をサポートするために「健康管理シート」を導入し、日々の体調を5段階で記録する取り組みを行っています。これにより本人の自己管理能力が向上するとともに、上司も体調変化に早めに気づけるようになりました。
キャリアパスの設計と成長機会の提供
精神障害者も他の従業員と同様に、キャリアアップの機会を求めています。障害者総合研究所の調査によると、精神障害者の約8割がキャリアアップに関心を持っていることが分かっています。長期的な就労を促進するためには、成長の機会を提供することが重要です。
精神障害当事者
精神障害者のキャリア形成を支援するための取り組み例は以下の通りです。
- 本人の特性や強みを活かした業務の割り当て
- 段階的なスキルアップを目指した研修プログラムの提供
- 能力や成果に応じた公平な評価制度の構築
ある会社では、障害のある従業員も職位や成長に応じて個人の目標を設定し、その達成度を評価する「目標管理制度」を導入しています。こうした取り組みにより、障害者の長期的なキャリア形成が実現しています。
精神障害者が長く働き続けるための職場環境づくりは、決して特別なことではありません。一人ひとりの特性を理解し、適切な配慮と成長の機会を提供することが、結果的に企業全体の働きやすさにもつながります。次章では、これらの取り組みを実践している企業の具体的な事例を紹介します。
企業の実践的取り組み事例
精神障害者の雇用を成功させている企業では、様々な工夫や取り組みを行っています。ここでは、実際に精神障害者の長期就労を実現している企業の事例を紹介し、具体的な取り組みから学びます。
大手企業における成功事例
大手企業では、専門的な知識や豊富なリソースを活かした先進的な取り組みが行われています。これらの事例は、規模の大小に関わらず参考になる点が多くあります。
金融業S社:専門家を含む「精神障害者雇用促進チーム」の結成
S社は特例子会社として設立され、精神障害者の雇用促進と職場定着に積極的に取り組んでいます。同社の特徴的な取り組みは以下の通りです。
- 精神科医や行政担当者を含む「精神障害者雇用促進チーム」の結成
- 外部委託の精神科医やカウンセラーによる月1回のカウンセリング実施
- 体調や状況に応じて勤務時間を調整できる短時間勤務制度の導入
S社 人事担当者
中小企業での工夫された取り組み
大企業と比べてリソースが限られる中小企業でも、創意工夫により精神障害者の雇用を成功させている事例があります。中小企業ならではの「小回りの利く」取り組みに注目しましょう。
印刷業M社:業務細分化とチーム制の導入
従業員50名のM社では、以下のような工夫で精神障害者の雇用定着を実現しています。
- 印刷工程を細かく分解し、障害特性に合った業務を割り当て
- 健常者と精神障害者がペアを組むバディ制度の導入
- 作業マニュアルの視覚化(写真や図を多用)
M社では「障害者だから」と特別扱いするのではなく、一人の従業員として期待と役割を明確に伝えることを大切にしています。その結果、精神障害者の平均勤続年数は5年を超え、高い定着率を実現しています。
テレワーク・短時間勤務を活用した事例
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、テレワークや短時間勤務を活用した精神障害者雇用が広がっています。これらの柔軟な働き方は、体調管理が重要な精神障害者にとって大きなメリットがあります。
IT企業D社:フルリモートでの障害者雇用
D社では、精神障害者の特性に合わせたフルリモート勤務を実現し、高い生産性と定着率を達成しています。
- オンライン上での業務指示と報告システムの構築
- タスク管理ツールを活用した業務の可視化
- 1日2回の定例オンラインミーティングによる進捗確認
精神障害のある従業員
専門チームを設置した組織的サポート体制
精神障害者の雇用を組織的に支援するため、専門チームを設置している企業も増えています。こうした体制により、個人に頼らない持続可能なサポートが可能になります。
製造業D社:雇用前実習と個別ケース会議の実施
D社では、早くから精神障害者雇用に取り組み、組織的なサポート体制を構築しています。
- 雇用前に実習期間を設け、仕事の適性や職場への適応能力を見極め
- 精神障害者ごとに組まれたチームによる「個別ケース会議」の開催と情報共有
- 従業員が相談に使えるカウンセリングルームの設置
D社では、問題の共有と対応を目的とした「精神障害者雇用促進チーム」を結成し、仕事とのミスマッチが発生した場合に迅速に配置変更するなど、状況に応じた細やかな対応を行っています。このような組織的な取り組みにより、精神障害者の適性や能力に合わせた業務割り当てが可能となり、安定した職場定着を実現しています。
これらの事例から分かるように、精神障害者の雇用を成功させるためには、企業規模や業種に応じた創意工夫が必要です。
どの事例にも共通しているのは、障害特性の理解に基づいた環境整備と、組織全体でサポートする体制づくりです。次章では、このような職場環境を支える社内の理解促進と協力体制の構築について詳しく見ていきます。
社内の理解促進と協力体制の構築
精神障害者が職場に定着し長く働き続けるためには、社内の理解促進と協力体制の構築が不可欠です。精神障害者の職場定着率が低い主な原因の一つに「職場の人間関係や雰囲気になじめなかった」という理由が挙げられています。このような課題を解決するために、企業全体で取り組むべき方策を紹介します。
従業員への啓発と研修の実施
精神障害者との円滑な協働を実現するためには、まず全従業員に対する精神障害についての正しい知識と理解を促進することが重要です。効果的な啓発・研修の取り組みを見ていきましょう。
- 精神障害の種類と特性(うつ病、統合失調症、双極性障害など)
- 精神障害の症状と行動特性の理解
- 精神障害者の強みと可能性
- 精神障害者との適切なコミュニケーション方法
精神障害者と協働する一般社員
単なる知識の提供だけでなく、精神障害当事者による体験談を聞く機会や、ロールプレイングなどの実践的な研修を取り入れることで、より効果的な理解促進が可能になります。
職場の受け入れ体制づくりのポイント
精神障害者を温かく迎え入れる職場環境を整えるためには、以下のようなポイントに注意して受け入れ体制を構築することが大切です。
配属前の準備
精神障害者を新たに配属する前に、受け入れ側の準備を整えておくことが重要です。
- 配属予定の部署メンバーへの事前説明と研修
- 本人の特性と必要な配慮事項の共有(本人の同意を得た範囲で)
- 業務内容と役割分担の明確化
- サポート担当者やメンターの選定
バディ制度やメンター制度を導入することで、精神障害者が職場に馴染みやすくなります。一対一でサポートする関係を築くことで、本人が相談しやすい環境を作ることができます。
管理職の役割と支援スキル
精神障害者の雇用において、直属の上司やマネージャーの役割は特に重要です。管理職が適切な知識と支援スキルを身につけることで、チーム全体のパフォーマンスが向上します。
- 精神障害の特性を理解し、個人の強みと弱みを把握する
- 先入観や偏見を持たず、一人の社員として適切に評価する
- 必要な配慮を提供しつつ、過度な特別扱いはしない
- 体調の変化に敏感に気づき、早期対応を心がける
精神障害者を部下に持つ管理職
トラブル発生時の対応方法
どんなに準備を整えていても、職場ではトラブルが発生する可能性があります。精神障害者の特性に起因する問題が生じた場合の適切な対応方法を知っておくことが重要です。
- 体調不良のサインを早期に発見するための観察ポイントを共有する
- 本人が休憩や早退を申し出やすい雰囲気を作る
- 緊急時の連絡先(家族や支援機関など)を確認しておく
- 休養が必要な場合の業務引継ぎ方法を決めておく
社内の理解促進と協力体制の構築は、一朝一夕に実現するものではありません。
継続的な取り組みと改善を通じて、精神障害者が働きやすい職場環境を整えていくことが大切です。そうした環境は、精神障害者だけでなく、全ての従業員にとっても働きやすい職場となり、組織全体の生産性向上にもつながります。
外部機関との連携と活用できる支援制度
精神障害者の雇用を成功させるためには、企業内の取り組みだけでなく、外部の専門機関との連携や各種支援制度の活用が重要です。適切な外部リソースを活用することで、企業の負担を軽減しながら、精神障害者の長期就労を実現することができます。
医療機関・支援機関との効果的な連携方法
精神障害者の安定した就労を支えるためには、医療機関や支援機関との連携が欠かせません。それぞれの機関の役割を理解し、効果的に連携することが重要です。
| 機関の種類 | 役割・支援内容 |
|---|---|
| 医療機関 (精神科・心療内科) |
・診断・治療・投薬管理 ・病状や治療状況の情報提供 ・就労に関する医学的見地からの助言 |
| 障害者就業・生活支援センター | ・就職前の準備から就職後の定着支援 ・生活面の支援 ・企業と障害者の調整 |
| 障害者職業センター | ・職業評価 ・職業準備支援 ・ジョブコーチ支援 |
製造業 人事担当者
就労定着支援サービスの活用
障害者総合支援法に基づく「就労定着支援」は、障害者の職場定着を支援するためのサービスです。2018年の法改正で新設され、精神障害者の職場定着率向上に大きく貢献しています。
- 対象者:就労移行支援等を利用して一般企業に就職した障害者
- 利用期間:最長3年間
主な支援内容はこちらです。
- 月1回以上の職場訪問や電話等による状況確認
- 企業や家族との連絡調整
- 生活リズムや体調管理の支援
就労定着支援サービスを効果的に活用するためには、障害者の採用前から支援機関と連携し、三者面談の機会を定期的に設けることが重要です。
障害者雇用に関する助成金・奨励金制度
精神障害者の雇用を促進し、職場環境を整備するための各種助成金・奨励金制度があります。これらを活用することで、企業の経済的負担を軽減しながら、より良い就労環境を整えることができます。
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース):障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主を支援
- 障害者作業施設設置等助成金:障害者が作業を容易に行えるよう配慮された施設や設備の設置・整備を行う事業主を支援
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者トライアルコース):障害者を試行的・段階的に雇い入れる事業主を支援
障害者職業生活相談員の役割と活用
障害者を5人以上雇用する事業所には、「障害者職業生活相談員」の選任が法律で義務付けられています。この相談員は社内における障害者支援の中心的役割を担います。
- 障害者の職業生活に関する相談・指導
- 障害特性に応じた業務の選定・調整
- 職場環境の整備や合理的配慮の提案
- 障害者と上司・同僚との間の調整
- 外部支援機関との連携窓口
相談員がその役割を十分に果たすためには、障害者職業生活相談員資格認定講習の受講や、精神障害に関する専門知識を学ぶ研修への参加など、継続的なスキルアップが重要です。
外部機関との連携や支援制度の活用は、精神障害者の雇用を成功させるための重要な要素です。
企業だけで抱え込まず、専門機関の知見や公的支援制度を積極的に活用することで、精神障害者が長く安心して働ける環境を整えることができます。
精神障害者本人が長く働くための自己管理とスキル
精神障害者が職場で長く働き続けるためには、企業側の配慮や環境整備だけでなく、本人自身の自己管理とスキルアップも重要です。ここでは、精神障害者が職場で安定して働き続けるために身につけておきたい自己管理能力とスキルについて解説します。
自己理解と障害受容の重要性
長く働き続けるための第一歩は、自分自身の障害特性を理解し、適切に受容することです。自己理解が深まることで、必要な配慮を職場に伝えやすくなり、自分に合った働き方を選択できるようになります。
精神障害のある会社員(勤続7年)
効果的な自己理解と障害受容のためのポイントは以下の通りです。
- 自分の障害特性と症状の変化パターンを把握する
- 得意なことと苦手なことを客観的に整理する
- 自分に必要な配慮や環境を明確にする
体調管理とストレス対処法
精神障害者にとって、日々の体調管理とストレスへの対処は、安定した就労を継続するための基本です。特に精神障害は体調の波があるため、自分の状態を把握し、適切に管理する能力が重要になります。
精神障害者が日常的に実践したい体調管理のポイントは以下の通りです。
- 規則正しい生活リズムを保つ(睡眠、食事、休息のバランス)
- 服薬管理を徹底し、医師の指示通りに薬を服用する
- 体調記録ノートをつけ、症状の変化や兆候を把握する
- 定期的な通院を欠かさず、医師に正確な状況を伝える
職場でのストレスを適切に管理するための具体的な方法を身につけることも重要です。
- ストレスの早期発見:自分のストレスサインを知り、早めに対処する
- リラクゼーション技法の習得:深呼吸、筋弛緩法、マインドフルネスなど
- 適切な境界線の設定:無理な要求は断る、自分のペースを守る
職場でのコミュニケーションスキル
職場での円滑なコミュニケーションは、精神障害者が働き続けるための重要な要素です。特に自分の状態や必要な配慮を適切に伝えるスキルは、誤解や行き違いを防ぎ、良好な職場関係を構築するのに役立ちます。
自分の障害や必要な配慮について、どのように職場に伝えるかは重要な課題です。以下のポイントを参考にしましょう。
- 障害について全てを話す必要はなく、業務に関連する部分を中心に伝える
- 「できないこと」だけでなく「できること」「工夫すればできること」も伝える
- 具体的な配慮の内容を提案する
統合失調症のある事務職
キャリア形成と自己成長の方法
精神障害者も、他の従業員と同じように自己成長やキャリアアップを望んでいます。長期的な就労を実現するためには、自分自身のキャリアについて考え、計画的に成長していくことが重要です。
精神障害があっても、自分らしいキャリアを築くことは可能です。以下のポイントを参考にしましょう。
- 自分の強みや適性を活かせる分野を見つける
- 無理のないペースで段階的にスキルアップを目指す
- 短期・中期・長期の目標をバランスよく持つ
職場での長期就労とキャリアアップのために、以下のような具体的な取り組みが効果的です。
- 自己学習の習慣化:業務に関連する知識やスキルを継続的に学ぶ
- 社内研修への積極的な参加:可能な範囲で研修に参加し、スキルを高める
- 障害者向けキャリア支援サービスの活用:障害者職業センターなどのサービスを利用する
これらの自己管理能力とスキルは、一度に身につけるものではありません。
日々の小さな努力の積み重ねが、長期的な就労継続とキャリア形成につながります。また、すべてを一人で抱え込まず、必要に応じて周囲のサポートを求めることも大切です。
7. まとめ:精神障害者と企業がWin-Winとなる雇用関係の構築
本記事では、精神障害者が長く働き続けるための環境づくりについて多角的に解説してきました。精神障害者の雇用成功には、企業側の適切な配慮と環境整備、本人の自己管理能力の向上、そして外部支援の活用がバランスよく機能することが重要です。
障害者雇用コンサルタント
精神障害者と企業のWin-Win関係構築は、単なる法定雇用率達成を超えた価値を生み出します。多様性を尊重する組織文化は、すべての従業員にとって働きやすい職場環境の基盤となり、企業の持続的な成長にもつながるのです。





